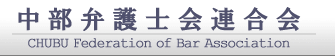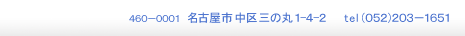2024年(令和6年)1月に発生した能登半島地震及び同年9月に発生した奥能登豪雨に関し、石川県は、内閣府との協議の上で、いずれの災害に関しても、応急仮設住宅(建設型・賃貸型)の供与期間として、災害時に持ち家に居住していた被災者については入居日から2年以内、災害時に賃貸住宅や公営住宅に居住していた被災者については入居日から1年以内と、災害時の居住形態により一律に被災者が入居できる期間に差を設けている。
入居期間に差を設けた背景には、災害時に賃貸住宅(公営住宅を含む)に居住していた被災者については、持ち家の居住者と異なり修理や建替えが不要となるため、災害後の住まいの再建にかかる期間、例えば別の賃貸住宅を確保するまでの期間が、持ち家に居住していた被災者よりも短くて済むとの想定があるものと推察される。
しかし、もともと能登半島、特に奥能登地域は、都市部などと比べて賃貸住宅の数が少ない上、マグニチュード7.6(最大震度7)という巨大地震である能登半島地震及び複合災害となった線状降水帯による奥能登豪雨により、それらの賃貸住宅自体も甚大な被害を受け、多くの住宅が居住できない状態となった。また、居住可能な状態で残った賃貸住宅についても、被災地の復旧、復興に関わる関係者の使用に供されるなどした結果、被災者が元の被災地で新たに賃貸住宅を確保することは極めて難しい状況にある。
そのため、『災害時に賃貸住宅に住んでいた者は被災後に自宅の修理や建替えが不要であり、他の賃貸住宅に転居すればよい結果、住まいの再建にかかる期間が持ち家の被災者よりも短く済む』という想定は誤っている。
もちろん、石川県金沢市などの都市部を含め日本全体を見渡せば、賃貸住宅は数多く存在する。しかし、そのことを理由に災害時に賃貸住宅に居住していた被災者が応急仮設住宅に居住できる期間を一律に短縮するのは、被災者をして元の居住地域や故郷を離れさせ、遠方の地域への転居を強いることに等しい。これは、憲法で保障された個人の尊厳(憲法第13条前段)や幸福追求権(憲法第13条後段)、居住・移転の自由(憲法第22条第1項)などの制約にも関わる重大な問題である。
また、応急仮設住宅に入居できる期間を含め被災者の住居の確保は、災害で住まいを奪われた被災者の生命・身体の安全や、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利である生存権(憲法第25条第1項)に深くかかわることから、被災者各人の個別的な事情及び被災地の実情を一切斟酌することなく、一律に、持ち家か賃貸住宅かという被災時の居住形態により別異の取扱いをしている点については、憲法が定める法の下の平等(憲法第14条第1項)の観点からも大きな問題である。
したがって、国及び石川県は、令和6年能登半島地震及び奥能登豪雨災害の被災者に対する応急仮設住宅の供与期間に関し、被災時の居住形態を理由として、供与期間に差を設ける取扱いを早急に是正する必要がある。
被災時の居住形態を理由とした応急仮設住宅の供与期間に関する別異の取扱いの問題だけでなく、能登半島地震および奥能登豪雨の被災地では、いまだに多くの被災者が元の住まいに戻ることや新たな住まいを見つけることが困難な状況が続いている。
被災者が被災地に戻って生活再建をするか否かを検討するにあたっては、それに先立って地域の復興計画や公共施設の再築計画等が明らかになっている必要がある。地域がどのようになっていくかがわからない状況の中で、被災地にとどまるのか否か、仮にとどまるとして、自宅を再建するか否か、どこに再建するか、賃貸物件を借りるか否か、どこに借りるかといった判断をすることは困難である。
被災から約1年2か月が経過した現時点においても、被災地では、生活に不可欠なライフラインの復旧や公費解体手続等が遅れ、住まいや事業の再建のために必要な建築業者や専門家等が不足しているだけでなく、必要とされる公共工事等の遅れなども生じており、復旧・復興にはさらなる長期間を要する可能性が高い。
復興まちづくりや災害公営住宅の建築も進んでいない状況において仮設住宅からの退去を迫ることは、被災者に被災地からの転居を余儀なくさせ、発災前の仕事や学校、コミュニティを失わせることとなり、ひいては地域コミュニティ自体が損なわれるおそれもある。
このような問題を避けるためには、被災の実情、復興状況等に鑑みつつ、応急仮設住宅に入居する被災者が、生活再建の場をじっくりと検討し、希望する恒久的な住まいが確保できるようになるまで応急仮設住宅が供与される必要がある。
ところが、冒頭で述べたとおり、石川県は、内閣府との協議によって応急仮設住宅の供与期間を2年以内ないしは1年以内としており、期間制限の対象となる被災者の一部の退去期限が本年3月末日に迫っている状況にある。
したがって、国及び石川県は、応急仮設住宅に入居する被災者に対し、被災時の居住形態の如何に関わらず、被災者が生活再建の場をじっくりと検討できるよう、原則2年以内にこだわることなく、希望する恒久的な住まいが確保できるようになるまで可能な限り供与期間を延長する必要がある。
以上の理由から、当連合会としては、国及び石川県に対し、令和6年能登半島地震及び奥能登豪雨災害の被災者に対する応急仮設住宅供与期間に関し、被災時の居住形態を理由とした別異の取扱いを是正すると共に、被災者が希望する恒久的な住まいが確保できるようになるまで可能な限り供与期間を延長することを求めるものである。
2025年(令和7年)2月22日
中部弁護士会連合会
理事長 野坂 佳生