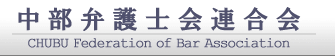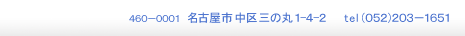わが国では、法律上同性同士(以下「同性カップル」という。)による婚姻は認められていない。このような法制度の下、同性カップルは、法律上異性同士(以下「異性カップル」という。)が婚姻によって享受できる数々の法的利益−例えば、配偶者としての相続権、配偶者控除、配偶者ビザの取得、共同養子縁組等−を享受することができないという不利益を被っている。また、法的利益だけではなく、民間企業の福利厚生、住居の契約、医療機関での面会や治療方針への同意、子どもの学校での保護者としての扱い等、社会生活のさまざまな場面においても、同性カップルは、家族として扱われず、あるいは、扱われないことのおそれにさらされるという不利益を被っている。
そして、法律婚制度が認められないことによる不利益は、このような法的利益や社会生活上の利益を享受できないことだけではない。婚姻には、人生を共にすることで得られる充実感、安心感等という個人の尊厳と結び付いた本質的価値があり、法律婚制度には、当事者間の人的結合関係が法的に保護され、公証されることによって安定的で充実した社会生活を送る基盤となるという個人の尊厳と結び付いた本質的価値がある。同性カップルは、このような法律婚の本質的価値を享受することができないのであり、個人の尊厳が損なわれているという重大な不利益を受けている。
これらの数々の重大な不利益がある一方で、同性カップルに対し法律婚制度の適用を認めたとしても、これによる具体的な弊害や侵害される反対利益は想定し難い。
同性カップルに対し法律婚制度の適用を認めないことは、合理的な根拠なく同性カップルを差別的に取り扱うものであるから、憲法14条1項に違反する。
また、憲法24条1項は、人と人とが性愛に基づき親密な継続的共同生活を営む人的結合関係を法律が「婚姻」として制度化することを前提に、「婚姻」をするかどうか、いつ誰と「婚姻」するかにつき、個人の自由な意思で決定できる権利(婚姻の自由)を保障するものである。すなわち、婚姻は当事者の合意の成立に基礎を置くものであり、当事者の人格的な結合を本質的要素とする。この人格的結合という婚姻の本質的な要素において、同性カップルと異性カップルとの間で差異はない。
したがって、同性カップルにも婚姻の自由が保障されるべきであり、現行法が同性カップルに対し法律婚制度の利用を認めないことは、その婚姻の自由を直接的に制約するものであり、憲法24条1項に違反する。
さらに、親密な他者を人生の伴侶として共同生活関係を送るか否かの選択は、自らの人生をどう生きるかという自己決定と密接に結びつくものであり、この意味で憲法24条1項の定める「婚姻の自由」は、憲法13条が保障する幸福追求権を基礎とした人格権的な重要な権利であると位置づけられる。現行法が同性カップルに対し法律婚制度の利用を認めないことは、同性の相手と婚姻を望む者の幸福追求の途を閉ざすものであり、個人の尊厳を深く傷つけるものであるから、憲法13条にも違反する。
このように、複数の点で憲法違反の疑いがある現行制度の違憲性を問う訴訟(いわゆる「結婚の自由をすべての人に」訴訟)が、2019年から、全国5つの地方裁判所(札幌・東京・名古屋・大阪・福岡)で提起され、憲法判断が相次いで示されてきた。2025年3月までに、6つの地方裁判所判決のうち5つが憲法違反との判断を示し、さらにその後の控訴審においては、現在までに出された5つの高裁判決すべてが憲法違反との判断を示している。その内容についても、地裁判決では法律婚以外の制度でも違憲性が解消できる可能性があると読める判断が続いたことに対し、高裁判決の中には、法律婚以外では違憲性が解消されないと解される判断が示されたものも複数あり、婚姻の平等に関する司法の判断は大きく前進している。
しかしながら、これらの司法判断において、同性カップルが法律婚制度を利用することができないことによる重大な不利益が繰り返し指摘されているにもかかわらず、国会は婚姻の平等に向けた具体的な議論を進めていない。国は早急に現在の状況の違憲性を解消しなければならない。
このような国の在り方とは対照的に、地方自治体レベルでは、2015年に東京都渋谷区、世田谷区で開始されたパートナーシップ制度が急速に広がっている。一部の自治体では、子を含む家族関係を認める「ファミリーシップ制度」も導入されるなど、同性カップルを家族として社会的に承認する動きが進んでいる。2025年6月30日現在、ファミリーシップ制度を含むパートナーシップ制度等の導入自治体数は530を超え、人口カバー率は約92%に達している。
また、国際的には、同性婚を法的に認める国と地域は、2025年1月23日現在で39となり、アジアでも台湾、ネパール、タイが法制化を進めている。国際連合の人権機関をはじめとする諸機関からもわが国に対し、性的指向および性自認に基づく差別を解消する措置を求める勧告が繰り返し出されている。
このような国内外の動きの中、2023年に性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(いわゆる「LGBT理解増進法」)が制定・施行されたものの、性的指向・性自認の分野におけるわが国の立法状況は不十分といわざるを得ない。今もなお、同性カップルは法律婚制度を利用することができず、様々な場面で重大な不利益を被り続けているのであるから、婚姻の平等を実現するための法制度の整備は、国が直ちに取り組むべき緊急の課題というべきである。
当連合会は、国に対し、同性カップルによる婚姻を可能とする民法等の法改正、すなわち婚姻の平等を実現することを速やかに行うことを強く求めるものである。
以上のとおり決議する。
以 上
2025年(令和7年)10月17日
中部弁護士会連合会
提 案 理 由
第1 はじめに
わが国では、現在に至るまで、法律上同性同士(以下「同性カップル」という。)による婚姻(以下「同性婚」という。)が法制度として認められていない。そのため、同性カップルは、異性カップルであれば当然に享受できる法的利益・社会的承認から排除され、家族としての生活基盤を安定的に築くことができない状態に置かれている。
婚姻は、当事者の人格的結合を公的に承認し、その共同生活を法的に保護する制度である。このような婚姻制度からの排除は、単に個別の権利利益の欠缺という次元にとどまらず、当事者の尊厳・アイデンティティに直接的かつ継続的な損害をもたらす深刻な人権侵害である。
日本弁護士連合会は、2019(令和元)年7月18日付「同性の当事者による婚姻に関する意見書」において、憲法 13条(個人の尊重・幸福追求権)、14条1項(法の下の平等)、24条(婚姻の自由と個人の尊厳)の各観点から、同性婚を認めるべきであることを明確に示し、国に対し速やかな法整備を求めた。
同年に全国5地裁で提起された「結婚の自由をすべての人に」訴訟では、これまでに地裁・高裁合わせて計11件の判決が出されているところ、そのうち、10件で憲法違反の判断が示されてきた。とりわけ控訴審では、札幌、東京(一次訴訟)、福岡、名古屋、大阪の5高裁すべてが違憲の判断を示した。このように違憲判断が連続して言い渡される事態は、憲政史上稀であり、同性カップルを排除する現行の婚姻制度が、正当性、合理性を有しないことが明らかな段階に至っていることを示している。
第2 同性同士の婚姻を認めない現行法の諸規定が憲法に違反すること
1 憲法 14条1項違反
性的指向は本人の意思により選択・変更し得ない属性であり、歴史的に偏見の対象とされてきた点に鑑みれば、これに基づく別異取扱いの合憲性判断にあっては厳格に審査されなければならない。
婚姻制度によって、婚姻当事者は、親子法上の推定、相続法上の地位、税・社会保障上の配偶者保護、在留資格など、社会生活の様々な場面での権利利益を享受することができる。また、婚姻が当事者の人格的結合を国家が公的に承認し、その関係を社会全体に対して証明する機能を有するということも、個人の人格的生存にとって重要な利益である。
性的指向のみによって同性カップルを婚姻制度から排除することは、これらの重要な権利利益へのアクセスを直接的、全面的かつ永続的に制限するものであるから、侵害される権利利益は極めて重大である。
他方で、同性婚を認めることによる現実的かつ具体的な弊害はおよそ認めがたく、重要な権利利益を全面的に排除することを正当化し得る根拠はない。 したがって、同性婚を認めていない民法、戸籍法の婚姻に係る規定は、憲法14条1項に違反する。
2 憲法24条1項違反
憲法 24 条は、戦後の家制度を廃止し、婚姻を当事者の自由かつ平等な合意に基づく人格的結合として再構成することに主眼を置いた規定である。すなわち、憲法24条の核心は、当事者の選択の自由(だれと婚姻するか、またはしないの自由)と、個人の尊厳・本質的平等の実現にある。同性カップルを婚姻制度から排除することは、当事者の人格的結合に国家が公的承認を与えないという意味で、婚姻に関する当事者の選択の自由、個人の尊厳を損なうものである。また、同性婚を認めないことは、婚姻が持つ当事者間の関係を公証する機能をも否定することになる。
この点、憲法 24条1項の「両性」や「夫婦」という文言が、異性間の関係を想定したものとの見解もある。しかし、これらの文言は、憲法制定当時、異性間の婚姻が社会通念上当然に想定されていたために用いられたにすぎない。同条が設けられた趣旨は、明治民法下の家制度を廃止し、個人の尊厳と法の下の平等という基本原則を婚姻制度において具体化することにあるから、同条の文言は同性婚を殊更に排除する意図を含むものではない。同性愛が人間の通常の性的指向の一つであり、異性愛と同等に尊重されるべきという規範意識が形成されている現在において、「両性」「夫婦」という文言は「両当事者」「双方」の意味と解するべきである。
また、異性間でも生殖能力の有無にかかわらず婚姻は認められることから、婚姻制度を生殖と結びつけて同性婚を否定する見解に正当性は認められない。
同性婚を認めないことは、婚姻に係る当事者の自由と個人の尊厳の保障を害するものであり、憲法 24条1項に違反する。
3 憲法13条違反
憲法 13条は、個人の尊厳を基礎にした幸福追求権を保障するものであるところ、婚姻が人にとって重要かつ根源的な営みであり、尊重されるべきものであることに鑑みると、幸福追求権としての婚姻について法的な保護を受ける権利は、個人の人格的な生存に欠かすことのできない権利である。
ここに、婚姻の成立及び維持のためには、他者からの介入を受けない自由が認められるだけでは足りず、婚姻が社会から法的な地位を認められ、婚姻に対して法的な保護が与えられることが不可欠である。したがって、憲法13条は、婚姻をするかどうかについての個人の自由を保障するだけにとどまらず、婚姻の成立及び維持について法制度による保護を受ける権利をも認めているというべきである。
同性カップルを婚姻制度から一律に排除する現行の婚姻制度は、かかる幸福追求権を侵害するものであり、憲法13条に違反する。
4 婚姻以外の制度では違憲性を解消できないこと
以上に述べたような憲法違反の状態を解消するための施策として、諸外国で見られる、婚姻とは別の制度を設けることも理屈上の選択肢としては考えられる。
しかしながら、婚姻によって、婚姻当事者はさまざまな権利利益を享受するものであるところ、婚姻制度とは別の制度を設ける際に、同様の権利が等しく享受されることの保証はない。さらに致命的な問題は、婚姻とは異なる制度を設けることによって、同性カップルに対する差別を固定化する恐れがあることである。婚姻と同等の価値を持たない制度では、当事者を「本来の婚姻の外側」に置くという社会的メッセージを生む。この点について、「結婚の自由をすべての人に」訴訟の大阪高裁判決は、「同性カップルについてのみ婚姻とは別の制度を設けることは、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑みると、新たな差別を生み出すとの危惧が拭えない。」と正しく指摘する。
同性カップルの関係性を保護、公証するために婚姻とは異なる制度を設けたとしても、これによって違憲性を解消することができないばかりか、新たな差別を生み出すおそれすらある。現行の婚姻制度を前提として違憲性を解消するためには、婚姻制度を同性カップルにも等しく適用するほかない。
第3 国内の動き
1 自治体の取り組み
2015年に東京都渋谷区・世田谷区で、自治体によるパートナーシップ制度が開始されて以降、同制度は全国的に拡大した。2025年6月末時点の導入自治体数は538に上り、導入自治体の人口カバー率は92.8%に達する。
さらに、近年では、同性カップルに限らず事実婚カップルや複数の家族形態を対象とする制度を導入する自治体や、当事者間のパートナーシップだけではなく子どもも含めて「家族」として扱う制度を設ける自治体も現れている。また、転居によって自治体ごとに再度手続きを行わなければならない不便を解消するため、複数自治体間での証明書相互利用や情報共有を可能とする「自治体間連携」の動きも進んでいる。
また、自治体職員に対する福利厚生でも、配偶者相当としての取扱いや慶弔・休暇・住居手当等の適用拡大の動きがみられる。ただし、自治体独自の対応となるため、自治体間で差が生じており、関係性の保護が約束されているわけではない。
その他に、地方自治体が、同性婚の法制化や婚姻の平等に関する国への意見書を採択する動きも見られる。例えば、2023年6月27日には福岡市議会が「同性婚の法制化の議論を求める意見書」を可決し、国会・政府に対し審議促進を要請した。2024年3月27日には大阪市議会が「同性婚や事実婚を認める新たな法制度の確立に向けた議論の促進を求める意見書」を可決し、パートナーシップ・ファミリーシップ制度では解消できない不利益に言及して国の制度整備を強く求めている。また、差別禁止やアウティング禁止を明文化した条例を制定する自治体もある。
これらの地方自治体の取り組みは、同性カップルの困難を少しでも解消しようとするとともに、国に対して婚姻の平等実現の必要性を訴えるものとして評価される。
2 企業の取り組み
金融、保険、不動産、通信、ブライダル等の民間サービスにおいて、契約上、同性のパートナーを配偶者(家族)として扱う例が増えている。 また、企業内では、家族手当・慶弔・看護・介護・異動の配慮・社宅・単身赴任手当等について、法律上同性のパートナーを配偶者として扱う会社も現れている。
企業による婚姻平等支持の可視化を目的とする「Business for Marriage Equality」には、製造・IT・金融・不動産・観光・メディアなど幅広い業種が参加し、2025年9月22日現在、664の企業・団体が婚姻の平等への賛同を表明している。
経済団体や外国商工会議所も、婚姻の平等の必要性を発信している。企業や経済界も、婚姻の平等の実現を求めている状況にある。
第4 国際社会の動き
1 婚姻の平等の広がり
世界では、同性カップルの法的保護の動きが拡大している。2025年1月23日現在、婚姻の平等が法的に認められている国・地域は 39に上る。2025年1月1日にリヒテンシュタインが、同年1月22日にタイが施行していることから見てとれるように、婚姻の平等の取り組みは、欧米の大国だけに留まるものではない。
タイにおける婚姻の平等の実現は、東南アジアでは初めてであり、アジア全体では台湾(2019年)、ネパール(2023年)に続く三例目となる。
2 国際機関からの勧告
市民的及び政治的権利に関する国際規約(ICCPR)を監督する国連・自由権規約委員会は、2022年の日本に対する総括所見(第7回)において、同性カップルが「公営住宅へのアクセス及び同性婚を含む、本規約にうたわれた全ての権利」を日本国内で享受できるようにすることを勧告した。これは、抽象的な差別禁止の一般論にとどまるものではなく、婚姻へのアクセスそのものを含めた具体的権利の保障を求める内容である。
女性差別撤廃委員会(CEDAW)は、2024年の日本に関する総括所見で、「同性婚および事実婚の法的承認の欠如」や「同性カップルによる養子縁組の禁止」を懸念事項として明記し、家族法分野での平等実現に向けた法整備を勧告した。夫婦の氏の選択や女性の資産管理等と並んで、同性カップルの家族形成の権利を条約実施の文脈で位置付けている点に留意すべきである。
さらに、普遍的定期的審査(UPR)でも、カナダをはじめ複数国が日本に対し、SOGI(性的指向・性自認)に基づく差別撤廃、同性パートナーシップの国家レベルでの承認、同性婚の容認を勧告した。
これらの国際的メッセージは、国内の裁判例の蓄積とも相まって、立法的解決の必要性を一層明らかにするものである。
第5 結語
本提案理由が示すとおり、同性カップルを婚姻制度から排除する現行法は、憲法13条、14条及び24条1項に違反するものであり、近時、現行制度を違憲とする判決が積み重ねられている。これらの判決のうち、名古屋高裁判決は、婚姻の平等を実現するに当たっては、婚姻の効力や親子関係に関する諸規定を性別中立的な文言に変更するといった法改正で足り、膨大な立法作業を必要としないことまでも説示している。
国内では自治体のパートナーシップ・ファミリーシップ制度、地方議会の意見書や決議の採択、企業・経済界の制度整備が進展しており、国外でも婚姻の平等は着実に拡大し、国際機関はわが国に対して婚姻の平等の実現を勧告している。そうであるにもかかわらず、政府は、違憲判決が積み重ねられても「注視」の態度を崩さず、違憲状態の是正を先送りしている。このような政府の対応によって、同性カップルは重大な権利利益の侵害等の不利益を被り続けている。
よって、当連合会は、国に対し、わが国における複数の違憲判決や、国内外の婚姻の平等を求める動きを踏まえて、同性カップルによる婚姻を可能とする民法等の法改正、すなわち婚姻の平等を実現することを速やかに行うことを強く求めるものである。
以上