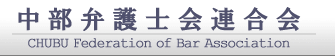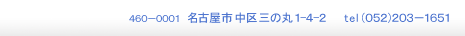第1 「人間の尊厳」の基盤となる生存権(憲法25条)
日本国憲法25条1項は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を有すると定め、同条2項は、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と定める。
国家による「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」の保障は、「個人の尊厳」(憲法13条)、ひいては「人間の尊厳」の基盤となる極めて重要な権利保障である。
第2 侵害される生存権
1 政策による政治的生存権侵害
近時、生存権は政策により侵害され続け、深刻な危機に瀕している。
すなわち、政府は、生活保護につき、2004年から老齢加算を削減・廃止し、2013年からは史上最大規模(平均6.5%、最大10%、削減額670億円)で生活扶助基準を引き下げ、2015年からは住宅扶助基準(削減額190億円)と冬季加算(削減額30億円)を引き下げ、2018年からは生活扶助基準(平均1.8%、最大5%)と母子加算・児童養育加算等(削減額160億円)を引き下げた。高齢単身世帯(75歳)においては、2004年の生活扶助費と比較すると実に24.5%減となっている。
このような相次ぐ引き下げにより、生活保護利用者は、「風呂は週1回」、「真冬でも暖房をつけない」、「食事は1日2食が限界」、「洗剤は使わない」、「香典等も払えず人間関係が断たれる」、「孫のための1日100円の貯金もできなくなった」などというもはや「健康で文化的」な生活とは到底いえない状態にまで追い込まれてしまっている。
政策により政治的に生存権が侵害されていると評価するほかない。
2 個別の行政作用等による生存権侵害
政策による政治的生存権侵害だけでなく、個別の行政作用等による生存権侵害も後を絶たない。
当連合会の会員が関わる近時の代表的な例だけでも、①生活保護の利用要件が整っているにもかかわらず申請を拒絶されるいわゆる水際作戦により車上生活者が死亡した事例(富山県)、②福祉事務所が精神障害者手帳の取得用及び更新用の診断書料を病院に支払う一方で同手帳について調査せず2年8か月にわたり障害者加算の支給を違法に怠った事例(愛知県)、③自動車の運転記録を提出しなかったことを理由に違法に生活保護を停止した事例及び自動車の見積書を提出しなかったことを理由に違法に生活保護を停止した事例(三重県)などがある。また、群馬県桐生市における生活保護費の違法な分割支給等が社会問題化するなどしており、さらに、生活保護利用者に対する差別・偏見による利用控えなど社会的な生存権侵害も頻発している。
このように、政策による政治的な侵害だけでなく、個別の行政作用等により生存権が侵害される例も後を絶たない。
第3 憲法が求める「司法の本質的役割」、「弁護士の本質的役割」
憲法が求める「司法の本質的役割」は、「国会や政府といった政治部門(立法・行政(内閣))が多数決原理によって国民の意思を国政に反映させようとするのと異なり、個別事件における法適用を通じて、少数者の権利保護を含む法の支配、法による正義を実現すること」とされている。
弁護士は、司法の一翼を担い、法曹三者の中で唯一、統治機構の外にいる。その弁護士が、市民とともに政治部門を監視し、少数者の権利が侵害されれば、その救済を図るため、裁判所に司法権発動を促すこと。これこそ憲法が求める「弁護士の本質的役割」である。特に、生存権は、人間の尊厳の基盤となる保護の必要性が極めて高い極めて重要な権利である一方、多数決原理が強く作用する政治部門等に侵害されやすい脆弱な権利でもある。
したがって、生存権保障を十全にし、人間の尊厳を確保するためには、特に、政治部門から独立した司法・弁護士が果たすべき役割が極めて重要となる。そして、弁護士がその本質的役割を十全に果たすためには、本質的役割を果たした弁護士に対する正当な対価の支払いが必要不可欠である。
第4 生存権の具体化のため司法・弁護士が果たしてきた役割
生存権の具体化において、司法、弁護士が果たしてきた役割は大きい。 すなわち、最高裁判所は、憲法制定直後、食管法事件において、憲法25条に法的効力はなく、単に政治的な指針であるとするプログラム規定説を採用した(最大判昭和23年9月29日)。
しかし、その後、東京地方裁判所は、朝日訴訟において、「健康で文化的な最低限度の生活」とは、「人間に値する生存」を可能ならしめるような程度のものでなければならない」とし、厚生大臣による生活保護基準設定行為は羈束行為であり憲法25条違反にもなりうるとした上、生活保護基準を違法と判断した(東京地判昭和35年10月19日)。この判決は控訴審で取り消されたものの、最高裁判所は、傍論ではあるが、生活保護基準設定についても厚生大臣の裁量の逸脱・濫用が認められる場合には違法となる旨判示し、憲法25条に法的規範性を与えた(最大判昭和42年5月24日)。そして、最高裁判所は、老齢加算廃止訴訟において、判断過程審査の手法を採用し、厚生労働大臣の裁量に一定の歯止めをかけるに至った(最三小判平成24年2月28日)。
そのような中、名古屋高等裁判所は、2013年から2015年にかけて行われた最大10%、平均6.5%の生活扶助基準引下げを巡って争われている「いのちのとりで裁判」(生活保護基準引下げ違憲訴訟)において、「健康で文化的な最低限度の生活」について、「人が3度の食事ができているだけでは、…生命が維持できているというにすぎず、到底健康で文化的な最低限度の生活であるといえないし、健康であるためには、基本的な栄養バランスのとれるような食事を行うことが可能であることが必要であり、文化的といえるためには、孤立せずに親族間や地域において対人関係を持ったり、…(中略)…自分なりに何らかの楽しみとなることを行うことなどが可能であることが必要」としてその内実を具体的にした上で、生活扶助基準設定につき厚生労働大臣の裁量の逸脱・濫用を認め違法とし、さらに、国家賠償法上の違法性まで認めて国家賠償を命じる画期的判決を言い渡した(名古屋高判令和5年11月30日)。
このように、生存権の内実は、長年にわたり積み重ねられた多くの裁判により具体化され着実に前進してきた。
それらの裁判には、司法の一翼を担う多くの弁護士が、代理人として生活保護利用者に寄り添い、訴え提起し、効果的な主張立証を行って司法権発動を促すなどの「不断の努力」(憲法12条)をしてその本質的役割を果たしてきた。
第5 「司法・弁護士の本質的役割」を果たした近時の事例と課題
1 「いのちのとりで裁判」最高裁判決
「いのちのとりで裁判」では、直前の総選挙で政権与党に復帰した政党の選挙公約「生活保護給付水準10%引下げ」に沿う形で、史上初めて基準部会等の専門家による審議検討を経ず厚生労働大臣が独断で生活扶助基準を最大10%、平均6.5%という前代未聞の大幅な率で引下げた事案が争われており、まさに、司法・弁護士の本質的役割が正面から問われる裁判であった。
この裁判において、最高裁判所は、愛知訴訟及び大阪訴訟につき、2025年6月27日、老齢加算廃止訴訟の判断枠組みを踏襲し、裁判官全員一致の意見で「厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり、生活保護法3条、8条2項に違反して違法」とする歴史的な原告側勝訴判決を言い渡した(最三小判令和7年6月27日)。
約1000人の原告とともに闘った約300人の弁護士が果たした役割は大きく、特に、当該最高裁判決及び名古屋高等裁判所判決を筆頭に、当連合会管内の司法・弁護士が果たした役割は極めて大きい。
まさに、憲法が求める「司法・弁護士の本質的役割」が十全に果たされた事例であると評価できる。
しかし、厚生労働大臣は、謝罪すらせず、被害救済も未だ進んでいない。また、政治部門による恣意的な生存権侵害の再発を防止するため、立法を含めた問題の抜本的解決が求められるなど残された課題は山積している。
2 個別の行政作用等による生存権侵害への対応等
個別の行政作用等による生存権侵害に対しても、いわゆる水際作戦等に対抗するため、当連合会管内の多くの弁護士が、生活保護申請に同行するなどしている。また、第2・2②、③の各事例では、当連合会管内の弁護士が代理人として訴訟提起し、いずれも勝訴判決が確定し、生存権侵害による被害が救済された。
このように、個別の行政作用等による生存権侵害に対しても、司法・弁護士の本質的役割が果たされている。
しかし、その背後には、救済されないままとなっている生存権侵害が数多く潜んでいることは想像に難くなく、また、生活保護利用者に対する差別・偏見等の社会的侵害の素地は今なお根深く残り続けている。
この点、日本弁護士連合会は、これまで述べてきた諸課題を解決すべく、2024年10月4日、第66回人権擁護大会において、現行生活保護法を抜本改正し、「生活保障法」の制定を求める旨決議している。
3 立法裁量の統制に関する課題
さらに、前記のとおり、厚生労働大臣による生活扶助基準の改定については、判断過程審査の手法により、行政裁量を統制することはできている一方、立法裁量については、依然として、堀木訴訟最大判(最大判昭和57年7月7日)のような広い立法裁量が認められている。立法裁量を統制するための新たな理論的根拠を確立することも課題として残されている。
第6 結語
当連合会は、「司法の本質的役割」、「弁護士の本質的役割」を今一度確認し、司法・弁護士がそれを十全に果たせるよう努めるとともに、政治部門による恣意的な生存権侵害を防止し、人間の尊厳の基盤となる生存権を守り抜くため、次のとおり宣言する。
1 私たち弁護士は、それぞれ、今一度、「司法の本質的役割」、「弁護士の本質的役割」を意識し、個別事件における法適用を通じて、少数者の権利保護を含む法の支配、法による正義を実現するよう努める
2 当連合会は、弁護士がその本質的役割を十全に果たせるよう民事法律扶助の対象事件の拡大や弁護士報酬の改善等に取り組む
3 当連合会は、「いのちのとりで裁判」最高裁判決を支持し、その趣旨を踏まえ、厚生労働大臣に対し、すべての生活保護利用者に謝罪した上、被害救済に全力を尽くすよう求める
4 当連合会は、国に対し、日本弁護士連合会が2024年10月4日人権擁護大会において制定を求める旨決議した「生活保障法」の制定を求める
以 上
2025年(令和7年)10月17日
中部弁護士会連合会
提 案 理 由
第1 「人間の尊厳」、「個人の尊厳」(憲法13条)の基盤となる憲法25条「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」
1 憲法25条1項は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を有すると定める。これは、国民が誰でも、人間的な生活を送ることができることを権利として宣言したものである(芦部信喜[著]=高橋和之[補訂]『憲法〔第8版〕』(岩波書店、2023年)291頁)。 そして、この趣旨を実現するため、同条2項は、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と定め、国に対し、生存権を具体化する努力義務を課している。これを受け、国は、生活保護法を立法するなどしている。
2 また、憲法13条前段は、「すべて国民は、個人として尊重される」と定める。この「個人の尊重」は、一般に、「人間の尊厳」(ドイツ基本法1条1項)と同趣旨であるとされる(長谷部恭男[編]『注釈日本国憲法(2)』(有斐閣、2017年)74頁〔土井真一執筆部分〕、宮沢俊義『憲法Ⅱ〔新版〕』(有斐閣、1974年)213頁以下、芦部信喜『憲法学Ⅱ』(有斐閣、1994年)57頁以下。以下、特に断りがない限り「人間の尊厳」という。)。
憲法13条にいう「個人の尊重」の原理は、我が国の基本的価値であり、全法秩序の基本的指針となる根本原理とされ、憲法の中にあって最も重要な条文とされている(前掲・長谷部『注釈日本国憲法(2)』64~65頁)。
3 そして、国家が、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を侵害することは、国民に対し、人間的な生活とはいえない、健康でない生活や文化的でない生活を強いることにほかならない。健康であること、文化的であることは、個人・人間が尊厳を保ち人間的な生活を送るために必須の要素であることは明らかであり、これらが欠けた状態の生活を強いることは、「人間の尊厳」を侵害することに他ならない。 憲法25条は、「人間の尊厳」の土台・基盤を築く極めて重要な権利なのである。
4 この点は、憲法25条の制定過程を見ても明らかである。
帝国議会衆議院に設置された「帝国憲法改正案委員小委員会」においても、マッカーサー草案には盛り込まれなかった憲法25条1項の規定をワイマール憲法にならって盛り込むにあたり、「人が個人的な尊厳ある人格として承認されるということを裏付けるには、やはり生存権を有することによってこれが具体的に行われるのではないか。それと表裏してこれが明記されなければならんと思います。」などと議論されている。立法者も、「人間の尊厳」の土台・基盤として憲法25条を制定しているのである(第90回帝国議会衆議院憲法改正案委員小委員会速記録 第4~6回)。
5 さらに、ワイマール憲法を生んだドイツにおいても、生存権は、「人間の尊厳」に直結する極めて重要な権利であると考えられている。
すなわち、ドイツにおける憲法関係の最高裁判所にあたる連邦憲法裁判所のメッスリング判事は、2024年6月24日、日本弁護士連合会ドイツ調査団に対し、次のとおり述べた。
「ドイツ基本法1条1項は、「人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し保護することは、すべての国家権力の義務である」と規定する。…(中略)…人間の尊厳は憲法上「至高の価値」とされる。その保障は基本法79条3項の「永遠条項」に含まれ、多数決によっても縮小されることのない「絶対に不可侵」なものである。この人間の尊厳の保障を基本法20条1項の福祉国家の原則と連動させることで生存最低限度の保障の給付請求権があることを認めた。保障の内容としては、身体的存在の保障だけでなく、人は必然的に社会的関係の中で生きていることから、人間関係を維持することや、社会的文化的政治的生活への最低限の参加を含むものとした」(日本弁護士連合会第66回人権擁護大会シンポジウム第1分科会基調報告書404頁~)。
ワイマール憲法と異なり、現在のドイツ基本法には、日本の憲法25条に相当する明文はない。しかし、ドイツ司法は、「人間の尊厳は不可侵」とする条文と福祉国家の原則を定める総則的条文から、解釈により、抽象的権利を超えて、生存最低限度の保障の給付請求権という具体的権利まで導いた上、その給付の内容は、社会的文化的政治的生活への最低限の参加を含むと明言しているのである。
まさに、生存権は、「人間の尊厳」の土台・基盤となる極めて重要な権利であり、これを侵害することは「人間の尊厳」を侵害することにほかならないと考えているのである。そして、社会的文化的政治的生活への最低限の参加まで可能となるような給付を行わなければ、生存権侵害にあたり、「人間の尊厳」も侵害されると考えているのである。
日本においても、この理は全く変わらないはずである。
6 以上のとおり、国家による「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」の保障は、「個人の尊厳」(憲法13条)、ひいては「人間の尊厳」 の土台・基盤となる極めて重要な権利保障である。
第2 侵害される生存権
1 政策による政治的生存権侵害
近時、生存権は政策により侵害され続け、深刻な危機に瀕している。 すなわち、政府は、2004年から老齢加算を削減・廃止し、2013年からは史上最大規模(平均6.5%、最大10%、削減額670億円)で生活扶助基準を引き下げ、2015年からは住宅扶助基準(削減額190億円)と冬季加算(削減額30億円)を引き下げ、2018年からは生活扶助(平均1.8%、最大5%)と母子加算・児童養育加算等(削減額160億円)を引き下げた。これにより、高齢単身世帯(75歳・1級地1、各種加算あり)の生活扶助費は、2004年の老齢加算廃止直前と比べて、実に約25%減となっている。
(1)老齢加算の廃止(2004年~)
老齢加算は、1960年の創設以来、40年以上にわたり加齢に伴う心身の変化により生じる特別の需要を満たすために支給され続けていた。
この老齢加算は2004年度から段階的に廃止され、2006年度には完全に廃止されるに至った。全日本民主医療機関連合会が行った老齢加算廃止後の生活保護利用者401人を対象に実施した生活実態調査報告によれば、1日の食事回数が「2回以下」が24%であり、中には「おかずがいらないパンやうどんで済ます」、「食事は朝昼兼用。残りを夕食に」、「おかずはたくあんだけ」、「朝は水で腹をふくらませる」、「月末は1日1食」という人もいる状況が明らかとなった。単身世帯のうち1か月の交通費0円が42.6%、教養娯楽費0円が62.6%、交際費0円が35.7%にものぼり、70歳以上の多くの生活保護利用者が、親族の葬儀にすら参列できなかったり、地域の付き合いも絶たなければならなくなるような状況に追い込まれたことが明らかとなっている。
(2)生活扶助基準の引下げ(2013年~)、期末一時扶助の引下げ(2013 年)
生活保護基準の中でも衣食その他の日常生活に充てる費用の基準として核心的に重要な生活扶助基準については、1950年の現行生活保護法制定以来、引き下げられたのは2003年と2004年の2回だけであり、その率もそれぞれ0.9%と0.2%という1%未満の率であった。 しかし、直前の総選挙で政権与党に復帰した政党の選挙公約「生活保護給付水準10%引下げ」に沿う形で、突然、2013年から2015年にかけて、3段階に分けて、最大10%、平均6.5%という前代未聞の大幅な率で生活扶助基準の引下げが断行された(削減額670億円)。さらに、2013年には、年越し費用の一部である期末一時扶助も年間70億円分も削減された。 この引き下げによる影響の把握を目的としてなされた山田壮志郎日本福祉大学准教授による生活保護利用者へのアンケート調査(604名が回答)の回答では、次のとおり、まさに健康で文化的な最低限度の生活を下回る生活を強いられている生活保護利用者の悲痛な声が多数見られた。
【食事関係】
「毎日漬け物ばかり食べている」、「肉はほとんど食べられない」、「米を節約するため、おかゆを食べるようになった」、「野菜、くだもの、乳製品が買えなくなり、レトルトばかり」、「食事は3回から2回にしている」
【住居関係】
「なるべく家にいないようにするため、昼間は図書館で過ごしている」、「風呂に毎日入りたいが入れない。できれば湯船につかりたいがシャワーのみ」、「故障した電化製品の修理をできなくなった」
【衣類関係】
「服が買えない」、「下着を購入するのがやっと」、「散髪は1年間全くいかなかった」、「美容院にも行けない」、「眼鏡も買えない」
【趣味・人付き合い関係】
「お寺に両親を納骨していて、年4回ほど寺から案内がありますが、お布施もできないようになった」、「葬式に行きたかったが行けなかった」、「新聞(日刊紙)を止めざるを得なかった」
【子育て関係】
「孫の部活のユニフォーム代がなく先輩にもらった」、「上の子のランドセル代をどうやって工面すればいいのかわからない」、「小学校の遠足、宿泊学習などの参加費の立て替えができずに参加させてあげられない」、「保育園での遠足や卒園児の発表会に必要な衣服が購入できないため、子どもにとって一生に一度の晴れ舞台に立たせてあげられない。情けない気持ちでいっぱい」
(3) 住宅扶助基準の引下げ(2015年)、冬季加算引下げ(2015年)
2015年7月には、住宅扶助基準の引下げにより、年間190億円分も削減された。その結果、福祉事務所から住宅扶助基準内の住居に移るよう指導を受け、住み慣れた住居で安心して生活することすら脅かされる状況となった者も発生している。
同年11月には、暖房費用等冬季特有の支出に対応するために支給される冬季加算も年間30億円分も削減された。地域によっては、20%もの削減がなされたところもあり、冬に十分な暖を取ることすらできない状況に追い込まれている。
(4) 生活扶助基準の引下げ(2018年~)、母子加算・児童養育加算の引下げ(2018年)
さらに、2018年から2020年にかけて、3段階に分けて、前記2013年からの引下げに次ぐ戦後2番目の引下げ幅となる最大5%、平均1.8%の率で生活扶助基準の引下げが行われた。それだけでなく、ひとり親世帯における子育て費用として支給される母子加算及び中学生以下の児童の子育て費用として支給される児童養育加算も年間160億円分も削減された。
(5) 昨今の物価高に適切に対応しないことによる実質引下げ
2020年を基準(100)とする消費者物価総合指数は、2022年平均が102.3、2023年平均が105.6、2024年平均が108.5となっており、ここ数年、物価が急騰している状況にある。
このような世界的な物価高の中、ドイツ、韓国、スウェーデン等の諸外国では、物価高に適切に対応し、生活保護基準を大幅に引き上げている。
ところが、日本では、物価高に適切に対応しておらず、生活保護基準は実質的に引き下げられている状況となっている。
(6) 小括
このように、日本の生活保護基準は、相次ぐ引下げによりもはや「健康で文化的な最低限度の生活」を営める水準とは到底評価できない状態となっている。生存権は、政策により侵害され続けており、深刻な危機に瀕している。
2 個々の行政作用等による生存権侵害
政策による政治的生存権侵害だけでなく、個別の行政作用等による生存権侵害も後を絶たない。
当連合会管内の会員が関わる近時の代表的な例だけでも、次のような例が挙げられる。
(1) 生活保護の申請要件が整っているにもかかわらず申請を拒絶されるいわゆる水際作戦により車上生活者が死亡した事例(富山県)(北日本新聞2018年4月2日付け記事等)。
富山県の当連合会会員は、数年間、軽自動車で生活し、所持金がなく1週間ほど食事を取ることができず自力歩行も困難な状態となって救急搬送された高齢男性を福祉関係者とともに支援した。同会員は、生活保護申請を行い、医療機関を受診させるなどの懸命の支援を行ったが、高齢男性は、支援の甲斐無く、死亡した。高齢男性は、同会員に対し、これまで何度も市役所に生活保護申請に行ったが、「住居がないと生活保護の申請はできない」などと言われ、申請を受け付けてくれなかったと述べ怒りをぶつけていた。高齢男性は預貯金等の資産をほとんど有しておらず、生活保護基準を下回る年金収入しかなかったことなどからすると、明らかに生活保護の申請要件が整っている状況であった。この高齢男性は、いわゆる水際作戦の犠牲になったものと言わざるを得ない。
(2) 生活保護申請権の侵害が疑われる事例(岐阜県)(岐阜新聞2024年2月19日付け記事等) 2021年度の岐阜市の生活保護申請率(相談に対する申請の比率)が全国平均を大きく下回る19.5%にとどまっており、県の監査で「申請権を侵害している可能性がある」ことが指摘されたことが岐阜新聞の連載記事で報じられた。この点につき、一定の改善策が講じられた後も、ⅰ弁護士等の支援者が同行しないと相談扱いにされ、申請させてもらえない、ⅱ住宅扶助額内の住まいに転居してから申請するよう言われた、ⅲ自動車保有が生活保護利用の妨げになっているなどの課題が前記連載記事の中で報じられ続けている。
(3) 障がい加算違法不支給事例(愛知県)(名古屋高判令和7年1月24日裁判所ウェブサイト、賃金と社会保障1875号55頁・被告は上告せず確定)
統合失調症を患っていた男性が精神病院に措置入院したことを契機に生活保護が開始されたケースで、福祉事務所は、男性の統合失調症についてはもちろん、退院後のグループホーム入居、通院継続(自立支援医療制度利用)、就労継続支援B型作業所通所等の経過を把握していた。保護開始から約半年後に男性が障害等級2級の精神障害者手帳を取得。福祉事務所は、上記病院からの請求により同手帳の「取得用」診断書料の一時扶助認定、その2年後に同手帳の「更新用」診断書料の一時扶助認定をしながら、本人や保健所等には手帳の有無や等級確認を一切することなく違法に障害者加算の支給を怠り、本人は、2年8か月にわたり本来の最低生活費を約20%も下回る生活を強いられた。
(4) 自動車の運転記録を提出しなかったことを理由に違法に生活保護を停止した事例及び自動車の見積書を提出しなかったことを理由に違法に生活保護を停止した事例(三重県)(津地裁令和6年3月21日裁判所ウェブサイト、賃金と社会保障1853号59頁、津地判令和6年9月26日裁判所ウェブサイト、賃金と社会保障1871号31頁、消費者法ニュース143号141頁、名古屋高判令和7年6月26日、名古屋高判令和7年10月30日)
① 生活保護利用中の身体障害を有する親子に対して、三重県内の社会福祉事務所が自動車の運転記録票を提出するよう指導指示を行ったが、提出しなかったことを理由に違法に生活保護停止処分をした。
② 生活保護利用中の身体障害を有する単身高齢女性が、保護申請時に自動車の見積書(無価値である上に引取費用が掛かる)を提出済みであるのに、三重県内の社会福祉事務所が異なる見積書2社以上を提出するよう指導指示を行い、提出しなかったことを理由に違法に生活保護停止処分をした。
(5) 預貯金の累積を理由とした違法生活保護廃止事例(石川県)(石川県2014年7月28日裁決、同2015年2月10日裁決賃金と社会保障1634号38頁)
預貯金が累積した生活保護利用者につき、預貯金の原資や累積状況等を調査することなく、生活保護利用者に辞退届を提出させた上、その月の一日に遡って違法に生活保護廃止処分を行うなどした。
(6) 支援団体から生活保護申請権の侵害である旨繰り返し指摘されな がら申請を拒絶し続けた事例(福井県)(生活保護問題全国会議、生活保護支援ネットワーク静岡2009年2月2日付け貴県・貴市の生活保護行政に関する要望書)
体調不良により仕事ができず所属していた派遣会社の寮から退去することを余儀なくされるなどした困窮者が生活保護を申請したところ、「住所がないから申請できない」などと違法な教示を受けた。その後、支援団体から上記の教示は違法な教示であり申請を受け付けるように警告されたにもかかわらず、その後も同様の教示を繰り返し生活保護申請を受け付けなかった。
3 社会的な生存権侵害
さらに、日本の生活保護の「捕捉率」(貧困とされる人のうちどの程度を生活保護で捕捉しているかを示す割合)は2割程度とされており(2018年11月公表・国民生活基礎調査に基づく推計(厚生労働省)等)、諸外国と比較してその低さが際立っている(生活保護問題対策全国会議「生活保護法から生活保障法へ」)。その背景には、生存権が「人間の尊厳」の基盤となる極めて重要な権利であるとの社会的コンセンサスの欠如、生活保護利用者に対する差別・偏見等により、生活保護の申請要件を満たしているにもかかわらず、生活保護を忌避し申請しない状態に追いやられるなどの社会的な生存権侵害が存在していることは明らかである。
第3 憲法が求める「司法の本質的役割」、「弁護士の本質的役割」
1 憲法が求める司法の本質的役割については、行政部門である内閣法制局ですら、国会において、次のとおり答弁している。
「司法と申しますのは、国会や政府のようないわゆる政治部門が基本的には多数決原理によって主権者である国民の意思を国政に反映させようとするものとはやや趣を異にいたしまして、やはり個別の事件における法適用を通じて、少数者の権利保護などを含みます法の支配あるいは法による正義を実現するということに本質的な役割があると言われています」(第151回国会参議院憲法調査会第9号・内閣法制局第一部憲法資料調査室長答弁)。
議院内閣制のもと、政治部門は、多数決原理によって国民の意思を国政に反映させる統治機構であることに異論はないであろう。しかし、多数決原理には「法」による限界があり、限界を超えていないか監視し、限界を超えていれば是正する役割を与えられているのが司法なのである。内閣法制局が答弁する上記の「司法の本質的役割」に異論を挟む者はいないであろう。
政治部門が、「数の力」を背景に限界を超え、少数者の権利を侵害したとき、司法は、「法の支配」、「法による正義」を実現すべく、最高法規たる憲法(憲法98条1項)や条約・確立された国際法規(憲法98条2項)を含む「法」を根拠に少数者の権利を保護する役割を与えられているのである。これこそが、憲法が司法に託した本質的役割であるといえる。
2 そして、弁護士は、司法の一翼を担う存在として、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命」(弁護士法1条)とする。弁護士は、法曹三者の中で唯一、統治機構の外にいるが、司法という統治機構を十分に機能させるためには、統治機構の外にいる弁護士の存在が欠かせないことから、憲法は、唯一の民間職業として弁護士の存在を明記しているのである。すなわち、憲法は、弁護士が、市民とともに政治部門を監視し、基本的人権や少数者の権利が侵害されれば、その救済を図るため、裁判所に司法権発動を促すことを期待しているのである。 これこそ憲法が求める「弁護士の本質的役割」である。
3 特に、生存権は、人間の尊厳の基盤となる保護の必要性が極めて高い極めて重要な権利である一方、その保障の対象となる人は、社会的・政治的に弱い立場に置かれた人々であることから、多数決原理が強く作用する政治部門等に侵害されやすい脆弱な権利でもある。
したがって、生存権保障を十全にし、人間の尊厳を確保するためには、特に、政治部門から独立した司法・弁護士が果たすべき役割が極めて重要となる。
4 そして、弁護士自身の経済的基盤が揺らいでいては、弁護士は、その本質的役割を十全に果たすことができない。弁護士がその本質的役割を果たすべき局面は、その多くが国等の公権力を相手にすることから弁護士の主張立証の負担は極めて大きい一方、依頼者は生活困窮者等であり正当な弁護士費用を自ら工面することができないことが多い。したがって、依頼を受けるためには総合法律支援法に基づく民事法律扶助制度等の援助制度を利用せざるを得ないが、その報酬額は、弁護士の負担に見合った正当な対価とは到底いえないほど低廉である。また、民事法律扶助制度は、生活保護申請への同行や審査請求には利用できないなど活用できる範囲が限定的である。
したがって、弁護士がその本質的役割を十全に果たせるようにすべく、民事法律扶助の対象事件の拡大や弁護士報酬の改善等に取り組むことが必要不可欠である。
第4 生存権の具体化のため司法・弁護士が果たしてきた役割
1 前記のとおり、保護の必要性が極めて高い一方、脆弱な権利でもある生存権の具体化において、司法・弁護士が果たしてきた役割は大きい。
以下、その経過を概説する。
2 食管法事件(生存権の権利性の否定)
まず、最高裁判所は、憲法制定直後である昭和23年、食管法事件において、生存権につき、単に「国家の責務として宣言したもの」にすぎず政治的な指針であるとするプログラム規定説を採用し、憲法上の権利として保障されることを明確に否定した(最大判昭和23年9月29日刑集2巻10号1235頁)。
しかし、その後、弁護士がその本質的役割を果たし、裁判所がこれに応えてきた結果、生存権は、憲法上の権利として保障されるに至る。
3 生存権への権利性(法的規範性)の付与と朝日訴訟基準
すなわち、東京地方裁判所は、生活保護基準自体が「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する憲法25条1項に違反し違憲であるなどとして提起された朝日訴訟において、「健康で文化的な最低限度の生活」とは、「「人間に値する生存」あるいは「人間としての生活」といい得るものを可能ならしめるような程度のものでなければならない」、「それが人間としての生活の最低限度という一線を有する以上理論的には特定の国における特定の時点においては一応客観的に決定すべきものであり、またしうる」とした上で、厚生大臣による生活保護基準設定行為を羈束行為であり憲法25条違反にもなりうるとし、当時の生活保護基準につき、「健康で文化的な生活水準」を維持できる程度のものとは言い難いとして、生活保護基準それ自体を違法と判断する画期的な判決を下した(東京地判昭和35年10月19日行集11巻10号2921頁)。
その後、この判決は控訴審で取り消されたものの、最高裁判所は、判決前に原告が死亡し、生活保護費の請求は一身専属的なものであることを理由として訴訟終了宣言をしたが、「なお、念のため」とした傍論で、「何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、いちおう、厚生大臣の合目的的な裁量に委されており、その判断は、当不当の問題として政府の政治責任が問われることはあつても、直ちに違法の問題を生ずることはない」が、「ただ、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によつて与えられた裁量権の限界をこえた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となることをまぬかれない」という基準(朝日訴訟基準)を定立した(最大判昭和42年5月24日民集21巻5号1043頁)。生活保護基準設定についても厚生大臣の裁量の逸脱・濫用が認められる場合には違法となる旨判示し生存権に法的規範性を与えた点では前進と評価できるが、違法となる場合は極めて限定的であり、厚生大臣に極めて広範な裁量を認めるものであった。
4 堀木訴訟基準
こうした中、最高裁判所は、当時の児童扶養手当法4条3項3号の併給調整条項が憲法25条に適合するか否かが問題となった堀木訴訟において、「憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄であるといわなければならない」という基準(堀木訴訟基準)を定立した(最大判昭和57年7月7日民集36巻7号1235頁)。この基準は、「健康で文化的な最低限度の生活」を現実の立法として具体化するに当たっては、「国の財政事情を無視することができず、また、多方面にわたる複雑多様な、しかも高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とするものである」ことを理由としており、生活外的要素の考慮を正面から認めた。
堀木訴訟基準は、朝日訴訟のような傍論での判断ではなかったことから、これ以降、憲法25条違反の判断枠組みのリーディングケースとして、多くの判例で引用されることとなった。
5 老齢加算廃止訴訟基準
もっとも、老齢加算廃止訴訟において、最高裁判所は、こうした「広い裁量」を前提とする判断枠組みに歯止めをかけた(最三小判平成24年2月28日民集66巻3号1240頁等)。
この事件では、第一審判決(東京地判平成20年6月26日判タ1293号86頁)及び控訴審判決(東京高判平成22年5月27日判タ1348号110頁)は、朝日訴訟基準を採用していたものの、最高裁判所は、朝日訴訟基準を採用せず、「厚生労働大臣の判断に、最低限度の生活の具体化に係る判断の過程及び手続における過誤,欠落の有無等の観点からみて裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があると認められる場合」等に生活保護法3条、8条2項に違反するとして、判断過程審査の手法を採用した。さらに、同判決は、老齢であることに起因する特別な需要の存在という事実が認められない場合のほか、統計等の客観的な数値等との合理的関連性を欠く場合、専門的知見との整合性を欠く場合等にも違法となることを示唆した(老齢加算廃止訴訟基準)。
6 生存権の内実を具体化し、国家賠償まで認容し生存権保障を強化した名古屋高等裁判所判決
そのような中、名古屋高等裁判所は、2013年から2015年にかけて行われた最大10%、平均6.5%の生活扶助基準引下げを巡って争われている「いのちのとりで裁判」(生活保護基準引下げ違憲訴訟)において、老齢加算廃止訴訟基準を採用して厚生労働大臣による生活扶助基準引下げにつき裁量の逸脱・濫用を認め違法としただけでなく、「健康で文化的な最低限度の生活」について、「人が3度の食事ができているだけでは、…生命が維持できているというにすぎず、到底健康で文化的な最低限度の生活であるといえないし、健康であるためには、基本的な栄養バランスのとれるような食事を行うことが可能であることが必要であり、文化的といえるためには、孤立せずに親族間や地域において対人関係を持ったり、…(中略)…自分なりに何らかの楽しみとなることを行うことなどが可能であることが必要」としその内実を具体的にした上で、「生活扶助費の減額分だけ更に余裕のない生活を、…(中略)…少なくとも9年以上という長期間にわたり強いられてきたものと認められるから、いずれも相当の精神的苦痛を受けたものと推認するに難くなく、このような精神的苦痛は、金銭的、経済的な問題の解消によってその全てが解消される性質のものではなく、事後的に本件各処分が取り消されたとしても、その間の生活が取り戻せるものではないことにも鑑みれば、本件各処分が取り消されることにより慰謝される部分があるとしても、その全てが慰謝されるとは認め難いところである」などとして国家賠償法上の違法性まで認めて国家賠償を命じる画期的判決を言い渡した(名古屋高判令和5年11月30日裁判所ウェブサイト、賃金と社会保障1845号66頁、賃金と社会保障1846号56頁、賃金と社会保障1847号48頁、消費者法ニュース139号124頁)。
第5 「司法・弁護士の本質的役割」を果たした直近の事例と課題
1 「いのちのとりで裁判」最高裁判決
(1) 「いのちのとりで裁判」では、直前の総選挙で政権与党に復帰した政党の選挙公約「生活保護給付水準10%引下げ」に沿う形で、厚生労働大臣が史上初めて独断で生活扶助基準を最大10%、平均6.5%という前代未聞の大幅な率で引下げた事案が争われている。津地方裁判所は、この事案の背景につき、「厚生労働省においては、平成24年の衆議院議員総選挙で政権復帰が想定されていた自由民主党が発表していた生活保護費を10%削減するとの方針ないし選挙公約に忖度し、当時会合が重ねられていた基準部会における議論とは全く無関係に…(中略)…本件改定を公表した」と容易に推認されるとまで判示した(津地判令和6年2月22日裁判所ウェブサイト)。この事案に関するマスコミ報道も多くがこのような背景事情があったと報じている。まさに、「いのちのとりで裁判」は、「政治部門が多数決原理によって国民の意思を国政に反映させよう」としたことに対し、「少数者の権利保護」の観点から、「法の支配、法による正義を実現する」という司法・弁護士の本質的役割が正面から問われる裁判であった。
(2) この裁判において、最高裁判所は、2025年6月27日、裁判官全員一致の意見で、厚生労働大臣が行った生活扶助基準の改定には「専門的知見との整合性を欠くところがある」と断じた上、「厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり、生活保護法3条、8条2項に違反して違法」と判示し、史上初めて厚生労働大臣による生活保護基準設定行為自体を違法とする歴史的な原告側勝訴判決を言い渡した(最三小判令和7年6月27日裁判所ウェブサイト)。
この歴史的な最高裁勝訴判決の獲得にあたっては、約1000人の原告とともに闘った全国約300人の弁護士、そして全国の裁判所が果たした役割は大きい。全国29地裁に提起された31の訴訟では、控訴審判決、第一審判決合わせて原告側勝訴29、原告側敗訴16(2025年9月28日現在)となっている。
特に、前記最高裁判決は、大阪訴訟のほか、当連合会管内の愛知訴訟に関する判決である。さらに、前記のとおり生存権の内実を具体化し、数多くの原告側勝訴判決の中でも唯一国家賠償請求まで認容した前記名古屋高等裁判所判決(前掲・名古屋高判令和5年11月30日)、「政治への忖度」という背景事情まで事実認定し事案の本質に迫った上、原告側勝訴とした津地方裁判所判決(前掲・津地判令和6年2月22日)、引下げの主要な理由とされた「デフレ調整」につき全国初提出された中核的な経済統計学者意見書を踏まえ的確にその不合理さを判示し原告側勝訴とした富山地方裁判所判決(富山地判令和6年1月24日裁判所ウェブサイト、賃金と社会保障1855・1856号113頁)といった全国を牽引する極めて先進的な原告側勝訴判決が言い渡されており、これらの判決の獲得にあたっては、当連合会管内を中心とした多くの弁護士の10年以上に及ぶ並々ならぬ「不断の努力」(憲法12条)があった。当連合会管内の司法・弁護士が果たした役割は極めて大きい。
まさに、憲法が求める「司法・弁護士の本質的役割」が十全に果たされた事例であると評価できる。
(3) しかし、最高裁判所が厚生労働大臣の行為につき、生活保護法3条、8条2項に違反する違法行為であるとしたにもかかわらず、厚生労働大臣は、謝罪すらせず、司法判断を踏まえた被害救済も未だ進んでいない。また、政治部門による恣意的な生存権侵害の再発を防止するため、立法を含めた問題の抜本的解決が求められるなど残された課題は山積している。
2 個別の行政作用等による生存権侵害への対応
(1) 第2・2に記載したものに代表される個別の行政作用等による生存権侵害に対しても、当連合会管内の多くの裁判所・弁護士が、その本質的役割を果たしている。
(2) まず、違法な生活保護申請の拒絶、いわゆる水際作戦等に対抗するため、当連合会管内の多くの弁護士が、生活保護申請に同行するなどしている。その弁護士費用の多くは、日本弁護士連合会の高齢者・障がい者及びホームレス等に対する法律援助事業でまかなわれており、当連合会管内におけるその利用件数は、2023年度で75件となっている(法テラス白書令和5年度版147頁)。
(3) また、第2・2③の事例については、愛知県の当連合会会員が代理人となり手帳取得時から支給されるべきであった障害者加算分の支払いを求めて国家賠償請求訴訟を提起し、第一審は請求を棄却したものの、名古屋高等裁判所は男性の請求をすべて認めた上、障害者加算制度が保障しているのは被保護者の生存権であることを明言した(名古屋高判令和7年1月24日裁判所ウェブサイト、賃金と社会保障1875号55頁・被告は上告せず確定)。
(4) さらに、第2・2④(1)の事例では、三重県の当連合会会員が代理人となり停止処分の取消しと国家賠償請求訴訟を提起し、第一審は、停止処分は相当性を欠き違法であるとして取り消し、国家賠償請求もそれぞれ10万円認容した(津地判令和6年3月21日裁判所ウェブサイト、賃金と社会保障1853号59頁)。控訴審も国家賠償請求を減額したものの第一審の結論を維持した(名古屋高判令和6年10月30日裁判所ウェブサイト、賃金と社会保障1871号15頁、消費者法ニュース143号144頁・上告不受理で確定(最決令和7年5月12日))。
(5) 第2・2④(2)の事例では、三重県の当連合会会員が代理人となり停止処分の取消しと国家賠償請求訴訟を提起し、第一審は、被告が処分の根拠としていた課長通知を「局長通知との整合性を直ちに認め難い」と判示した上で、停止処分を違法であるとして取り消し、国家賠償請求を15万円認容した(津地判令和6年9月26日裁判所ウェブサイト、賃金と社会保障1871号31頁、消費者法ニュース143号141頁)。控訴審も国家賠償請求を減額したものの第一審の結論を維持した(名古屋高判令和7年6月26日・双方上告せず確定)。
(6) 第2・2⑤の事例では、石川県の当連合会会員が代理人となり審査請求を行うなどし、生活保護廃止処分取消しの裁決を得た上(石川県2014年7月28日裁決、同2015年2月10日裁決賃金と社会保障1634号38頁)、取り消された生活保護廃止期間の生活保護費全額を遡及支給させた。
(7) このように、個別の行政作用等による生存権侵害に対しても、司法・弁護士の本質的役割が果たされている。
しかし、司法・弁護士の本質的役割が果たされることにより救済される例は氷山の一角であり、その背後には、救済されないままとなっている生存権侵害が数多く潜んでいることは想像に難くない。また、生存権が「人間の尊厳」の基盤となる極めて重要な権利であるとの社会的コンセンサスの欠如、生活保護利用者に対する差別・偏見等の社会的侵害を含めた生存権侵害の素地は今なお根深く残り続けている。
3 社会的な生存権侵害への対応
社会的な生存権侵害は、生存権が「人間の尊厳」の基盤となる極めて重要な権利であるとの社会的コンセンサスの欠如、生活保護利用者に対する差別・偏見等により生み出されている。
「いのちのとりで裁判」における取り組み等のように、司法・弁護士がその本質的役割を十全に果たし、生存権が人間の尊厳の土台・基盤となる極めて重要な権利であることを示し続け、不断の努力を続けることこそが、社会の認識を変え、差別・偏見をなくすことにつながる。
その意味で、司法・弁護士が、「法の支配、法による正義」を社会にも及ぼすことが求められているというべきである。
4 諸課題を解決するため制定が求められる「生活保障法」
これまで述べてきた諸課題を解決するための主要な処方箋として、日本弁護士連合会は、生活保護法改正要綱案(改訂版)(生活保障法)を作成、公表しており、2024年10月4日、第66回人権擁護大会において、現行生活保護法を抜本改正し、「生活保障法」の制定を求める旨、決議している。
「生活保障法」は、①権利性の明確化、②いわゆる水際作戦を不可能にする制度的保障、③生活保護基準の決定に対する統計等の客観的数値との合理的関連性、専門的知見との整合性を前提とした民主的コントロール等を内容としており、これにより、上記の諸課題の多くは解決されるものと考えられる。
5 立法裁量の統制に関する課題
また、前記のとおり、厚生労働大臣による生活扶助基準の改定については、判断過程審査の手法により、行政裁量を統制することはできている一方、立法裁量については、年金減額訴訟最高裁判所判決(最二小判令和5年12月15日民集77巻9号2285頁)がそうであったように、依然として、広い立法裁量を認める堀木訴訟基準が適用されている。 しかし、行政裁量の統制を十全に行っても、立法裁量の統制を十全に行えないのであれば、結局、行政裁量に対する司法判断を立法的に覆すことを可能にすることとなる。これでは、「少数者の権利保護を含む法の支配、法による正義を実現する」という司法の本質的役割を十分に果たせない。「法の支配、法による正義」にいう「法」は、最高法規たる憲法(憲法98条1項)や条約・確立された国際法規(憲法98条2項)を当然に含み、行政府のみならず立法府をも拘束することは明らかであり、これを実現して初めて「法の支配、法による正義」が実現されるのである。したがって、今後、立法裁量の統制を十全に行うことが課題として残されているというべきである。このような観点からいえば、同判決の補足意見は、「立法の判断過程審査の具体的な内容自体、立法権と司法権との関係を踏まえた上で、その理論としての必要性、明確性、有用性等が成熟したものになっているとは考えられ」ないとして、堀木訴訟基準を擁護していることは問題である。 「いのちのとりで裁判」でいえば、立法府に対しては、最高裁判所が違法と判断したことを踏まえ、そのような違法行為の再発を防止するための立法的措置を講じることが期待されるし、名古屋高裁判決が示した生存権の具体的内実等の司法判断を踏まえ、その趣旨を立法に反映させることが期待される。この点、ドイツ連邦憲法裁判所は、2010年、政府が設定した生存最低限度の基準に対し、「デタラメな数値や感覚的に過ぎない数値」に基づく基準設定は許さないとして違憲判決を言い渡している(いわゆるハルツⅣ判決)。これを受け、ドイツ立法府は、司法判断を踏まえた「基準需要算出法」を制定するという立法的措置を講じていることが参考になる。「法の支配、法による正義」は、立法府にも当然、及ぶのである。
そして、司法判断の趣旨を没却するような立法は「法の支配」の観点から許されないことは言うまでもない。 以上のとおり、生存権保障は、「人間の尊厳」 の土台・基盤となる極めて重要な権利保障であり、その保障を十全にするためには、政治部門から独立した司法・弁護士が果たすべき役割が極めて重要となる。 「いのちのとりで裁判」や個別事例において司法・弁護士が果たした役割等を踏まえれば、当連合会管内の多くの裁判所・弁護士は、その本質的役割をしっかりと果たしていると評価できる。 かつてのプログラム規定説、朝日訴訟基準がそうであったように、私たち弁護士は、当事者や支援者、専門家らとともに訴訟を追行することで、不合理な先例を覆すよう「不断の努力」(憲法12条)を続けてきた。司法権を行使する主体である裁判官も、弁護士等の努力に応え、確実に生存権保障を前進させてきた。 しかし、未だに課題は山積していることからすれば、司法・弁護士がその本質的役割をさらに十全に果たしていくことが求められる。
また、憲法25条が保障する制度は、生活保護制度だけではないし、司法的統制を及ぼすべき政治部門の政策は、生活保護制度に限ったものでは全くない。今後、生存権を具体化するあらゆる制度その他少数者の権利を侵害する政治部門の政策に司法的統制を十分に及ぼすべく、「不断の努力」(憲法12条)を続けることが付随的審査制のもとにおいて求められる弁護士の役割なのである。 そこで、当連合会は、「司法の本質的役割」、「弁護士の本質的役割」を今一度確認し、司法・弁護士がそれを十全に果たせるよう努めるとともに、政治部門による恣意的な生存権侵害を防止し、個人の尊厳、ひいては人間の尊厳の基盤となる生存権を守り抜くため、次のとおり宣言する。 1 私たち弁護士は、それぞれ、今一度、「司法の本質的役割」、「弁護士の本質的役割」を意識し、個別事件における法適用を通じて、少数者の権利保護を含む法の支配、法による正義を実現するよう努める 2 当連合会は、弁護士がその本質的役割を十全に果たせるよう民事法律扶助の対象事件の拡大や弁護士報酬の改善等に取り組む 3 当連合会は、「いのちのとりで裁判」最高裁判決を支持し、その趣旨を踏まえ、厚生労働大臣に対し、すべての生活保護利用者に謝罪した上、被害救済に全力を尽くすよう求める 4 当連合会は、国に対し、日本弁護士連合会が2024年10月4日人権擁護大会において制定を求める旨決議した「生活保障法」の制定を求める 以 上
第6 結語