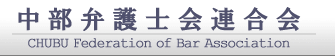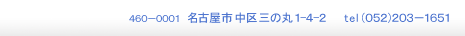1 はじめに
政府は、令和6年12月2日をもって、現行の健康保険証の新規発行をやめ、マイナンバーカードに健康保険証の機能を持たせた「マイナ保険証」へ移行することを閣議決定した。
マイナ保険証への一本化は、次のとおり、国民が、プライバシー等侵害に対する危険を踏まえて、マイナンバーカードを取得しない自由を奪われて、カードの取得を事実上強制する結果となる。
また、特に高齢者や障害者らについて現行制度より保険医療を受ける機会を奪ってしまうのではないかという懸念がある。
2 マイナンバーカード任意取得の原則(番号法第17条第1項)違反
いわゆる番号法は、マイナンバーカードの取得について申請主義を採用している(第17条第1項・任意取得の原則)。その趣旨は、情報漏えい等によるプライバシー等侵害の危険性とカードの利便性とを利益衡量して、国民一人一人がマイナンバーカードの所持について選択する自由を有することにある。
しかし、マイナ保険証への一本化は、わが国の国民皆保険制度の下では、全国民に対するマイナンバーカードの事実上の取得強制にほかならず、上記任意取得原則の趣旨に反する。
なお、健康保険証廃止後も、マイナンバーカードを取得していない者に対して資格確認書が発行される、是正措置が採られることになった。しかし、令和6年12月2日施行予定の健康保険法第51条の3では、誰にでも資格確認書を発行することは、「当分の間」の「経過措置」であるから、政府は、いつでも経過措置をとりやめて、資格確認書の発行を例外的な措置と位置づけることができる。結局、事実上のマイナンバーカードの取得強制であることに変わりはない。
3 プライバシーと情報漏えいに対する危惧
また、マイナ保険証(マイナンバーカード)には、健康保険証機能のみならず、令和5年4月から保険医療機関・薬局に義務化されたオンライン資格確認等システムの整備に伴い、当該被保険者(国民)の診療・薬剤情報、特定健診情報等も結合された。更に、国は、利便性を謳って、マイナンバーカードの多目的利用を押し進めようとしている。
こうして、マイナンバーカードに紐づけられる情報が増大し、マイナポータルで閲覧できる情報が増加すれば、マイナポータルがインターネット回線を通じて提供されるサービスであることから、情報漏えい等を完全に防ぐことは困難であり、マイナポータル利用者側のセキュリティ対策が脆弱な場合にはID、パスワードを窃取されたり、マイナンバーカードとパスワードを第三者が取得したりして、なりすましでマイナポータルにアクセスされたりして、医療情報に限られない極めて広範な個人情報が不正に閲覧されて、悪用される危険がある。
4 マイナ保険証の取得・管理が困難である人の存在(国民皆保険制度なのに保険証がない国民が出るおそれ)
現行の健康保険証は、特段の申請行為なしに、被保険者(国民)のもとに送付されているのに対して、マイナ保険証は、被保険者(国民)自らが市役所等に出向いて交付申請をして、パスワード等を登録しなければ交付されず、保険証としても利用できない。そのうえ、マイナ保険証に利用する電子証明書を更新するために、最低5年に一度は更新申請手続が必要になる。これらの点で、マイナ保険証は、かえって国民に負担、不便を強いる。
また、このようにマイナ保険証が、申請やパスワード管理を必要とすることから、マイナ保険証の取得、管理、及び更新が困難な高齢者、障害者らの存在が具体的に想定される。マイナ保険証の取得、管理、更新ができない結果、保険医療を受けられなくなったり、パスワードやカードの管理が不十分で、個人情報の漏えいや財産に対する危険が生じたりすることが危惧される。
これらの問題点に対して、政府は、マイナ保険証を取得していない者全員に申請なしに「資格確認書」を交付するとか、パスワードなしのマイナ保険証を発行するといった対策をとるというが、前述の通り、資格確認書は経過措置に過ぎないし、パスワードなしのマイナ保険証は、保険者や医療機関にさらなる対応を求め、負担をかけるものと言わざるを得ない。
5 結語
そこで、当連合会は、政府に対し、下記の措置を求めることをここに決議する。
記
マイナ保険証への原則一本化方針を撤回し、現行の健康保険証の発行を存続させる。
以上
2024年(令和6年)10月18日
中 部 弁 護 士 会 連 合 会
提 案 理 由
1 はじめに
政府は、令和6年12月2日をもって、現行の健康保険証の新規発行をやめ、マイナンバーカードに健康保険証の機能を持たせた「マイナ保険証」へ移行することを閣議決定した。
政府は、マイナ保険証を強引に進めようとするため、令和6年5月から7月の3か月間にマイナ保険証の利用人数の増加に応じて、医療機関は最大20万円、病院は最大40万円の一時金を支払うなどの金銭的なインセンティブを付与している。
しかし、このような経済的な手段による露骨な誘導にもかかわらず、現在なおマイナ保険証の利用率が低調であるのは、後述の情報漏えいやプライバシー侵害に対する国民の心配などが要因として考えられる。
しかるに、マイナ保険証一本化に対する反対声明は、日弁連(令和5年11月14日)、福岡県弁護士会(令和4年12月26日)、仙台弁護士会(令和5年5月19日)、大阪弁護士会(令和5年12月22日)、愛知県弁護士会(令和6年5月1日)、兵庫県弁護士会(同年6月28日)、滋賀弁護士会(同年8月21日)、熊本県弁護士会(同年9月11日)、広島弁護士会(同年9月12日)と全国で声明を発布しているのは8単位会(中弁連内では愛知県の1単位会のみ)にとどまり、法律専門家である弁護士間でさえもマイナ保険証一本化に対する問題意識は十分共有されていないと思われる。
そこで、中弁連定期大会から2カ月後に施行が迫っている、現行健康保険証の新規発行の取りやめの前に、改めて、中弁連圏内からマイナ保険証の問題点を周知、共有していただくため、本提案をする次第である。
以下、理由を詳述する。
2 マイナンバーカード任意取得の原則(番号法)違反
マイナンバーカード任意取得の原則は、マイナンバーカードの交付には厳格な本人確認が必要となるため、本人が、市区町村の窓口等に出向かざるを得ないところ、これを国民に強制できないこと、また、カードの取得は、本人がカードの利便性とプライバシー等に対する危険とを利益衡量して選択することができるようにするために定められたものである。
しかるに国民皆保険制度の下では、マイナ保険証への一本化は、カード取得の事実上の強制であり、番号法第17条第1項の申請主義(任意取得の原則)に反する。
3 情報漏えいに対する危惧
また、マイナ保険証(マイナンバーカード)には、健康保険証機能のみならず、2023(令和5)年4月から保険医療機関・薬局に義務化されたオンライン資格確認等システムの整備に伴い、当該被保険者(国民)の診療・薬剤情報、特定健診情報等も結合された。
国は、利便性を謳って、マイナンバーカードの多目的利用を更に押し進めようとしている。
マイナンバーカードに紐づけられる情報が増大し、マイナポータルで閲覧可能な情報が増加すれば、マイナポータルがインターネット回線を通じて提供されるサービスであることから、情報漏えい等を完全に防ぐことは困難であるし、利用者側のセキュリティ対策が脆弱な場合にはID、パスワードを窃取され、なりすましでマイナポータルにアクセスされたりして、医療情報に限られない極めて広範な個人情報が不正に閲覧されて、悪用される危険がある。
4 マイナ保険証の取得・管理が困難である人の存在
(1) 申請しないと取得できないこと
現行の健康保険証は、特段の申請行為を行わなくても、保険者から自宅や職場に送られているのに対して、マイナ保険証は、顔写真を付けてマイナンバーカードの交付申請を行った上、市役所等で厳格な本人確認を行い、パスワード等の登録を行わなければ交付を受けて保険証として利用できない。その上、マイナ保険証に利用する電子証明書を更新するために、最低5年に一度は更新申請手続が必要となる。
(2) 介護施設入居者等にとって対応困難なこと
上記(1)で述べたように、マイナ保険証は申請やパスワードが必須であるため、上記健康保険法等の一部改正法案の国会審議で、マイナ保険証の取得や管理、更新手続が困難な介護施設入居者、独居の高齢者や障害者の方たちは、保険医療が受けられずに、場合によっては生命の危険にすら直面したり、カードとパスワードの管理が困難となるために個人情報漏えいや財産に対する危険に直面したりする可能性が存することが実証的に明らかにされた。
また83.6%の介護施設等で利用者や入所者の保険証を管理しているところ、マイナ保険証に一本化されると、施設でパスワードの管理まで行うことは、施設関係者に多大な負担となることから対応困難との回答が多数寄せられている(令和5年3月下旬から同年4月にかけて、全国保険医団体連合会(保団連)が42都道府県の介護施設等を対象に行った調査結果)。
これに対して、政府からは、暗証番号なしのマイナ保険証を作るなどという対策案も出されたが、それでは顔認証できない場合は医療機関が目視により本人確認をするなど特別の対応をせざるを得なくなるなどの問題があり、保険者や医療機関にさらなる負担をかけるものと言わざるを得ない。
5 プライバシー保障について
(1) 診療・薬剤情報、特定健診情報等との結合
診療・薬剤情報、特定健診情報等との結合が当然の前提とされているが、健康保険証機能をデジタル化するだけであれば、診療・薬剤情報、特定健診情報等とマイナ保険証とを結合させる必要はない。
現在、マイナ保険証とオンライン資格確認等システムの整備に伴い、自分の診療・投薬情報、特定健診情報等との結合が当然の前提とされており、これに同意しない手続は存在しない。
しかし、医療機関では個別にこれらの情報を提供するかについて不同意が選択できるように、診療・薬剤情報、特定健診情報等との結合自体も拒む機会を与えるのが、センシティブ情報である医療情報の保護として相当である。
診療・薬剤情報、特定健診情報等との包括的連携を拒む手続が保障されていない現在のマイナ保険証のシステムはプライバシー保障に欠ける。
(2) オンライン資格確認時に説明なしの同意を求めるシステム
令和5年4月から義務化されたオンライン資格確認システムでは、患者は、受診時に、マイナ保険証を用いてオンライン資格確認をする際、同時に、特定健診情報や過去の投薬情報等を医療機関に提供することについて「同意」を求められる。しかし、これは、医師から、その情報を提供する必要性等について何も説明を受けないうちに「同意」を求められるということであり、また、投薬情報等について、過去3年分の全ての投薬情報の提供について、一括して「同意」を求められ、患者は提供範囲の選択ができないシステムとなっている。
これらは患者の、自己の医療情報にかかる「コントロール権」をないがしろにするシステムである。
(3) データマッチング(名寄せ)とAIによるプロファイリングについて
上記のように、診療・薬剤情報、特定健診情報等が新たにマイナンバーに紐づけられた情報となることは、マイナンバーによりデータマッチング(名寄せ)可能な情報の範囲が広がることを意味する。
マイナンバーによりデータマッチング(名寄せ)可能な情報の範囲が広がれば、(AIによる)プロファイリングに関する法的な規制が整備されていない現状において、個人のプライバシーにとって脅威となる。
6 結語
以上の理由から、政府に対し、マイナ保険証への原則一本化方針を撤回し、現行の健康保険証の発行を存続させることを求める。
以上