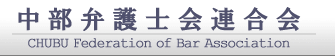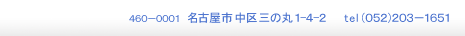�P�@����Љ�ɂ�����`�h�̗��p����
���B�́A���퐶���̗l�X�ȏ�ʂŁA�f�W�^���Z�p�̉��b�ɂ�������A�f�W�^���Z�p�ɐZ�肫���������𑗂��Ă���B�`�h���Љ�̗l�X�ȕ���ɗ��p����A�l�Ԃ̎d�����ւ���悤�ɂȂ�Ȃǂ`�h�̑��݂����܂�������́A�`�h����ƌĂԂ��Ƃ��ł���B
�������A���ᔻ�ɂ`�h���܂ރf�W�^���Z�p�̗����p������Ă������Ƃ́A���������B�̐l�i�܂ł��`�h�Ɏx�z�����悤�ɂȂ��Ă��܂��댯����s��ł���B���̎Љ�ɂ����āA���B���l�Ƃ��Ă̑������ێ����A�����I�ɂ`�h���܂ރf�W�^���Z�p�𗘊��p���Ă������߂ɂ́A�f�W�^���Z�p�A���ɂ`�h���A���@��̗��O�A�l���̊ϓ_����A�ᔻ�I�Ɍ��ߒ����K�v������B
�Q�@�`�h�̗����p�ɐ��ފ댯���ƌ��@��̗��O�A�l��
�i�P�j�u�l�̑����v�̌���
���@�́A�l���̍ł���{�I�ȗ��O�Ƃ��āA�u�l�̑����v�̌�����搂��Ă���B
���́u�l�̑����v�̌����ɂ����ẮA�S�Ă̐l�ɑ���l�ԂƂ��Ă̑����̍l������O��ɁA�g�����Ȃǂ̏W�c�I�S������̌l�̉���A�l�̎����A���Ȍ���̑��d�A�����ĎЉ�ɂ�鑽�l���̑��d�Ƃ����K�͂��������B
�i�Q�j�v���C�o�V�[���ɑ���댯
�`�h�́A�l���C���^�[�l�b�g�𗘗p���������Ȃǂ̃f�W�^���f�[�^�����ʂɎ��W���A���p���Ă���B����́A�l�����l�ɒm��ꂽ���Ȃ���������̏����܂ޓ_�ŁA�v���C�o�V�[����N�Q����\��������B
�i�R�j���ʂ���������댯
�`�h�����W������́A��̂Ȃ������Ȃ��̂ł���Ƃ͌���Ȃ��B�Ό���X�e���I�^�C�s���O���ꂽ�f�[�^�ɂ���Ċw�K������A���R�A�������瓱����錋�ʂ��o�C�A�X�̂����������̂ƂȂ�B
���̂悤�ȕ������f���Ȃ��ꂽ�Ƃ��A���B�́A�`�h�i�R���s���[�^�j����ʂ̃f�[�^�Ɋ�Â��Ă��̔��f���o�����Ƃ��������Ŕ��_�̏p���������˂Ȃ��B�`�h�ɂ��o�C�A�X�ɑΏ��ł��Ȃ�����u���邱�Ƃ́A�`�h�ɂ�鍷�ʂ��������邱�ƂɂȂ���B
�i�S�j������l���]���ƁA���ꂪ�Œ艻����댯
�`�h�́A�l�̃E�F�u�T�C�g�̉{�������Ȃǂ̃f�[�^�ɂ���āA���̌l���ǂ������X����L����l���Ȃ̂���\���E���͂��A�u���Ȃ��͂��������l���ł��v�Ƃ������f������i�v���t�@�C�����O�j�B
�`�h���v���t�@�C�����O�ɂ��o�͂��錋�ʂ́A�l���Ɋ�Â��O���[�v���A���b�e���\����s���Ƃ����_�ŁA�u�l�̑����v�̌����ɂ��W�c�I�ȍS�����������ꂽ�͂��̐l�Ԃɑ��āA�ĂѐV���ȍS�������邱�ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B
�܂��A���ȂɊւ����A�l�i�Ɩ��ڕs���̂��̂ł���Ȃ�A�u�l�̑����v�̌����Ɋ�Â��āA�ǂ̂悤�Ȏ��ȏ�W�߂��Ă��邩��m��A�l���Ɋ�Â��O���[�v��������A�������m�ۂ��邽�߂ɁA���ȏ����R���g���[�����錠�����F�߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��i���ȏ��R���g���[�����j�B
�i�T�j���Ȍ��茠�A���S�̎��R�ɑ���댯
�`�h�ɂ��v���t�@�C�����O�́A�C���^�[�l�b�g��̏����{������l�̎����f���A����ɉ�����������̑I�����Ē��Ă���B����͂���Γ��Y�l�̔F�m�ߒ�����������Łu������v���n�b�L���O������̂ł���A�l�̎����I�Ȉӎv����i���Ȍ��茠�j��c�߂邱�ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B
�i�U�j�����`�̕���ɂȂ���댯
�l�̎��Ȍ��茠�̑��삪�e�l�̐����I�ӎv����̏�łȂ����A�ߑ㗧����`���Ƃ̊�Ղ��Ȃ������`�A�����匠���Q���邨���ꂪ����B�Ƃ�킯�A�����Ŕ��B�������������`�h����g���čI���ȋU���i�f�B�[�v�t�F�C�N�j���쐬����邱�ƂɂȂ�A���̊댯�͑傫���������ƂɂȂ�B
�R�@�`�h�ɑ���K���̐��E�I����
��L�̂悤�Ȃ`�h�̊댯���܂��A�`�h�̊J���y�ї��p�ɂ��āA�e���E�n��ɂ����ėl�X�ȋK������������Ă���B
���ɁA�d�t�ł́A2016�N�ɐ��������f�c�o�q�i�d�t��ʃf�[�^�ی�K���j�ɂ����āA�v���t�@�C�����O�ɑ��Ĉًc���q�ׂ錠�����K�肷��Ȃǃv���t�@�C�����O�̐�����K�肵�āA������������`�h�̋K���ɂ��Ĉӎ��������ċc�_����Ă������A2024�N�R��13���A�`�h�@�����B�c��ɂ���ď��F���ꂽ�B
�܂��A�č��ł́A2023�N10���ɂ`�h�̈��S�ȊJ���Ɨ��p�Ɋւ���哝�̗߂����o����A�`�h�������炷���v�����邽�߁A�`�h�̖��ӔC�Ȏg�p�ɂ�郊�X�N���y�����邱�Ƃ��K�v�ł���Ƃ������ꂪ������Ă���B
���A�ɂ����Ă��A2024�N�R��21���A���A����Ől�H�m�\�i�`�h�j�̊J���◘�p�ȂǂɊւ��錈�c�Ă��̑�����A�`�h�V�X�e�����A�r�c�f���̒B���Ɋ�^�����邽�߂ɂ́A���S�ŁA���S�A�M���ł���`�h�V�X�e���Ɋւ���K�������K�v�ł���Ƃ��Ă���B
�����āA�䂪���ł��A2024�N�S��19���ɑ����ȁA�o�ώY�ƏȂ��A�`�h�J���E�E���p�ɂ������ĕK�v�Ȏ�g�ɂ��Ă̊�{�I�ȍl�������������̂Ƃ��āA�u�`�h���Ǝ҃K�C�h���C���v�i��1.0�Łj�����\�����B���K�C�h���C���́A�d�t�Ōf����l���ւ̔z���܂��Ȃ���A�č��̋K���̂悤�ɁA�`�h�̗����p��}�邽�߂Ɉ��S�������m�ۂ��ׂ��ł���Ƃ̊ϓ_���܂܂�Ă�����̂Ǝv���A����ɂ́A����E���e���V�[�Ȃǂ̑��ʂɂ����y���Ă���_�������Ƃ�����B�������A���̂悤�ȃK�C�h���C���ɂ��Ώ��ɑ��ẮA�u�`�h���p�ɑ��Ă������I������������ɂ́A�K�C�h���C���ł͂Ȃ��A�`�h�K���̊�{�I�g�g�݂��߂�@���𐧒肵�A���̒��Ɍ��@���{�I�l���Ƃ̊W�����������菑�����ނ��ƂŁA�`�h�@���Ɍ��@��̉��@�Ƃ��Ă̖��m�Ȉʒu�Â���^����ׂ��ł���B�v�i�R�{���F�c��`�m��w�����j�ȂǂƂ��āA�@�������}����ׂ��Ƃ���ӌ�������B
�S�@���A�������ɋ��߂��邱��
�i�P�j�`�h�ɂ��ẮA���̗L�p���ƍ���̔��B�A�Z����ے�ł��Ȃ��̂������ł���B�����̏�ʂɂ����Ă`�h�́A�s���ׂ̍��Ȗ��ӂ��W�A��������c�[���Ƃ��ė��p���邱�ƂŁA�u�f�W�^�������`�v�Ƃ����ׂ��A�s���F���������������Ƃ��đ����A�����ɎQ���ł���`�h����̐V���Ȗ����`������������傫�ȉ\������߂Ă���B�����炱�����B�́A�`�h�̗����p��}��Ȃ�����A���̋��Ђ��\���ɗ������A���@��̗��O��l�������������Ƃ��Ȃ��悤�ȋK�����A�Z�p�ʁA���x�ʂ̗��ʂ���͍�����K�v������B�܂��A�`�h�ɂ�鋺�Ђ��\���ɗ������A�^��������ɑ��ēK�Ȕᔻ�v�l�i���e���V�[�j�������A�l���𓊂��o���Ȃ��s�����琬���A�f�W�^�������ɂ����Ď��������s������Ȃ�Љ���\�z���邱�Ƃ��K�v�ł���B
�i�Q�j�ٌ�m�ɋ��߂��鎋�_
�f�W�^���Z�p�̋}���Ȑi�W�ɔ����A�V���Ȍ��@��̊�@�������Ă���Ƃ����錻�݁A�L���Ō��S�ȃf�W�^���Љ��z�����߂ɉ�X�ٌ�m���ϋɓI�Ȉӌ��\�����Ȃ������ʂ͑����͂��ł���B��X�ٌ�m�́A�`�h���܂ރf�W�^���Z�p���A�l���ɂǂ̂悤�ȉe����^������̂��Ƃ����ϓ_�ŁA�������������Ĕᔻ�I�ɖڂ����点�Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�Y��ĂȂ�Ȃ��̂́A�`�h����ʂɎ��W�����f�[�^�Ɋ�Â��ĉ�͂��s���A���̒��́u�����v�ɐe�a�I�ȋZ�p�ł���Ƃ����_�ł���B��{�I�l���̗i����g���Ƃ����X�Ƃ��ẮA��ɏ����h�̐l����ی삷��Ƃ������_�ŁA�`�h�ɑ���K���̂�������������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�i�R�j�s������̕K�v��
���݂̃f�W�^���Љ�̊����ł́A���K�Ƀf�W�^���Z�p����g���Ă���s���́A�C�Â��Ȃ������Ɏ���̐l������@�ɂ��炳��Ă���Ƃ�������B���̂悤�Ȏs���ɑ��A���̂悤�Ȍ���𐳊m�ɓ`���Ă������Ƃ��܂��A�s���ւ̖@�����S����X�ٌ�m�̎g���Ƃ�����B
��X�ٌ�m�́A�w�Z����ւ̔h�����Ƃ⎙���A���k��ΏۂƂ����I�[�v�����ƁA����҂Ƃ��Ă̎Љ�Q��𑣂�����Ҏs������̎��H�Ȃǂ�ʂ��A�܂��A�s���W���V���|�W�E���̎�Ó��Ŗ���N�ƌ����̏����邱�ƂȂǂ�ʂ��āA�K�ȃf�W�^�����e���V�[���������鋳��̏����Ă����ׂ��ł���B
�T�@����
�ȏ���A�����ٌ�m��A����́A����A�Љ�ɂ����Ă`�h�̗����p�����i����Ă����ɂ�����A�����Љ�݂̂Ȃ炸�A�T�C�o�[��ԏ�ɂ����Ă����@��̊�{�I�l�����i�삳��邱�ƁA�����āA�`�h�̃����b�g�����Ȃ�����A�S�Ă̌l���`�h�ɂ���Ĉӎv�����c�߂��邱�ƂȂ��A�����I�Ɏ��Ȍ�����Ȃ����Ƃ��ł��閯���`�Љ�������������ƍl����B
���̂悤�ȎЉ���������邽�߁A���A����́A�ȉ��̊��������邱�Ƃ�錾����B
�i�P�j�`�h�̋}���Ȕ��W�A���p�̏�̊g�哙�A����܂��܂��i�W���Ă����f�W�^�����ɂ����āA�`�h�̗����p��}��Ȃ�����A���@��̗��O��l���ɑ��鋺�Ђ��\���ɗ������A���\���ꂽ�K�C�h���C�����̑��̕���ɂ��Đl���̊ϓ_���猟�������P���ׂ��_���w�E���铙�A�`�h�ɑ���K�ȋK���̎����Ɍ������𑱂��邱�ƁB
�i�Q�j�`�h���܂ރf�W�^���Z�p�ɂ���Ă����炳��錻�y�я����̐l���N�Q�A���ɏ����h�ɑ���l���N�Q�ɑ��Ėڂ����点�A���̖h�~����ы~�ς̂��߂̊����Ɉ��������͂����Ă������ƁB
�i�R�j�������Ȃ��f�W�^���Љ�̐i�W�܂��A�s���ɑ��ăf�W�^���Z�p�ɂ��댯���܂߂Đ��m�Ȓm����`���A���Ē�������Љ�ɎU������U���ɘf�킳��Ȃ����������s���̈琬�Ɋ�^���鋳��̐��i�ɋ��͂��邱�ƁB
�ȏ�
�Q�O�Q�S�N�i�ߘa�U�N�j�P�O���P�W��
���@���@�ف@��@�m�@��@�A�@���@��
�� �� �� �R
�P�@����Љ�ɂ�����`�h�̗��p����
���B�́A���퐶���̗l�X�ȏ�ʂŁA�f�W�^���Z�p�̉��b�ɂ�������A����ł́A�f�W�^���Z�p�ɂ���đ�ʂ��e�Ղɒ~�ς����v���C�o�V�[���ɑ��ċ^��������Ȃ���A�f�W�^���Z�p�ɐZ�肫���������𑗂��Ă���B�`�h���Љ�̗l�X�ȕ���ɗ��p����A�`�h���l�Ԃ̎d�����ւ���悤�ɂȂ�Ȃǂ`�h�̑��݂����܂�������́A�`�h����ƌĂԂ��Ƃ��ł���B
���{�ٌ�m�A����ł́A2022�N�X���Q�X���A��64��l���i����ɂ����āA�u�f�W�^���Љ�̌��ƉA�`�֗����ɉB���ꂽ�v���C�o�V�[�E�����`�̊�@�`�v�Ƃ����e�[�}�ŁA�V���|�W�E���i��Q���ȉ�j���J�Â����B�����ł́A�s���^�[�Q�e�B���O�L���ƃv���C�o�V�[�̖��A�M�p�X�R�A�̖��A�l�H�m�\�ɂ���Čl�̃v���C�o�V�[�⎩�Ȍ��茠�ɉe�����^������Ƃ������A�ƍߗ\���V�X�e���̐���A��F�؋Z�p�̗����p�ɔ������Ȃǃf�W�^���Z�p�ɊW����L�ĂȖ�肪�w�E����A�������ꂽ�B
���̌㍡���܂ŁA�f�W�^���Z�p�͂܂��܂��i�����Ă���A���ɁAChatGPT�iOpenAI�Ђ̏��W�j�ɑ�\����镶�͂�C���X�g�Ȃǂ������I�ɐ������鐶���`�h���g�߂Ȃ��̂ɂȂ�ƁA���̗����p���}���ɐi�݁A���̋Z�p���������i�������B�܂��A���������܂��āA�e���E�n��ɂ����Ă͂`�h�̊J���y�ї��p�ɂ��ėl�X�ȋK�����{�������������ɂȂ��Ă��Ă���B
�l�H�m�\�i�`�h�FArtificial Intelligence�j�Ƃ́A�����ȁA�o�ώY�ƏȂ�2024�N�S��19���Ɍ��\�����`�h���Ǝ҃K�C�h���C���ɂ��A�ꉞ�A�u�@�B�w�K������\�t�g�E�F�A�Ⴕ���̓v���O�������܂ޒ��ۓI�ȊT�O�v�Ƃ���Ă͂��邪�A���m�Ȓ�`�͂Ȃ��̂�����ł���B�������A������̒�`�ɂ����Ă��A�`�h���u��ʂ̃f�W�^���f�[�^�����W�E�~�ρv���A����Ɋ�Â��āu�w�K�v������̂ł���Ƃ��������͋��ʂ��Ă���悤�Ɏv����i�{�錾�Ăɂ����ẮA��������������L����V�X�e���Ƃ����Ӗ��ŁA�`�h�Ƃ����p���p������̂Ƃ���B�j�B
��64��l���i����ɂ����Ă��w�E����Ă������ł͂��邪�A�`�h�́A�l���C���^�[�l�b�g�𗘗p���������Ȃǂ̃f�W�^���f�[�^�����W���A���͂��邱�Ƃɂ���āA���̌l�̋�����n�D�A����Ƃ��������ʂ𐄑����A�܂��s����\�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă���B���ꂾ���ł͂Ȃ��A�`�h�́A���̌l�ɗ^������𑀍삷�邱�ƂŎv�l�ɉe�����y�ڂ��A���̍s����U�����邱�Ƃ܂ʼn\�ɂȂ��Ă���B�`�h�́A���B�̈ӎv����Ƃ����Ӗ��ł̐l�i�ɂ܂ʼne�����y�ڂ����Ƃ��Ă���̂ł���B
���B���A���ᔻ�ɂ`�h���܂ރf�W�^���Z�p�̗����p������Ă����A���������B�̐l�i�܂ł��`�h�Ɏx�z�����悤�ɂȂ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ��낤���B���̎Љ�ɂ����āA���B���l�Ƃ��Ă̑������ێ����A�����I�ɂ`�h���܂ރf�W�^���Z�p�𗘊��p���Ă������߂ɂ́A�f�W�^���Z�p�A���ɂ`�h���A���@��̗��O�A�l���̊ϓ_����A�ᔻ�I�Ɍ��ߒ����K�v������̂ł͂Ȃ��낤���B���ꂪ�A���A����̖��ӎ��ł���B
�Q�@�`�h�̗����p�ɐ��ފ댯���ƌ��@��̗��O�A�l��
�i�P�j�u�`�h�@�댯�v�Ȃǂ̃L�[���[�h�ŃC���^�[�l�b�g�̋L������������ƁA�`�h�험�p����댯��A�`�h�ɂ���Đl�Ԃ̎d�����D����댯�Ȃǂ̎w�E�������邪�A�����́A�`�h�̎g�p���@�ɊW����댯�ł��낤�Ǝv����B�����̊댯�ւ̑Ώ����d�v�Ȗ��ł͂��邪�A�����ł́A���@��̉��l�A���O�����Ƃ����ϓ_�ɗ����āA�`�h�̗��p�ɂǂ̂悤�Ȋ댯��������ł���̂����A�]�O�w�E����Ă�������܂߁A�����������B
���@�́A�l���̍ł���{�I�ȗ��O�Ƃ��āA�u�l�̑����v�̌�����搂��Ă���B
��\�O���@���ׂč����́A�l�Ƃ��đ��d�����B�����A���R�y�эK���Nj��ɑ��鍑���̌����ɂ��ẮA�����̕����ɔ����Ȃ�����A���@���̑��̍����̏�ŁA�ő�̑��d��K�v�Ƃ���B
���́u�l�̑����v�̌����ɂ����ẮA�S�Ă̐l�ɑ���l�ԂƂ��Ă̑����̍l������O��ɁA�g�����Ȃǂ̏W�c�I�S������̌l�̉���A�l�̎����A���Ȍ���̑��d�A�����ĎЉ�ɂ�鑽�l���̑��d�Ƃ����K�͂��������B
�`�h�͋@�B�ł���A���B�͐l�Ԃł���B���A�`�h�Ƃ����@�B�ɂ���āA���B�l�Ԃ̍ł������I�Ȑl���₻��Ɋ�Â����@��̉��l����������悤�Ƃ��Ă���B
�i�Q�j�v���C�o�V�[���ɑ���댯
�`�h�͊w�K�̉ߒ��ɂ����āA��ʂ̃f�W�^���f�[�^�����W���A���͂���̂ł��邪�A���̒��ɂ́A���B�̒m��Ȃ������Ɏ��W����Ă���f�[�^������B�Ⴆ�A���B���C���^�[�l�b�g�Ō�����������A�E�F�u�T�C�g���{�������肷��A���̗����́A�N�b�L�[�𗘗p���邱�ƂŁA���̊Ԃɂ��A�`�h�Ɏ��W����Ă��邱�Ƃ�����B�������A�{�l���֘A�������o���Ă��Ȃ������̃E�F�u�T�C�g�̉{�������܂ŁA�R�t���Ď��W���邱�Ƃ��\�Ȃ̂��B�`�h�́A�u���Ȃ��v�̃C���^�[�l�b�g��̍s�����A���Ȃ��ȏ�ɒm���Ă���̂ł���B
�f�`�e�`�iGoogle�AApple�AFacebook�iMeta�j�AAmazon�e�Ёj�ɑ�\�����f�W�^���v���b�g�t�H�[���i�c�o�e�j���Ǝ҂́A�������ăE�F�u�T�C�g�̖K�◚���A�d�b�i�C�[�R�}�[�X�A�d�q������j�T�C�g�ł̍w�������A�L���{�������A�����G���W���ł̌������A�C���^�[�l�b�g��ł̖c��ȃf�W�^���f�[�^�����W���A�ǐ肵�Ă���A���̗����p�ɂ��A����ȗ��v�ƌ��͂Ă���B
���̂悤�ɁA�`�h�́A�l���C���^�[�l�b�g�𗘗p���������Ȃǂ̃f�W�^���f�[�^�����A��ʂɁA�{�l�̓��ӂȂ��A���ɂ͖{�l����������m��Ȃ������Ɏ��W����B���R�����̃f�W�^���f�[�^�ɂ͌l�����l�ɒm��ꂽ���Ȃ��A��������̏����܂ݓ���B�l�̏��́A�l�̐l�i�ƈ�̕s���̂��̂ł���A��������̂悤�Ɏ��W���邱�ƁA�܂����W�F���邱�Ƃ́A���@13���Ɋ�Â��v���C�o�V�[����N�Q����\��������B�܂��A����݂̂Ȃ炸�A�`�h�����W�����v���C�o�V�[���́A�ȉ��̂悤�ɁA�W�c�I�ȍS�����������ꂽ�͂��̐l�Ԃɑ��ĐV���ȍS�����ۂ����ƂɂȂ肩�˂Ȃ��p�r�ɗ��p����Ă���B
�i�R�j���ʂ���������댯
�`�h�����W����̂́A�l�̉{���������ł͂Ȃ��B�C���^�[�l�b�g��Ɉ��邠��Ƃ�����f�[�^�����W���Ă���B�������A��ʂɃf�[�^�����W���邩��Ƃ����āA���̃f�[�^���A��̂Ȃ������Ȃ��̂ł���Ƃ͌���Ȃ��B�Ό���X�e���I�^�C�s���O���ꂽ�f�[�^�ɂ���Ċw�K������A���R�A�������瓱����錋�ʂ��������̂ƂȂ�B
�Ⴆ�A�č��ł͍��l�����l����������������Ă����Ƃ������т����邽�߁A���̂悤�ȉߋ��̔ƍ߃f�[�^��p���Ă`�h�Ɋw�K��������ƁA���l��ƍ߂̃��X�N�������l�X�Ƃ������ʓI�Ȕ��f���ʂ��o�����Ƃ����댯�����]�O����w�E����Ă���B�����f�[�^�ɂ��w�K�̕��Q�́A�ƍߕ���Ɍ��������̂ł͂Ȃ��B�Ⴆ�A�`�h�́A�ߋ��̃f�[�^�Ɋ�Â��āA�u�����炵���v�A�u�j���炵���v�Ƃ������l�ςɊւ��ĕ������f���o�����Ƃ�����B
���̂悤�ȕ������f���Ȃ��ꂽ�Ƃ��A���B�́A�����ے�ł���ł��낤���B��ʂ̃f�[�^�Ɋ�Â��āA�`�h�i�R���s���[�^�j���o�͂����Ƃ��������ŁA���B�͔��_�̈ӗ~�������A���ʂᔻ�Ɏ����S���ɂȂ�͂��Ȃ����B���_���悤�ɂ��A�`�h���ǂ̂悤�ȃf�[�^�𗘗p�����̂����A�ǂ̂悤�ȃ��W�b�N�Ō��ʂ��o�����̂����u���b�N�{�b�N�X�ł��邽�߁A���Y���ʂɑ��āA�o�C�A�X�̗L�����A���f���邱�Ƃ͂قڕs�\�ł���B�`�h�ɂ��o�C�A�X�ɑΏ��ł��Ȃ�����u���邱�Ƃ́A�`�h�ɂ�鍷�ʂ��������邱�ƂɂȂ���B
�i�S�j������l���]���ƁA���ꂪ�Œ艻����댯
�`�h�ɂ�镪�͎�@�́A�u�v���t�@�C�����O�v�Ƃ��Ă��B�v���t�@�C�����O�Ƃ́A�`�h���A�l�̃E�F�u�T�C�g�̉{�������Ȃǂ̃f�[�^�ɂ���āA���̌l���ǂ������X����L����l���Ȃ̂���\���E���͂��邱�Ƃ������B�`�h���A�u���Ȃ��͂��������l���ł��v�Ɣ��f���Ă����̂��B
�l�̎����ɍ������L����\��������^�[�Q�e�B���O�L�����A�v���t�@�C�����O�̌��ʂƂ��Ă����炳�����̂̈�ł���B�f�`�e�`�Ȃǂ̂c�o�e���Ǝ҂��~�ς��Ă����ʂ̃f�[�^�́A�`�h��p���ĕ��͂����邱�Ƃɂ��A���[�U�[�̎�A�n�D��S�A�o�Ϗ�ԓ��𐄑����A�œK�ȃ^�C�~���O�ōL����\�������邱�ƂȂǂɗ��p����Ă���B
�v���t�@�C�����O���l�̑������ɗ��p���ꂽ���Ƃ��āA2019�N�́u���N�i�r�����v����������B�w�����A�A�E�����ɗ��p����T�C�g�ł���u���N�i�r�v�̉^�c�Ђ��A�w���̃E�F�u�T�C�g�̉{�������Ȃǂ����W���āA�`�h�Ńv���t�@�C�����O���邱�Ƃɂ��A��������ނ������Ȋw����\�����Ă����̂ł���B�������A���̌��ʂ��̗p���̊�Ƃɔ̔����Ă����̂��B�w�����炷��ƁA���Ȃ̐l�����d����邱�ƂȂ��A�u��������ނ������v�Ƃ������b�e�����`�h�ɏ���ɂ����Ă������ƂɂȂ�B
�v���t�@�C�����O�Ɋւ��[���Ȗ��Ƃ��āA�\�[�V�����X�R�A�̖�肪�w�E����Ă���B�\�[�V�����X�R�A�Ƃ́A�`�h���A�l�̎Љ�I�ȐM�p�X�R�A���A�l�X�ȑ����Ɋ�Â��Ċi�t�����邱�Ƃ������B��U�A�\�[�V�����X�R�A���Ⴍ�i�t������Ă��܂��ƁA�Љ�I�E�o�ϓI�ȐM�p������ꂸ�A���ʂƂ��āA���܂ł��i�t�������P����Ȃ��Ƃ����a�n���Ɋׂ��Ă��܂��i����̓o�[�`�����X�����ƌĂ�Ă���B�j�B�`�h�ɂ��v���t�@�C�����O�ł́A�`�h�ɂ���ď���Ɋi�t������邾���łȂ��A���ꂪ�Œ艻���Ă��܂��Ƃ����댯������̂��B
����́A�`�h���e�l�̂�������m��Ȃ������ɑ�ʂ̏������W���A�{�l���]�܂Ȃ��p�r�ŗ��p���Ă���Ƃ������悤�B�����āA�`�h���o�͂��錋�ʂ́A�u�l�v�Ƃ��đ��d�����]���ł͂Ȃ��A�����Ɋ�Â��O���[�v���A���b�e���\��Ƃ����_�ŁA�u�l�̑����v�̌����ɂ��W�c�I�ȍS�����������ꂽ�͂��̐l�Ԃɑ��āA�ĂѐV���ȍS�������邱�ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B
�܂��A���ȂɊւ����A�l�i�Ɩ��ڕs���̂��̂ł���Ȃ�A���@13���Ɋ�Â��āA�ǂ̂悤�Ȏ��ȏ�W�߂��Ă��邩��m��A�s���Ɏg���Ȃ��悤�֗^���錠�����F�߂���ׂ��ł���B�`�h���{�l�̓��ӂȂ��s���v���t�@�C�����O�ɑ��āA�l���Ɋ�Â��O���[�v��������A�l�̎������m�ۂ��邽�߂ɂ́A���ȏ��ɑ��邱�̂悤�ȃR���g���[���̌����i���ȏ��R���g���[�����j���F�߂���K�v������B�������A�킪���ł͌��݂܂ŁA�����������ȏ��R���g���[�����͌����ɂ͏��F����Ă��Ȃ��B
�i�T�j���Ȍ��茠�A���S�̎��R�ɑ���댯
�v���t�@�C�����O�́A�l�̊S�̗\���Ɋ�Â��Ĉӎv����ւ̉���������邱�Ƃ��\�ƂȂ��Ă���A�l�̈ӎv����ɑ��ċ���ȉe����^���邱�ƂȂǂ����O����Ă���B
�v���t�@�C�����O�́A�l�ɗ^������ɂ��Ȃ���B�����A�`�h�́A�v���t�@�C�����O�ɂ���āA�l�ɑ��A��������^����̂��B�����ɖ��𒍂��̂��A�e���V�����G�R�m�~�[�ł���B
�A�e���V�����G�R�m�~�[�Ƃ́A���̐��m���Ƃ͊W�Ȃ��A���p�҂̃A�e���V�����i�S�j���W�߂���ɏd�����u����邱�Ƃ������B�A�e���V�����G�R�m�~�[�̉��ł́A���ӂ��Ђ��₷���h���I�ȏ�Љ�Ɉ���悤�ɂȂ�B�����āA�l���������������{������ƁA�`�h���e�ɂ��A���̌l�̎����f���A����ɉ�����������̑I�����Ē���悤�ɂȂ�B���̂悤�ɑI��ł���������́A���R�A�{�l�ɂƂ��čD�݂̏��ł��邩��A���̌l�́A�����{�����Ă��܂��B����ƁA�`�h�́A�����������̎����ɉ��������݂̂�I�����Ē���悤�ɂȂ�B�������A���̌l�́A���̏��ɐG��邱�ƂȂ��A�����ɂƂ��ĐS�n�悢���ɕ������߂�ꂽ��ԂɊׂ�B���̂悤�ȏ�Ԃ́A��ɂr�m�r��ŋN����Ƃ��ăG�R�[�`�����o�[�A��Ɍ����G���W����ŋN����Ƃ��ăt�B���^�[�o�u���ƌĂ��B
�A�e���V�����G�R�m�~�[���̂́A���Ɏn�܂������Ƃł͂Ȃ����A�l�ɗ^��������Ƃ����e���́A�`�h���֗^���邱�ƂŁA�i�i�ɑ傫���Ȃ��Ă���̂ł���B�����āA�l�ɗ^�����Ă�����ɕ肪�����邱�Ƃ́A���̌l�̎v�l�i���S�j���x�z���A�ӎv����ߒ������c�߂Ă��܂����ƂɂȂ���B
���̂悤�ɁA�`�h�́A�C���^�[�l�b�g��̏����{������l�̎����f���A����ɉ�����������̑I�����Ē��Ă���B����͂���Γ��Y�l�̔F�m�ߒ�����������Łu������v���n�b�L���O������̂ł���A�l�̎����I�Ȉӎv����i���Ȍ��茠�j��c�߂邱�ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B
�l�̈ӎv����̉ߒ��A�l�̓��S�̗̈�́A�ł����I�ȗ̈�ł���ɂ�������炸�A�`�h�͂܂��ɂ������^�[�Q�b�g�ɂ��Ă���Ƃ����_�ɁA��X�͑傫�Ȋ�@��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�i�U�j�����āA�����`�̕���ɂȂ���댯
�l�ւ̕������Ƃ���ɂ��ӎv����̑���́A�����I�ӎv����������ł��Ȃ����ꍇ�����R�z�肳���B
�����Â������ɂ͂Ȃ邪�A�u�P���u���b�W�E�A�i���e�B�J�����v�́A�`�h�ɂ���āA�l�̈ӎv���肪���삳�ꂽ��Ƃ��Ēm���Ă���B���̎����ł́A�I���R���T���^���g��Ђł���P���u���b�W�E�A�i���e�B�J���A�r�m�r�̃f�[�^�Ȃǂ���l���v���t�@�C�����O���āA���̐��i�Ȃǂɉ����������L�����o�������邱�ƂŁA���̈ӎv����𑀍삵�A2016�N�ɍs��ꂽ�A�����J�哝�̑I�Ȃǂɉe����^�����Ƃ������̂ł���B���̎����ł́A�ӎv����𑀍삳�ꂽ�l�X�́A����������ł��A�Ö��p�ɂ�����ꂽ��ł��Ȃ��B�����^��������𑀍삳�ꂽ���Ƃɂ���āA���g�́u�^�Ӂv�Ƃ��āA���삳�ꂽ�ӎv������s���Ă���̂ł���B���̂悤�Ȏ�@�����F�����A�����`�́A���{���畢����Ă��܂������ꂪ����B
���̊댯�́A�Ƃ�킯�����`�h�̔��B�ɔ����Đ[���x�𑝂��B���[���ʂ����E���������Ɗ肤�N���������`�h�����p����A���B�́A���U�̏��Ɋ�Â��Ĉӎv������������Ă��܂������������B���ӂ������Đ����`�h�𗘗p����A�����ȃv���p�K���_���쐬���邱�Ƃ��\�ɂȂ�̂�������Ȃ��B
�����`�h�́A��͂��ʂ̃f�[�^���w�K���A����Ɋ�Â��ĕ��́A�摜�A����Ȃǂ̃R���e���c�������I�ɐ�������@�\��L���Ă���B�����`�h�ɂ���ďo�͂����R���e���c�̐��x�͌��サ�Ă���A�`�h�����������Ƃ͂킩��Ȃ����̂��o�Ă��Ă���B
�����`�h�́A�����f�[�^�Ɋ�Â��ĕ����o�͂����邱�Ƃ�����B�܂��A��ɐ����������o�͂���Ƃ͌���Ȃ��B�ނ���A��������e�ł��A�^���̂��Ƃ��o�͂���Ƃ������������ł���B
�ŋ߁A�j���[���[�N�B�ٌ̕�m���A�S�����閯���i�ׂ̎������`�h�ō쐬�����Ƃ���A���݂��Ȃ���������p���Ă��܂����Ƃ�����肪��ꂽ�iCOURTHOUSE NEWS SERVICE June 22, 2023�Q�Ɓj�B���̎����́A�q���Ђ�i�����i�ׂł��������A���Y�ٌ�m�������ŁA�������̍q���Ђ��֘A���Ă���U���̔�������p�����Ƃ���A�����͎��݂����A�����`�h�������Ƃ��炵���o�͂������̂ł������Ƃ����̂ł���B���̎����́A�����`�h����Ƃ��Ă͐M���ł��Ȃ����Ƃ�\���Ă���B�����͂����Ă��A���B�́A��X�̏�ʂŁA�����`�h���쐬�����R���e���c���^�����Ƃ͓���悤�Ɏv����B
�`�h�𗘗p���ċ��U�̃R���e���c������Z�p�́A�u�f�B�[�v�t�F�C�N�v�ƌĂ��B�f�B�[�v�t�F�C�N�̖��́A�ȑO���瑶�݂������̂ł��邪�A�����`�h�����B���Ă������Ƃɂ��A�N�ł���R�X�g�Ńf�B�[�v�t�F�C�N���쐬�ł���悤�ɂȂ��Ă��Ă���_����w�A���ɔ��Ԃ������Ă���B�ŋ߂ł́A�r�m�r�Ȃǂ���l�̉��������W���A����Ɋ�Â��āA�`�h�ŋU�������쐬���Đe����ɂȂ肷�܂��ċ��K�����܂����Ƃ�����������m���Ă���B���̋U�����́A�킸���R�`�S�b���x�̉����f�[�^������ΐ����\�Ƃ����Ă���B
���̂悤�ɐ����`�h�ɂ��U�̃R���e���c�����o���ƁA�l�X�̏�̂ɑ���M�p���h�炬���˂��A�Љ��s����ɂ��邨���ꂪ����Ƃ������Ă���B
�����`�́A�l�̑����̏�ɐ��藧���̂ł���A�l���K���Ɏ��Ȍ���ł��Ă����@�\������̂ł���B�������A���ɂ݂Ă����悤�ɂ`�h�́A�l�̑����ɑ����ʂ���댯���y�ڂ��A���ɂ͎��Ȍ��茠�܂Ŏx�z���悤�Ƃ��Ă���̂ł���B�����l�̎��Ȍ��茠�̑��삪�e�l�̐����I�ӎv����̏�łȂ����A�ߑ㗧����`���Ƃ̊�Ղ��Ȃ������`�A�����匠���Q���邨���ꂪ���邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B�Ƃ�킯�A�����`�h�������҂Ɋւ���I���ȃf�B�[�v�t�F�C�N���쐬���邱�ƂɂȂ�A������U�����ƌ������邱�Ƃ�����ɂȂ邱�Ƃ͂������A���ɋU�����ƌ�������ꂽ�l�ɂƂ��Ă����ӎ����ł̓��Y���҂̈�ۂ𑀍삳���\���͔ے�ł��Ȃ��B
�R�@�`�h�ɑ���K���̐��E�I����
��L�̂悤�Ȃ`�h�̊댯���܂��A�`�h�̊J���y�ї��p�ɂ��āA�ȉ��Ɏ����Ƃ���e���E�n��ɂ����ėl�X�ȋK������������Ă���B
�i�P�j�d�t�̋K��
�d�t�ł́A2016�N�ɐ��������f�c�o�q�FGeneral Data Protection Regulation�i�d�t��ʃf�[�^�ی�K���j�ɂ����ăv���t�@�C�����O���܂ފ��S�����ӎv����ɕ����Ȃ������A�v���t�@�C�����O�ɑ��Ĉًc���q�ׂ錠�����߁A�v���t�@�C�����O�̐�����K�肵�āi��21���A22���j�A������������`�h�̋K���ɂ��Ĉӎ��������ċc�_����Ă����B�����āA2024�N�R��13���A�`�h�@�iArtificial Intelligence Act�j�����B�c��ɂ���ď��F���ꂽ�B����A2030�N12��31���܂łɒi�K�I�Ɏ{�s����Ă����B
�`�h�@�́A���X�N�x�[�X�E�A�v���[�`���̂���̂Ƃ��Ēm���Ă���B�����A�`�h�ɂ�郊�X�N���A�@���e�ł��Ȃ����X�N�iunacceptable risk�j�A�A�n�C���X�N�ihigh-risk AI systems�j�A�B����̓��������K�v�ȃ��X�N�ilimited risk AI systems, subject to lighter transparency obligations�j�A�C�ŏ����X�N(minimal risk)�Ƃ����S�i�K�ɕ����A���ꂼ�ꃊ�X�N�ɕ��ނ����V�X�e�����Ƃɋ֎~�����A�v�������Ȃǂ����߂�Ƃ������@�ł���B
�����āA�u�s����c�߂���A���Ɋ�Â����ӎv����ˁA�d��Ȕ�Q�������炷�v���̂͋��e�ł��Ȃ����X�N�Ƃ���Ă���B�d�t�ɂ����ẮA�`�h���A���������댯���y�ڂ����Ƃ���������ƔF������Ă���̂ł���B
�܂��A�u���̔F�f�[�^�Z�b�g����A�@�����̍�������(�l��A�����I�ӌ��A�J���g���ւ̉����A�@���I�܂��͓N�w�I�M�O�A�������A�܂��͐��I�w��)�𐄑�����v���Ƃ�A�u�Љ�I�X�R�A�����O�v�A�u�v���t�@�C�����O�܂��͐��i�����݂̂Ɋ�Â��Čl���ƍ߂�Ƃ����X�N��]�����邱�Ɓv�Ȃǂ��A���e�ł��Ȃ����X�N�Ƃ���Ă���A�v���t�@�C�����O�Ƃ����ϓ_������`�h�̊댯�����x�����Ă��邱�Ƃ�������B
�ł́A���������K���̍���ɂ�����͉̂����B
�`�h�@���A��P���̖ړI�ɂ����āA�u�c�c�d�t��{�����͂ɋK�肳��Ă��閯���`���܂ފ�{�I�Ȍ����c�c���A�d�t�̈���ɂ����āA�`�h�V�X�e���̗L�Q�ȉe�����獂�x�ɕی삷�邱�Ƃ��m�ہv�Əq�ׂĂ���Ƃ���A�`�h�@�́A��{����ی삷�邽�߂̋K���Ȃ̂ł���B
�R�{���F�����́A�`�h�@�����������o�܂�A���̋K����e�܂��A�`�h�@���̗p���郊�X�N�x�[�X�E�A�v���[�`�ɂ�����u���X�N�v�Ƃ́A�u�i�d�t�j��{�����͂ɋK�肳�ꂽ��{���ɑ��郊�X�N�ł���v�Əq�ׁA�f�c�o�q�A�`�h�@���܂ނd�t�̂`�h�@���́A�u��{�����͂��ۏႷ���{�����������邽�߂̌��@��̉��@�Ƃ��Ă̐��i��L���Ă���v�Əq�ׂĂ���B
�i�Q�j�č��̋K��
�č��́A2023�N10���ɂ`�h�̈��S�ȊJ���Ɨ��p�Ɋւ���哝�̗߂o�����B
�哝�̗߂́A�ړI�̍��ɂ����āA�u�ӔC����`�h�̎g�p�́A�������̐��E�����L���ŁA���Y�I�ŁA�v�V�I�ŁA���S�Ȃ��̂ɂ��Ȃ���A�����������ۑ�̉����ɖ𗧂\�����߂Ă���B�����ɁA���ӔC�Ȏg�p�́A���\�A���ʁA�Ό��A�U���Ȃǂ̎Љ�I���Q������������\��������B�v�Əq�ׁA�u�`�h��P�̂��߂Ɋ��p���A���̖����̃����b�g����������ɂ́A���̑傫�ȃ��X�N���y������K�v������B�v�Əq�ׂĂ���B
�܂�A�`�h�������炷���v�����邽�߁A�`�h�̖��ӔC�Ȏg�p�ɂ�郊�X�N���y�����邱�Ƃ��K�v�ł���Ƃ������ꂪ������Ă�����̂Ǝv����B
�哝�̗߂Ɋ�Â��{��ł́A�����Ȃ����S�I�Ȗ������ʂ����Ă���B���Ȃ́A�`�h���f�����J�������Ƃɑ��A�`�h�V�X�e������L�Q�܂��͍��ʓI�ȏo�͂Ȃǂ��Ȃ���Ȃ����Ƃ������ׂ�Ǝ㐫�������邽�߂̃e�X�g��Ɓi�u�`�h���b�h�e�B�[�~���O(AI red-teaming)�v�ƌĂ��B�j���s�����Ƃ����߂Ă���B
�o�C�f�������́A�哝�̗߂ɉ������K�����������Ă������߂̗��@�[�u���������A�c�_���Ă��邪�A�����_�ł͖��������������̂͂Ȃ��悤�ł���B
�������A���@������Ă��Ȃ�����Ƃ����Ă`�h�̊J���◘�p�����u����Ă����ł͂Ȃ��A����ҕی�⋣�������S���A�M����ψ���i�e�s�b�j�́A�����̌����Ɋ�Â��A�`�h�̗��p�Ɋւ��āA���ʂ�Ό��A�֑��`�A�f�B�[�v�t�F�C�N�ɂ�鍼�\�A�s�����ȋ����A�v���C�o�V�[�N�Q�Ȃǂ̎����܂�ɓ����Ă���悤���B
�i�R�j���A�̓���
���A����́A2024�N�R��21���A�l�H�m�\�i�`�h�j�̊J���◘�p�ȂǂɊւ��錈�c�Ă��̑������B
���c�ẮA�r�c�f���̊��S�Ȏ����Ɍ������i�W���������邽�߂ɁA���S�A���S�A�M���ł���l�H�m�\�V�X�e���𑣐i���邽�߁A �u�l���Ɗ�{�I���R�́A�l�H�m�\�V�X�e���̃��C�t�T�C�N���S�̂�ʂ��đ��d����A�ی삳��A���i�����Ƃ������Ƃ��m�F���A���ׂẲ���������ъW�҂ɑ��āA���ېl���@�ɏ������ĉ^�p���邱�Ƃ��s�\�Ȑl�H�m�\�V�X�e���̎g�p�A�܂��͐l���A���ɐƎ�ȏ��ɂ���l�̐l���A�̋���ɉߓx�̃��X�N�������炷�l�H�m�\�V�X�e���̎g�p�����l�܂��͒�~����悤���߂�A���� �Ǝ�ȏɂ���l�X�́A�l�H�m�\�̃��C�t�T�C�N���S�̂��܂߂�B�����āA�I�t���C�����Ől�X���L����̂Ɠ����������I�����C�����ł��ی삳���K�v�����邱�Ƃ��Ċm�F����B�v�ƌ��c�����B
���̌��c�Ă͕č����哱�������̂ł���A�`�h�V�X�e�����A�r�c�f���̒B���Ɋ�^�����邽�߂ɂ́A���S�ŁA���S�A�M���ł���`�h�V�X�e���Ɋւ���K�������K�v�ł���Ƃ����X�^���X�ɗ����Ă�����̂Ǝv����B
�i�S�j���{�̌���
���{�ł́A2024�N�S��19���ɑ����ȁA�o�ώY�ƏȂ��A�`�h�J���E�E���p�ɂ������ĕK�v�Ȏ�g�ɂ��Ă̊�{�I�ȍl�������������̂Ƃ��āA�u�`�h���Ǝ҃K�C�h���C���v�i��1.0�Łj�����\�����B
���K�C�h���C���́A�`�h�̊��p�ɔ����Đ����郊�X�N�̑傫���ɑΉ����đ���{�����X�N�x�[�X�E�A�v���[�`���̗p���Ă���A���Ǝ҂ɁA�`�h�̈��S���S�Ȋ��p��}�邽�߂̎w�j��^������̂ł���A�����`�h�ɂ���Ă����炳��郊�X�N�ɂ����ӂ��Ă���B
���K�C�h���C���́A��{���O�Ƃ��āA�u�l�Ԓ��S�̂`�h�Љ���v���f���Ă���A��̓I�ɂ́A
�@�@�l�Ԃ̑��������d�����Љ�
�A�@���l�Ȕw�i�����l�X�����l�ȍK����Nj��ł���Љ�
�B�@�����\�ȎЉ�
���R�̒��Ƃ��Ď����Ă���B
�u�l�Ԓ��S�v�Ƃ����_�ɂ��āA���K�C�h���C���́A�u���Ȃ��Ƃ����@���ۏႷ�閔�͍��ۓI�ɔF�߂�ꂽ�l����N�����Ƃ��Ȃ��悤�ɂ��ׂ��ł���v�Əq�ׂ�ƂƂ��ɁA�l�Ԃ̑����y�ьl�̎����A�`�h�ɂ��ӎv����E����̑��쓙�ւ̗��ӁA�U��ւ̑�ȂǂU�̃|�C���g���q�ׂ���ŁA���ʂ̎w�j�Ƃ��āA���S���A�������A�v���C�o�V�[�ی�A�Z�L�����e�B�m�ہA�������A�A�J�E���^�r���e�B�A����E���e���V�[�A���������m�ہA�C�m�x�[�V�����Ȃǂ��f����B
��L�K�C�h���C��������ƁA�d�t�Ōf����l���ւ̔z���܂��Ȃ���A�č��̋K���̂悤�ɁA�`�h�̗����p��}�邽�߂Ɉ��S�������m�ۂ��ׂ��ł���Ƃ̊ϓ_���܂܂�Ă�����̂Ǝv����B����ɂ́A����E���e���V�[�Ȃǂ̑��ʂɂ����y���Ă���_�������ƌ�����B
���{�̃K�C�h���C���ɑ��āA�R�{���F�����́A�u�`�h���p�ɑ��Ă������I������������ɂ́A�K�C�h���C���ł͂Ȃ��A�`�h�K���̊�{�I�g�g�݂��߂�@���𐧒肵�A���̒��Ɍ��@���{�I�l���Ƃ̊W�����������菑�����ނ��ƂŁA�`�h�@���Ɍ��@��̉��@�Ƃ��Ă̖��m�Ȉʒu�Â���^����ׂ��ł���B�v�i�u�`�h�Ɩ@�v���R�Ɛ��`2024�N�U�����j�Əq�ׂ�B�K�C�h���C���́A�����܂ł��w�j�ł��邽�߁A�R�{�����̏q�ׂ�悤�A����A�@�������}����ׂ��ł��낤�B
�i�T�j���߂���K���̕�����
�`�h�ɑ��ĂȂ�炩�̋K�����K�v�ł���Ƃ����͍̂��ۓI�ɋ��ʂ̕������ł���Ǝv����B���݂́A�d�t�A�č��Ȃǂ��ʂɂ`�h�̋K�����������Ă���ł��邪�A�C���^�[�l�b�g���O���[�o���Ȃ��̂ł���ȏ�A�`�h�̋K�������ۓI�Ȃ��̂ƂȂ�ׂ��ł��낤�B
�ł́A�Ȃ��A�`�h���K������̂��B��͂肻�̍����ƂȂ�̂͌��@��̗��O�A�l���ł͂Ȃ��낤���B
�d�t���l���ۏ��O�ʂɏo���Ă���̂ɑ��A�č��́A�`�h�������炷���v�����邽�߁A�`�h�̖��ӔC�Ȏg�p�ɂ�郊�X�N���y������Ƃ����p����ł��o���Ă��邪�A�����ɂ�����u���X�N�v�́A�`�h�ɂ��L�Q�܂��͍��ʓI�ȏo�͂̉\�����w���Ă��邩��A��͂�l�����l���������̂ł���Ƃ�����B���{�̋K���ɂ����Ă��A�l�Ԓ��S�Ƃ�����{�p���ɂ����āA�l���ւ̔z�������Ă���B
�����āA�K���̍��������@�Ɋ�Â��l���ł���̂Ȃ�A��͂肻�̋K���́A�@�Ɋ�Â��ĂȂ����ׂ��Ǝv����B�`�h�̊��p�ɂ����Ă����炳���l�X�ȃ��X�N�́A��Ɍ��������Ƃ���A�����͌��@13���́u�l�̑����v�ɑ���댯�ɂ���悤�Ɏv����B�`�h�ƑΛ������X�́A�`�h�ɂ���āu�l�̑����v����������Ȃ��悤�ɂ��邽�߂̕�����l���Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ł��낤�B
�S�@�`�h�����p�����u�f�W�^�������`�v�̉\��
�����܂ŁA�`�h���A���@��̗��O�A�l���̊ϓ_����A�ᔻ�I�Ɍ��ߒ����Ă������A����ŁA�`�h�����p�����u�f�W�^�������`�v������Ă���B
2024�N�V���̓����s�m���I�ɏo�n�����`�h�G���W�j�A�̈���M�����́A���̑I����ɂ����āA�x���҂Ƃ̋c�_�܂����u����̍X�V�v�����݂��B�C���^�[�l�b�g�Ō�������\������A�x���҂̎���A�R�����g�Ȃǂ͂��A����ɔ��f������̂ł���B���f�����邩�́A�������Ŕ��f����̂ł͂Ȃ��B�s���ł���A�����ł����Ă�������������ɔ��f������B�ʏ�A�I����ł̌���́A���҂���x���҂ւ̈���ʍs�ƂȂ邱�Ƃ��������A���쎁�̏ꍇ�́A�x���҂̐����z�����Č���������̂��B
���쎁�ɂ��`�h�̊��p�́A�V�����I���^���Ƃ��������ł͂Ȃ��B����ɑ��Ċ�ꂽ�x���҂̃R�����g���A�u���Ӂv�Ƒ�����A�����ōs��ꂽ���Ƃ́A�܂��������ӂ����W���A����Ƃ�������ɔ��f�����邱�ƁA�������ӂ̓����Ȃ̂ł���B���ɂ݂Ă����Ƃ���A���̎��W�̓f�W�^���̓��ӕ���ł���B�����āA���W�������̕��́A�������f�W�^���̓��ӕ���ł���B�u���ӂ��s���ɂ����ɔ��f�����邩�v�Ƃ������_�ł`�h�����p����A����ւ̊֗^�́A�����Ƃ����̂��̂ł͂Ȃ��Ȃ�A��葽���̖��ӂ��L���ׂ��ɔ��f��������̗��Ă����邱�Ƃ��\�ƂȂ�ł��낤�B�܂��A��l��l�̖��ӂ�����ɔ��f�����\�������܂�A�s���̐����Q���ւ̈ӗ~�����߂�Ƃ��������I���ʂ������邩������Ȃ��B������w�̉F��d�K�����i�����w�j���A�s���F���������������Ƃ��đ����邱�Ƃɂ�萭����ς�����\�����߂����̂Ƃ��āA���쎁�̎��݂������]�����Ă���B
���̂悤�ɂ`�h�̊��p�ɂ́A�u�f�W�^�������`�v�Ƃ������ׂ��A�V���������`�����S�ɔ��W������\������߂��Ă���悤�Ɏv����B�`�h�́A��X�̎Y�Ƃɂ����ėL�p�ȃV�X�e���Ƃ��Ċ��p����Ă��邪�A���ꂾ���ł͂Ȃ��A�����`�Ƃ����ϓ_�ɂ����Ă��傫�ȉ\�����߂��c�[���ł���ƍl������B
�����Ƃ��A���ł͂܂��A�����������p�����ݎn�߂�ꂽ�i�K�ɉ߂����A�u�f�W�^�������`�v�������Ɏ��������ƍl����̂͑��v�ł��낤�B�`�h������ɖ��ӂf������ꏕ�ɂȂ蓾��Ƃ͂����A�`�h������̗��Ď�̂ƂȂ��Ă��܂��ẮA������u�����`�v�ƌĂ�ŗǂ����̂��^���������B�����Ȃ�Ȃ��悤�ŏI�I�Ȍ��f�͐����Ɩ��͎s�����s���Ƃ������Ƃɂ��Ă��A�`�h�����Ă�������ɁA�����Ɩ��͎s�����A���_���鍪������������̂��Ƃ������������悤�B
�T�@���A�������ɋ��߂��邱��
�i�P�j�`�h�ւ̑Ώ��̕K�v��
�����܂ł݂Ă����Ƃ���A�`�h�́A�l�X�Ȍ��@��̗��O��l���ɉe����^���A�Љ�̐��̊�Ղ�h�邪�����˂Ȃ��댯����s��ł������A�`�h�́A���܂�ɂ��[�����B�̐����ɍ������낵�Ă���A���͂⊮�S�ɂ`�h��r�����邱�Ƃ͍���ł��邾���łȂ��A���̗L�p�����l����Ɣr�����邱�Ƃ��K�Ƃ������Ȃ��B�`�h�́A�Y�ƊE�͂������s���̕���ɂ����Ă��A��Ƃ̌������Ɏ�����c�[���ƂȂ�A�Ƃ�킯�����`�h�͗l�X�ȕ���ɂ����ċƖ��������̂��߂Ɏ���������邱�Ƃ͎��m�̂Ƃ���ł���B�܂��A�u�f�W�^�������`�v�Ƃ����s���F�������ɎQ���ł���V���Ȗ����`������������傫�ȉ\�����߂����̂ł��邱�Ƃ���ɏЉ���B�������A���݂��A�`�h�̎Љ�I�L�p�����F�m����A���̊��S�Ȕr�����s�\���s�K�ł�����`�h����ƌĂׂ鎞��ł��邩�炱���A�`�h�́A���u����A���B�̓��퐶���̂�����g�߂ȏ�ʂɐZ�����A�l�����������댯���܂��܂��������Ă���ƂȂ�̂͊ԈႢ�Ȃ��B
���̏��ʼn߂����ɂ͂����Ȃ��B�`�h�ɂ��ẮA�����p��}��Ȃ�����A���̋��Ђ��\���ɗ������A���@��̗��O��l�����������Ȃ����߂̋K�����A�Z�p�ʁA���x�ʂ̗��ʂ���͍�����K�v������Ƃ�����B
�܂��A�`�h�ɂ�鋺�Ђ��\���ɗ������A�^��������ɑ��ēK�Ȕᔻ�v�l�i���e���V�[�j�������A�l���𓊂��o���Ȃ��s�����琬���A�f�W�^�������ɂ����Ď��������s������Ȃ�Љ���\�z���邱�Ƃ��K�v�ł���B
�i�Q�j�`�h�Ɋւ���K���̂����
�`�h�Ɋւ���Z�p�ʂł̑�Ƃ��ẮA�Ⴆ�A�C���^�[�l�b�g��̏��ɂ��̏�M�҂̎��ʏ���t�^���Ă��̏��ɐG���҂����̐M�������m�F���₷������Z�p�i�I���W�l�[�^�[�E�v���t�@�C���j��A�����̃A���S���Y���������������̂`�h������I�ɑ��݂��A�l�����ꂼ��̂`�h�������I�ɔ�r�A�I���ł��������A�P��̂`�h�������炷���̕�����悤�Ƃ���\�z�i�`�h�R���X�e���[�V�����j�Ȃǂ�����Ă���B
�K���Ƃ��ẮA�f�W�^������ł̋Z�p�i�W�̑����ɐv���ɑΉ��ł���K�C�h���C�����ɂ�����\�t�g�ȋK���ƁA���ɐ[���Ȑl���N�Q�A�����`�ւ̊�@�̖�肪���O����镪�쓙�ɂ����闧�@�[�u�ɂ��n�[�h�ȋK�����g��������K�v������B�܂��A�c�o�e���Ǝғ��ɁA���m����̏��Ȃ��������C���Z���e�B�u��^����Ƃ����Ӗ��ł́A�l�̎��ȏ��R���g���[�����̌����ȔF�m�Ƃ��̎������̂��߂̗��@�[�u��A���쌠���̒m�I���Y���̕ی십���[�u�����A�`�h�ƃA�e���V�����G�R�m�~�[�����т����Ƃɂ��\����H���~�߂�S�ۂƂ��ėL���ƍl������B
����ŁA�`�h���͂��߂Ƃ���f�W�^���Z�p�̗L�p���₻��𗘗p���鑤�̗��v�����l�����A�s���߂����K�����Ȃ���Ȃ��悤�ɔz������K�v�����邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B
�e��ʂɂ����Ă����Ȃ�K�����K���ɂ��ẮA��q�����l�̐l���A�����`�ւ̊�@��I�m�ɗ������A�f�W�^���Z�p�𗘗p���鑤�̗��v�ɂ��ڔz������o�����X���o�����������K�v�ł���B
�i�R�j�ٌ�m�ɋ��߂��鎋�_
�f�W�^���Z�p�̋}���Ȑi�W�ɔ����A�V���Ȍ��@��̊�@�������Ă���Ƃ����錻�݁A�L���Ō��S�ȃf�W�^���Љ��z�����߂ɉ�X�ٌ�m���ϋɓI�Ȉӌ��\�����Ȃ������ʂ͑����͂��ł���B
��X�ٌ�m�́A�`�h���܂ރf�W�^���Z�p���A�l���ɂǂ̂悤�ȉe����^������̂��Ƃ����ϓ_�Ŕᔻ�I�ɖڂ����点�Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���Ƀf�W�^���Z�p�͋}���ɐi�����邩��A�Z�p���i�����������̎p���������A�l���N�Q�������Ȃ��悤�A�i���̕��������R���g���[�����铭���������K�v�ƂȂ낤�B
�܂��Y��ĂȂ�Ȃ��̂́A�`�h����ʂɎ��W�����f�[�^�Ɋ�Â��ĉ�͂��s���Ƃ����_�ł���B�܂�A�`�h�́A���̒��́u�����v�ɐe�a�I�ȋZ�p�Ȃ̂ł���B��{�I�l���̗i����g���Ƃ����X�Ƃ��ẮA��ɏ����h�̐l����ی삷��Ƃ������_�ŁA�`�h�ɑ���K���̂�������������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�i�S�j�s������̕K�v��
���݂̃f�W�^���Љ�̊����ł́A���K�Ƀf�W�^���Z�p����g���Ă���s���́A�C�Â��Ȃ������Ɏ���̐l������@�ɂ��炳��Ă���Ƃ�������B���̂悤�Ȏs���ɑ��A���̂悤�Ȍ���𐳊m�ɓ`���Ă������Ƃ��܂��A��X�ٌ�m�̎g���Ƃ�����B
���ɁA�A�e���V�����G�R�m�~�[�̉��ŁA�s���ɒ������ɂ��̂܂ɂ��肪�����Ă�����A�����`�h�ɂ��{���炵���t�F�C�N����������肵�Ă��邱�ƂȂǂɂ���āA���������ɐڂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A�s���̐l���́A�傫�Ȋ댯�ɂ��炳��邱�ƂɂȂ�B
�R�{���F�����́A����ێ悷��s����H���ɂ��Ƃ��A���ɐG���҂��K�x�ȃo�����X���ӎ����A���l�ȏ��ɐڂ��邱�ƂŋU���ւ̑ϐ���{���v���W�F�N�g�Ƃ��āu���I���N�v�̊T�O�����Ă���B��X�ٌ�m���܂��A���́u���I���N�v�̊T�O�Ɏ^�����A���Ē�������Љ�ɎU������U���ɘf�킳��Ȃ����������s���̈琬�Ɏ��g��ł����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���ɁA�����A���k�ւ̋�����d�v�ł���B2019�N12���ɕ����Ȋw�Ȃ����\����������v�ĂƂ��Ă̂f�h�f�`�X�N�[���\�z�iGlobal and Innovation Gateway for All�A�u���ׂĂ̎����E���k�ɃO���[�o���Ŋv�V�I�Ȕ����v�j�̂��ƁA������l������ɒ[����t�^���ăf�W�^���Љ�ɉ�����������s�����Ƃ��Ă��鍡���ɂ����ẮA�����A���k�ւ̓K�ȃf�W�^�����e���V�[����͌������Ȃ��Ǝv����B
�f�W�^���Љ�ɂ�����s���̃��e���V�[����Ƃ��ẮA���\�N�O�������Ă����u���������v�ɉ����A�����ł́u�f�W�^���V�e�B�Y���V�b�v����v�Ƃ����T�O�������悤�ɂȂ��Ă��Ă���B
���̊e�T�O�ɂ��Ă͍L����������̂́A�T�ˁA�u�댯�ȏ�牓������v�Ƃ������z�����������Ă̋��炩��A�u�f�W�^���Z�p�̐��m�Ȏd�g�݂�`���邱�Ƃɂ��A�×����鑽�l�ȏ��ւ̑I��\�́A�ϐ�����g�ɂ������A���ꂩ��̃f�W�^���Љ�ɂ����閯���`��S�����������s�����琬����v�Ƃ�������փV�t�g���Ă�����̂ƍl���邱�Ƃ��ł���B���́u�f�W�^���V�e�B�Y���V�b�v����v�́A�e��w�p�@�ւ⋳��@�֓��ɂ����Ď��H�������A����܂��܂��g������݂��邱�Ƃ��\�z�����B
��X�ٌ�m�́A�s���ւ̖@�����S�����̂Ƃ��āA�w�Z����ւ̔h�����Ƃ⎙���A���k��ΏۂƂ����I�[�v�����ƁA����҂Ƃ��Ă̎Љ�Q��𑣂�����Ҏs������̎��H�Ȃǂ�ʂ��A�܂��A�s���W���V���|�W�E���̎�Ó��Ŗ���N�ƌ����̏����邱�ƂȂǂ�ʂ��āA��L�̋���E�ɂ�����V���Ȓm����������A�K�ȃf�W�^�����e���V�[���������鋳��̏����Ă����ׂ��ł���B
�U�@����
�ȏ�܂��A�����ٌ�m��A����́A����A�Љ�ɂ����Ă`�h�̗����p�����i����Ă����ɂ�����A�����Љ�݂̂Ȃ炸�A�T�C�o�[��ԏ�ɂ����Ă����@��̊�{�I�l�����i�삳��邱�Ƃ�ڎw�������ƍl����B�����āA�`�h�̃����b�g�����Ȃ�����A�S�Ă̌l���`�h�ɂ���Ĉӎv�����c�߂��邱�ƂȂ��A�����I�Ɏ��Ȍ�����Ȃ����Ƃ��ł��閯���`�Љ�������������ƍl����B���̂��߂ɂ́A�`�h�ɗ������̂ł͂Ȃ��A��X���A�f�W�^���Z�p�A���ɂ`�h���A�l���̊ϓ_����ᔻ�I�Ɍ��߁A�l�Ƃ��Ď����I�ɂ����𗘊��p���Ă����K�v������̂ł���B
���̂悤�ȎЉ���������邽�߁A���A����́A�ȉ��̊��������邱�Ƃ�錾����B
�i�P�j�`�h�̋}���Ȕ��W�A���p�̏�̊g�哙�A����܂��܂��i�W���Ă����f�W�^�����ɂ����āA�`�h�̗����p��}��Ȃ�����A���@��̗��O��l���ɑ��鋺�Ђ��\���ɗ������A���\���ꂽ�K�C�h���C�����̑��̕���ɂ��Đl���̊ϓ_���猟�������P���ׂ��_���w�E���铙�A�`�h�ɑ���K�ȋK���̎����Ɍ������𑱂��邱�ƁB
���̂悤�ȎЉ���������邽�߁A���A����́A�ȉ��̊��������邱�Ƃ�錾����B
�i�Q�j�`�h���܂ރf�W�^���Z�p�ɂ���Ă����炳��錻�y�я����̐l���N�Q�A���ɏ����h�ɑ���l���N�Q�ɑ��Ėڂ����点�A���̖h�~����ы~�ς̂��߂̊����Ɉ��������͂����Ă������ƁB
�i�R�j�������Ȃ��f�W�^���Љ�̐i�W�܂��A�s���ɑ��ăf�W�^���Z�p�ɂ��댯���܂߂Đ��m�Ȓm����`���A���Ē�������Љ�ɎU������U���ɘf�킳��Ȃ����������s���̈琬�Ɋ�^���鋳��̐��i�ɋ��͂��邱�ƁB
�ȏ�