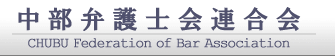現在、法務省の法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会において、少年法における「少年」の年齢を20歳未満から18歳未満に引き下げることが検討されている。
しかし、当連合会の「少年法の適用年齢引下げに反対する理事長声明」(2015年8月31日)のとおり、少年法の適用年齢を引き下げることは、18歳、19歳の少年から、立ち直りに向けての社会的支援を受ける機会を奪うことを意味する。その結果、とりわけ自立への温かく手厚い支援の必要性が高い時期である18歳、19歳の少年が、単に非行の結果責任を問われることにより自己評価を一層低下させ、また、社会的支援を活用する機会を失わしめ、社会的孤立が深刻化することにより再犯リスクが高まるおそれが大きくなる。それは、再犯防止の観点から有益な策ではないことはもちろん、無謀な逆効果となることは明白である。
そこで、以下のとおり決議する。
少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げることに改めて反対する。
2019年(令和元年)10月18日
中部弁護士会連合会
提 案 理 由
第1 はじめに
少年法では、「20歳に満たない者」を少年と定義し、少年法の適用対象としている。
ところが近時、公職選挙法、民法の分野で成年年齢引下げが順次実施され、それを契機に少年法についても適用年齢を引き下げる議論がなされるようになった。そして現在、法制審議会においては、仮に少年法の適用年齢を18歳未満とした場合に採り得る刑事政策的対応を含めた犯罪者処遇策が検討されている。
しかし、いかに代替的な刑事政策的対応がなされようとも、少年法の適用年齢引下げは合理的理由を欠くものであって是認しがたい。
そのため、当連合会では2015年8月31日に適用年齢引下げに反対する理事長声明を出し、その後も日本弁護士連合会ほか、各単位会でも適用年齢引下げに反対する意見書、声明が出されているが、こうした声を無視するかのように法改正に向けた動きが加速しつつあるという憂うべき状況となっている。
そこで、適用年齢引下げの問題性を明らかにし、法の改悪を阻止するため、以下に述べる理由から、改めて引下げ反対の決議を求める。
第2 保護処分優先主義、個別処遇原理の持つ意義
1 わが国の少年法は、「少年の健全な育成」を目的として掲げ(少年法1条)、すべての少年事件を家庭裁判所に送致し(全件送致主義)、非行に陥った少年を教育、治療、環境調整によって更生させ、円滑に社会復帰できるようにする保護処分優先主義を採用している。その根拠は、少年はいまだ心身の発達が十分ではなく、生育環境や交友関係等の外部的条件の影響を受けて非行に至る部分が多いため、少年の可塑性に期待をして、刑罰を科すよりもむしろ教育的な処遇をはかることが少年の更生に資するという点にある。
そして、保護処分優先主義を採用した論理的帰結として、個々の少年ごとにいかなる更生方法が妥当であるのか探ることが求められ、少年の性格や成育環境等の千差万別な非行原因に目を向け、その原因を除去するために、それぞれの少年のために求められるものは何かを検証・実践する個別処遇が基本原理となる。
この個別処遇を支えているのが家庭裁判所の専門的調査(少年法9条)である。この調査は、単に非行の結果の外形的軽重のみに着目するのではなく、少年の成育環境や家庭環境、非行時の精神状態や心理状態等の調査に基づいて少年を理解し、非行の原因や背景を解明することにより科学的合理的根拠のある個別処遇を可能ならしめている。
そして、この一連の過程においては、少年非行を、子どもの生育過程に生じた問題であると観る「非行観」に立った上で、非行に至った少年が、虐待、いじめ、その他さまざまな不適切な扱いを受けたものでもあるという側面に着目し、その成長発達の権利を保障する教育、治療、環境調整を行うという司法のソーシャルワーク機能が重視される。
このように、わが国の少年法制は、少年の成長発達権を保障し、教育的福祉的援助を通じて一人ひとりの少年の主体的更生をめざし、もって、少年が社会の一員として建設的な役割を担えるようにして、社会への参加を促すものであって、近代民主主義社会の要請に応じるものである1。
2 こうした少年法制のもとで、これまで一人ひとりの少年に合った処遇が選択されたことにより、現実に、少年非行が減少するという効果が得られている。
すなわち、少年非行の検挙者数は、1983年のピーク時には31万7438人であったものが、2017年には5万209人と84.2%減少している。また、少年人口あたりの発生数で比べても、2017年には最も人口比の高かった1981年の5分の1となっている2。さらに、殺人(未遂を含む)と傷害致死の合計も、1961年のピーク時に比べると89.7%(少年人口あたりの発生数でも83.8%)も減少している3。加えて、2013年(平成25年)出所から2016年までの4年内刑務所再入率は、26歳未満出所者で29.9%に上るのに対し4、18歳以上の少年院出院者による再入率は12.0%と有意な差がある5。
このように、適用年齢引下げに賛成する論調がその根拠とする「少年事件の増加・凶悪化」とはまさに逆の現象が起きているのである。
こうした事実からも、現在の少年法制における保護処分優先主義、個別処遇原理の有用性は明らかなところである。
第3 適用年齢引下げに合理的根拠はないこと
1 少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げると、18歳、19歳の少年(以下、「年長少年」という)は、少年法制による保護処分優先主義、個別処遇原理による教育、治療、環境調整を受けることができなくなる。現在、家庭裁判所で扱われる少年事件の約5割が年長少年で占められている6ことからすれば、その影響は極めて大きい。
このように年長少年について保護処分優先主義を放棄することには、以下に述べるように何ら合理性がない。
2 年長少年にとっての教育的処遇の必要性
年長少年といえどもいまだ年若く、環境等の周囲の影響を受けやすいことはそれ以外の少年と同じであって、仮に犯罪行為に至ったとしても教育的処遇こそが更生に資することは異ならない。
それゆえ、年長少年とそれ以外の少年を区別する理由は何もなく、むしろ、非行の問題を抱える少年の実情を考えると、これから社会に巣立とうとする年長少年に対してこそ、教育的処遇が重要な意味を持つ。
すなわち、調査によれば、少年院収容者のうち、家庭等で虐待被害を受けた少年は60.1%に及び、特に女子少年では70%を超えるとされている7。少年院収容者のうち18歳以上の年長少年の占める割合は2016年で約47.56%を占めており8、その中に虐待被害を受けて深い心的外傷を抱えた少年が多く含まれていることは明らかである。
こうした心的外傷による苦悩は年齢によって異なるものではないが、これから社会に出て他者との深い関わりを持とうとする年長少年にとっては、一つの超えるべき課題として切実な問題となって目前に迫ってくる。このような年長少年の心の傷に向き合い、癒すことは、刑罰主義では到底困難であって、現在の少年法制のもとでの保護処分優先主義、個別処遇原理に基づく教育的処遇こそがふさわしい。
また、少年院収容者のうち5〜8割の少年に発達障害的特徴が存在することが指摘されている9。
児童精神医学の分野においては、子どもの発達障害、さまざまな精神障害に関する理解と教育の手法または治療に関する研究は、現在飛躍的に発展してきており、こうした児童精神医学の研究結果などを前提として、少年院においては、家庭裁判所の科学的調査や精神鑑定の結果を踏まえて少年を理解し、適切な教育と支援を行ってきた実績が蓄積されつつある。かかる特性を考慮した特別な配慮に基づく教育と支援が年長少年にも必要であることは論を待たない。
3 専門的見地からの指摘
こうした年長少年への保護処分優先主義、個別処遇原理に基づく教育的処遇の必要性・有用性は、専門的見地からも明らかとなっている。 すなわち、日本児童青年精神医学会は、少年非行の現在の問題状況を踏まえて、2016年に少年法適用年齢引下げ案に反対し、少年法適用年齢はむしろ引き上げるべきであるとの声明を発している。
さらに、近時、脳神経科学や心理学、精神医学の知見を受けて、思春期から20歳半ばにかけて脳の構造自体の変化が高まるとの指摘がなされ、特別な配慮を要すると考えられるようになっており、諸外国では司法制度の見直しが行われてきている10。
これらは、生育過程でさまざまなハンディにより成長発達を妨げられ、社会に適応しづらく、生きづらさを抱える若者の現実を理解した専門家の意見として傾聴すべきである。そして、子どもの成長発達に関する前記のような科学的知見に基づく治療や福祉的ソーシャルワークの支援により現実に少年非行が防止され、再犯が防止されている可能性にも着目すべきである。
4 小括
以上のとおり、年長少年への個別的専門的処遇を困難にする少年法の適用年齢引下げは、年長少年の立ち直りを阻害することになりかねず、さらには専門的知見に基づく意見も軽視するものであり、到底是認できるものではない。
第4 適用年齢引下げの論拠の問題性
これに対し、適用年齢引下げを積極的に進める考えからその論拠が提示されているが、以下のとおり、そのいずれもが合理性がないものである。
1 他の法令との統一性の問題
適用年齢引下げに働く方向での議論として、前述した公職選挙法、民法の成年年齢と統一することが、「法体系として望ましく分かりやすい」との意見がある。
しかし、法律の適用年齢は、法律ごとの趣旨や目的に基づき定めるべきものである。
そのため、民法の中でも、遺言や養子縁組の承諾は15歳からできるとされているし、選挙権年齢は若者の政治参加の保障という観点を考慮する必要があるなど、内容に応じて適用年齢は分けられているのが実情である。
これに対し、少年法の適用年齢は、少年の立ち直りや再犯防止に有効であるかどうかという観点から考えるべきものである。そして、少年については現行法どおり20歳未満を適用年齢とすることが少年の立ち直りや再犯防止に有効であること、実際に少年事件の減少等の効果も認められていることは前述のとおりである。
したがって、年長少年を少年法の適用対象から除外することによる不利益を無視してまで民法等と成年年齢を合わせる必要はない。
2 少年事件の増加・凶悪化の問題
少年事件の増加・凶悪化という意見がむしろ事実に反していることは、前述のとおりである。
こうした意見は、発達したマスメディアやSNSによる過剰な情報伝達により、従前より個々の事件が過激かつ印象的に流布されていることが背景にあることが推測でき、そこには適用年齢引下げを裏付ける立法事実は存在しない。
3 代替手段の有効性の問題
法制審部会においては、少年法適用年齢引下げに伴い、その代替手段として、年長少年に対しては刑罰を原則とするものの、検察官がこれを不起訴処分とした場合には事件を家庭裁判所に送致して「若年者に対する新たな処分」を行う等の構想が検討されている。
しかし、そもそも年長少年に対しては刑罰を原則とし、起訴された少年については、家庭裁判所の手続ではなく成人と同様の刑事手続がとられるため、起訴された少年の個別の事情に配慮して、将来を見据えた教育的処遇がなされない点で重大な問題がある。
また、起訴・不起訴を検察官が判断する点も問題である。すなわち、検察官の判断においては非行の結果そのものが重視されざるを得ず、家庭裁判所が行うような個別の調査を経ての合理的根拠に基づく処遇選択を期待することができなくなってしまう。例えば、現行の少年法制においては、結果として重大な少年事件であっても、調査の結果により保護処分とすることがその少年の更生に資すると判断されたり、逆に比較的軽微な少年事件でも、調査の結果によりあえて逆送などの重い処分がなされたりすることが可能であるが、そのような個々の少年の実情に応じた判断ができなくなるという弊害が生じる。
さらに、法制審部会が家裁の関与を前提とした代替手段を検討しているのは、従前の少年法制における家裁の保護的機能を評価しているからに他ならないが、こうした代替手段では現在の有用な保護的機能を後退させることになってしまい、家裁が関与する意味も失われることになる。
結局のところ、代替手段はどこまでいっても代替手段でしかなく、前述のように有用な現行制度を超えるものではない。
そもそも、少年法適用年齢を引き下げなければ代替手段を検討する必要もないのであり、代替手段は、適用年齢引下げという結論ありきで生じる議論である。
それゆえ、代替手段の内容により適用年齢引下げの可否を検討するのではなく、前提として本当に適用年齢引下げをする必要があるのかを子細に検討しなければならないが、引下げの必要性がないことは前述のとおりである。
第5 おわりに
これまで70年にわたるわが国の少年法制の運用は、家庭裁判所などの関係機関のみならず、補導委託先など多くの市民の自発的協力と援助によって支えられてきた。そして、その温かな人の輪に出会って自立更生の道を歩むことができた少年は数知れず存在する。わが国の少年法制は、そのようにして市民に支えられ、子ども、若者の育ちを支えあう文化の中で運用されてきた。非行や非行のくり返しから子どもを守ることは、国、社会の責任であるという思想と文化がある。年長少年を少年法から除外する改正論は、非行防止対策として有害無益であるのみならず、少年法制の運用によって培われ、少年の更生を基盤として熟成したわが国の少年処遇のあり方を打ち壊してしまうことになるのではないかと大きな疑問がある。
以上から、当連合会はここに決議する次第である。
以上
1 児童の権利に関する条約40条1項「締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定されたすべての児童……の年齢を考慮し、更に、当該児童が社会に復帰し及び社会において建設的な役割を担うことがなるべく促進されることを配慮した方法により取り扱われる権利を認める。」(政府訳(外務省ホームページ))
2 平成30年版犯罪白書 第3編/第1章/第1節/1
3 各年の司法統計年報と総務省統計国の人口推計をもとに作成(日本弁護士連合会「少年法の適用年齢引下げを語る前に」2017年6月改訂版)
4 法務省矯正統計調査「再入受刑者の前刑出所時属性及び犯罪傾向の進度別再入状況」(2016年調査)
5 法務省法務総合研究所研究部報告「青少年の立ち直り(デシスタンス)に関する研究」(2018年3月)によれば、少年院出院時18歳以上の年長少年のうち、再入院したり刑事施設へ入所した者の割合は合計12.0%であった。
6 2018年検察統計 統計表18−00−25
7 富田拓「児童精神医学の観点から『18歳問題』を考える」法政論叢2018年54巻1号247頁
8 少年矯正統計(2016年)少年院別新収容者の年齢
9 十一元三「司法領域における広汎性発達障害の問題」家庭裁判月報第58巻第12号4頁
10 武内謙治「少年法日独比較:『適用年齢引下げ』について考える」世界の児童と母性81巻68頁。前掲富田拓論文280頁以下。