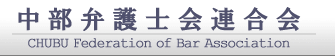�P�@�ƍߔ�Q�ғ���{�@�i�ȉ��u��{�@�v�Ƃ����B�j�̑�R���P���́A��{���O�Ƃ��āu���ׂĔƍߔ�Q�ғ��́A�l�̑������d���A���̑����ɂӂ��킵��������ۏႳ��錠����L����B�v�ƒ�߁A�P�X�W�T�i���a�U�O�j�N�ɍ��A����ō̑����ꂽ���A��Q�Ґl���錾�i�u�ƍ߂���уp���[���p�̔�Q�҂̂��߂̐��`�Ɋւ����{�����錾�v�j�ł́A�ƍߔ�Q�҂̌o�ϓI�⏞���߂Ă���B
�ƍߔ�Q�ɂ��đ��`�I�ӔC���͉̂��Q�҂ł���B�������A��{�@�̑O���ɂ���Ƃ���A���S�ň��S���ĕ�点��Љ���������邱�Ƃ́A�������ׂĂ̊肢�ł���ƂƂ��ɁA���̏d�v�ȐӖ��ł���A�ƍߓ���}�~���A���S�ň��S���ĕ�点��Љ�̎�����}��Ӗ���L�����X���܂��A�ƍߔ�Q�ғ��̐��Ɏ����X���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����ɂ�������炸�A���Ȃ��A�ƍߔ�Q�҂͏\���ȑ��Q�y�ьo�ϓI�⏞���邱�Ƃ��ł����A��{�@�ɒ�߂�ꂽ�ƍߔ�Q�҂Ƃ��Ă̌������N�Q���ꂽ�܂܂̏�Ԃɒu����Ă���̂ł���B
�Q�@���������ƍߔ�Q�҂̑��Q�̎��������m�ۂ��A�\���Ȍo�ϓI�⏞���������邽�߂ɂ́A�����������ォ��A�ƍߔ�Q�҂��@���̐��Ƃł���ٌ�m�Ɉ˗������āA���Q�ґ�����̎��k�̐\�����A���̌�̑��Q���������ɂ��Ă̖@�I�x������K�v������B���̍ۂٌ̕�m��p��i�ה�p�̕��S�̖����������A��Q�҂̌��������������ׂ��ł���
�܂��A���������x���ɂ���Ă����Q���Ȃ������ƍߔ�Q�҂ɑ��āA��{�@��S���Ɋ�Â��āA�ƍߔ�Q�҂̂��߂̎{��𑍍��I�ɍ��肵�A���{����Ӗ��������A�K�ɑ��Q�y�ьo�ϓI�⏞���s���K�v������B
�݂̂Ȃ炸�A��{�@��T���́A�n�������c�̂��ƍߔ�Q�҂̎x���Ɋւ��A���̒n��̏ɉ������{������肵�A���{����Ӗ����߂Ă��邱�Ƃ���A�n�������c�̂��ƍߔ�Q�Ҏx���ɓ����������i������������j�𐧒肵�āA�d�w�I�ɔƍߔ�Q�҂ɑ���o�ϓI�x�����s���Ă������Ƃ��s���ł���B
�R�@�����ŁA���A����́A�ƍߔ�Q�ғ���{�@�̊�{���O�ɂ̂��Ƃ�A�ȉ��́i�P�j�Ȃ����i�R�j�̐��x���̎��������y�ђn�������c�̂ɋ��߂�ƂƂ��ɁA���A����ɏ�������e�P�ʉ�i�S�j�̊������s�����Ƃ�錾����B
�i�P�j�ƍߔ�Q�҂̑��Q�̎������m�ۂɎ����邱�Ƃ���A�����A����ɂ��A�ƍߔ�Q�҂���Q���ォ��ٌ�m�Ɉ˗��ł��鐧�x������ƂƂ��ɁA�ƍߔ�Q�҂̍s�������i�ד��̍ٔ��葱��p�̉������s�����ƁB
�i�Q�j�����A�ƍߔ�Q�҂����Q�y�ьo�ϓI�⏞���錠�����߂��ƍߔ�Q�ғ��⏞�@�𐧒肷�邱�ƁB��̓I�ɂ́A�����A�ƍߔ�Q�҂̗L���鑹�Q�����������̗��֕����x��݂��邱�ƁA�܂��A�ƍߔ�Q�҂����Q�҂ɑ��鑹�Q���������̍����`���擾�ł��Ȃ��ꍇ�ɂ́A���֕����x�Ɠ����̕⏞��ƍߔ�Q�҂ɑ��čs�����ƁA�y�т��̂��߂̍������m�ۂ��A��������ъg�[���邱�ƁB
�i�R�j�n�������c�̂��A�ƍߔ�Q�҂̑��Q�̂��߂̌o�ϓI�x�����s�����ƁA�y�т��̂��߂̍������m�ۂ��A��������ъg�[���邱�ƁB���Ɏs�����͓������𐧒肵�A�ƍߔ�Q�҂̌�����ۏႵ�A���Q�̂��߂̌o�ϓI�x�����s�����ƁB
�i�S�j���Q�̎������m�ۂ��\���ɍs���Ă��Ȃ�������ӂ܂��āA���A����ɏ�������e�P�ʉ�́A�ƍߔ�Q�����Ғc�́A�ƍߔ�Q�Ҏx���c�́A�n�������c�́A�@�֓��ɃA�v���[�`���A�����������A�n�������c�̂���A���Q���������̗��֕����x���܂߂��������̐�������߂銈����ϋɓI�ɍs�����ƁB
�ȏ�
�Q�O�Q�R�N�i�ߘa�T�N�j�P�O���Q�O��
���@���@�ف@��@�m�@��@�A�@���@��
�� �� �� �R
�P�@���Q�҂���̑��Q���������x�����Ă��Ȃ�����
�ƍߔ�Q�ҁi�ȉ��A���ɒf��̂Ȃ�����A��Q�҂��S���Ȃ����ꍇ�̈⑰���܂߂āu�ƍߔ�Q�ҁv�Ƃ����B�j�́A�ƍ߂ɂ���āA���Q�҂���A�����A�g�́A���Y�A���R�y�і��_���̎�X�̖@�v��N�Q�����B���̔�Q�ɂ��āA�ƍߔ�Q�҂́A���Q�҂ɑ��ĕs�@�s�ׂɊ�Â����Q������������L����B���̑��Q�����ɂ��đ��`�I�ɐӔC���̂́A�����܂ł��Ȃ����Q�҂ł���B�������A�ƍߔ�Q�ғ���{�@�i�ȉ��u��{�@�v�Ƃ����B�j�̑O���ɂ���Ƃ���A���S�ň��S���ĕ�点��Љ���������邱�Ƃ́A�������ׂĂ̊肢�ł���ƂƂ��ɁA���̏d�v�ȐӖ��ł���A�ƍߓ���}�~���A���S�ň��S���ĕ�点��Љ�̎�����}��Ӗ���L�����X���܂��A�ƍߔ�Q�ғ��̐��Ɏ����X���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���Q�҂���ƍߔ�Q�҂ւ̑��Q�����͏\���ɍs���Ă��炸�A���ɔ�Q���d��Ȏ����ł́A���Q�҂Ɏ��͂��Ȃ����̗��R�ő��Q�������قƂ�Ǎs���Ă��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ͈ȑO����w�E����Ă����B�ƍߔ�Q�҂����Q�҂ɖ����i�ׂ��N���āA�ٔ��������Q�҂ɑ��Ďx���𖽂��锻�����̍����`���擾�����Ƃ��Ă��A�قƂ�ǎx���͂Ȃ��ꂸ�A�����`�͖��ʂɂȂ��Ă��܂����Ƃ������B
�Ⴆ�A�@���Ȃ����Q�����̎��Ԃɂ��čs�����Q�O�O�O�N�i�����P�Q�N�j�̒����i�ȉ��u�Q�O�O�O�N�̒����v�Ƃ����B�j�ł́A�E�l�����Ə��Q�v�������̔�Q�҈⑰�P�O�U�l�̂����A���������S�z�x����ꂽ�̂͂U�D�U���i�V�l�j�ɉ߂����A�U�W�D�X���ł́u�S���x�����Ȃ��A�x���̌����݂��Ȃ��v�Ƃ����ł������B
�Q�O�P�W�i�����R�O�j�N�ɓ��{�ٌ�m�A������{�����u���Q���������ɌW������`�̎������Ɋւ���A���P�[�g�����v�i�ȉ��u�Q�O�P�W�N�̃A���P�[�g�����v�Ƃ����B�j�ł��A�E�l���̔�Q�Ҏ��S���Ăł́A�����z�S�z����邱�Ƃ��ł������̂͋͂���S�D�S���ł������A�S���x�����Ȃ��������͖̂�V�R�D�U���ł������B�܂��A���Q���̐g�̔Ƌy�ѐ��ƍ߂܂Ŋ܂߂�A��߂�ꂽ�S�z�̎x�������҂���R�X���A�ꕔ�̎x���ɂƂǂ܂����҂���P�Q���A�S���x�����Ȃ������҂���S�W���ł������B�������A�S�z�̎x��������R�X���ɂ́A��Q�҂����z���������č��ӂ���i��̘a���⎦�k�ʼn����������Ă��܂ނ��Ƃ���A�S�z�̎x����������Ƃ����āA���̖�R�X���̎��đS�Ăɂ����ď\���Ȕ�Q���ʂ������Ƃ͂����Ȃ��B
�Q�O�P�W�N�A���P�[�g�����̉ɂ́A���Q�҂Ɏ��͂��Ȃ��A���Q�҂����ݕs���Ȃǂ̗��R�ʼn���ł��Ȃ������Ƃ������̂������������B
�Q�@���A����ɂ�����ƍߔ�Q�Ҏx���Ɋւ��邱��܂ł̌��c�E�錾
���A����ł́A�Q�O�O�O�i�����P�Q�j�N�P�O���P�R���Ɂu�ƍߔ�Q�Ҏx���̎��g�݂Ɋւ��錈�c�v�i�ȉ��u�����P�Q�N���c�v�Ƃ����B�j���s�����B�܂��A�Q�O�O�Q�i�����P�S�j�N�ɂ͔ƍߔ�Q�Ҏx�����e�[�}�ɃV���|�W�E�����s���u�ƍߔ�Q�Ҏx���̏[�����߂����錾�v�i�ȉ��u�����P�S�N�錾�v�Ƃ����B�j���s�����B
�����P�Q�N���c�ł́A���N�ɂ�����ƍߔ�Q�ҕی�֘A��@�i�u�Y���i�ז@�y�ь��@�R����@�̈ꕔ����������@���v�y�сu�ƍߔ�Q�ғ��̕ی��}�邽�߂̌Y���葱�ɕt������[�u�Ɋւ���@���v�j�����肳�ꂽ���A�����́u�ٔ��葱�Ɍ��肳�ꂽ���̂ł���A�ƍߔ�Q�҂ɑ���o�ϓI�x���A���_�I�x���Ȃǂ́A�ۑ�Ƃ��Ďc���ꂽ�܂܂ł���B�������A�ƍߔ�Q�҂̎x���́A����I�Ȋ�{���j�Ɋ�Â��āA�o�ϓI���ʁA���_�I���ʁA�Y���i�@�I���ʓ������ʂ��瑍���I�������I�ɍs��Ȃ���A���̎������������������B�ƍߔ�Q�҂��u����Ă���ߎS�Ȍ���Ɋӂ݂�A�ꍏ���������{�I�Ȗ@�������K�v�ł���B�v�Ƃ��āA���ɔƍߔ�Q�Ҋ�{�@�̐�������߂��B
�����P�S�N�錾�ł́A��ė��R�ɂ����āu��Q�҂̍��Y�I��Q�̕⏞�ɂ��ẮA�ƍߔ�Q�ғ����t���x���@�ɂ�鋋�t���x���^�p����Ă���A�Q�O�O�P�i�����P�R�j�N�V���ɂ͖@�������Ȃ��ꂽ���̂́A���̐��x�ɂ́A�Ώ۔�Q�͈̔͂ɐ����������A���������t���z���Ȃ���z�ł���_�ŁA��Q�҂₻�̈⑰�̖�����ɂ͎����Ă��Ȃ��B�v�Ǝw�E���A���錾�ł͖`���Ŕƍߔ�Q�҂́u�o�ϓI�ɂ͂��Ƃ��A�g�̓I�E���_�I�ɂ����S�������Y����B���ɔ�Q��������̏Ռ��͐r��ł���A���̗�������̂��߂Ɋe��̎x�����K�v�ł���B�v�Əq�ׂāA�ƍߔ�Q�҂ٌ̕�m�ւ̃A�N�Z�X��Q�̉������Ɏ��g�ނ��Ƃ�錾�����B
�R�@�ƍߔ�Q�҂����Q���Ă��Ȃ��͕ς���Ă��Ȃ�����
����猈�c��錾����Q�O�N�ȏ�o�߂������݁A�ƍߔ�Q�҂ɑ���x�����i�݁u�ƍߔ�Q�҂��u����Ă���ߎS�Ȍ���v�͉��P���ꂽ�̂ł��낤���B�Q�O�O�O�N�i�����P�Q�N�j�ȍ~�A���ƍ߁E���\�͔�Q�҂̂��߂̃����X�g�b�v�x���Z���^�[���e�s���{���ɐݒu����A�܂��A�ߎ��A�ƍߔ�Q�ғ��x�����̐��肪�S���̓s���{���y�юs�����Ő����i�߂��Ă���A�����x�ƍߔ�Q�҂ɑ���x�����i��ł����B�ƍߔ�Q�҂̑��Q�ɂ��ẮA�Q�O�O�W�i�����Q�O�j�N�ɑ��Q�������ߐ��x����������A���Q���������̎������̌��オ���҂��ꂽ�B�Q�O�P�W�N�̃A���P�[�g�����i���������S�X�S���j�ł́A�����`�⎦�k���쐬���̈��̐��ʂ��������R�U�S���̂����A���Q�������߂��P�S�O���Ɩ�R�W�D�T�����߂Ă���B
�������A�O�q�̂Ƃ���A�Q�O�P�W�N�̃A���P�[�g�����ł́A�E�l���̔�Q�Ҏ��S���Ăł́A�����z�S�z����邱�Ƃ��ł������̂͋͂���S�D�S���ł������A�S���x�����Ȃ��������͖̂�V�R�D�U���ƁA�Q�O�O�O�N�̒�������S�����P�݂͂��Ă��Ȃ��B���̂悤�ɔƍߔ�Q�҂̑������A���Q���Ă��Ȃ��͉���ς���Ă��Ȃ��̂ł���B
�S�@�s�\���Ȕƍߔ�Q�ҋ��t���̎x��
���̂悤�ɁA���Q���Ă��Ȃ��ƍߔ�Q�҂́A�\���Ȍo�ϓI�x�����Ă���̂ł��낤���B
�ƍߔ�Q�ғ����t���̎x�����ɂ��ƍߔ�Q�ғ��̎x���Ɋւ���@���i�ȉ��u�Ƌ��@�v�Ƃ����B�j�Ɋ�Â��ƍߔ�Q�ғ����t�����x�́A������P�X�V�S�i���a�S�X�j�N�̎O�H�d�H�r�����j�������_�@�ɂP�X�W�O�i���a�T�T�j�N�ɐ��肳�ꂽ�B
���̌�A�Ƌ��@�́A�т��̉������d�ˁA���ɕ����P�R�N�ɂ́A���t���̎x���z����������Ԕ����ӔC�ی��i�����Ӂj���݂Ɉ����グ����A����܂ł̈⑰���t���A��Q���t���ɉ����āA�d���a���t�����n�݂��ꂽ�B
�������A�Ƌ��@�ɂ�鋋�t���̎x���͂��܂��ɏ\���ł���Ƃ͌�����B
�x�@�������\�����ߘa�R�N�x�̔ƍߔ�Q���t���̎x���ْ�z�̕��ς́A�⑰���t������U�U�S���~�ł���B����ł͑��Q���Ȃ������⑰�ɑ���o�ϓI�x���Ƃ��Ė��炩�ɕs�\���ł���B��Q���t������R�U�Q���~�Ɏ~�܂��Ă���B
�Ⴆ�A���{�ٌ�m�A����{�N�R���Ɍ��\�����u�ƍߔ�Q�ғ��⏞�@��������߂�ӌ����v�ŏЉ�ꂽ����ł́A�q�ǂ��Q�l���E�Q���ꂽ�����T�O��̒j���́A�c���ꂽ�ȂƎq�Ƃ̂R�l�Ő����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B��������͎���ł���A�q�ǂ����E�Q���ꂽ����ɏZ�ݑ����邱�Ƃ͂ł����]���������A����͏Z��[�����c���Ă��蔄�p���ł����A�Z�ނ��Ƃ̂ł��Ȃ�����̃��[�����x���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��Q�҉Ƒ��ɂ��Ă̌�����ɂ���排������A���ꏊ���������j���͐��_�Ȃ���f����悤�ɂȂ�A�܂��E���ꂽ�q�ǂ��̌��ǂ��Ď��̂��Ƃ���Ȃ���ڂ𗣂����Ƃ��ł����A�ސE��]�V�Ȃ����ꂽ�B��������X������A��Q�҂Q�l���̈⑰���t���Ƃ��Čv��U�W�O���~���x�����ꂽ���A�������r�₦���⑰��̐������܂��Ȃ��ɂ͗]��ɕs�\���Ȋz�ł���B�܂��A���Q�҂͎��E���Ă���A�j����⑰�͉��Q�҂ɑ��Q���������߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��A�Ƃ̂��Ƃł���B
�T�@��{�@�̊�{���O�Ƃ��Ă̔ƍߔ�Q�҂̌���
��{�@�̑�R���P���́A��{���O�Ƃ��āu���ׂĔƍߔ�Q�ғ��́A�l�̑������d���A���̑����ɂӂ��킵��������ۏႳ��錠����L����B�v�ƒ�߂Ă���B���̌����́A�u���ׂč����́A�l�Ƃ��đ��d�����v�ƒ�߂���{�����@��P�R���ɍ�����L������̂Ɖ�����ׂ��ł���B
�ƍߔ�Q�҂��u�����̎�́v�Ƒ����邱�Ƃ́A���ۓI�Ɍ���A�P�X�W�T�i���a�U�O�j�N�ɍ��A����ō��A��Q�Ґl���錾�i�u�ƍ߂���уp���[���p�̔�Q�҂̂��߂̐��`�Ɋւ����{�����錾�v�j���̑�����A����X�^���_�[�h�ȍl�����ƂȂ��Ă���B
�����āA���̍��A��Q�Ґl���錾�ł́A�ƍߔ�Q�҂̑��Q�A�o�ϓI�⏞�ɂ���
��W���u��Q�ُ��v�̒��ŁA
�u���Ȃ̍s�ׂɐӔC�̂���ƍߎ҂܂��͂��̊W�҂́A�Ó��ȏꍇ�ɂ́A��Q�ҁA���̉Ƒ��܂��͔�}�{�҂ɁA�����Ȕ�Q�ُ����s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̔�Q�ُ��Ɋ܂܂��̂́A���Y�̕ԊҁA����������Q�܂��͑��Q�ɑ���x���A��Q�̌��ʔ���������p�ٍ̕ρA�T�[�r�X�̒A�����̉ł���B�v
�܂��A��P�Q���u��Q�⏞�v�̒��ŁA
���̔�Q�҂��A�ƍߎ҂܂��͂���ȊO����\���ȕُ����Ȃ��ꍇ�ɂ́A���Ƃ́A�o�ϓI�⏞���s�Ȃ��悤�w�͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
a �d��Ȕƍ߂̌��ʁA�g�̂ɂ��Ȃ�̔�Q���A�܂��͐g�̂�_�̌��N�ɑ���������Q��
b ����������Q�̂��߂Ɏ��S�����҂܂��͐g�̓I����ѐ��_�I�s�\�ɂȂ����҂̉Ƒ��A���ɔ�}�{��
����ɑ�P�R���ŁA
��Q�ҕ⏞����̑n�݁A��������ъg�[�̓w�͂�����K�v������B����������Q�҂ɂȂ������Ƃ����̔�Q��⏞���闧��ɂȂ��ꍇ�Ȃǂł́A�K�ł���A�⏞�ړI�̂��߂ɁA����ȊO�̊����n�݂�����@���l������B
�ƒ�߂Ă���B
�������A����܂łɏq�ׂ��Ƃ���A���Ȃ��A�ƍߔ�Q�҂͏\���ȑ��Q�y�ьo�ϓI�⏞���邱�Ƃ��ł��Ă��炸�A�O�L�̍��A��Q�Ґl���錾�ɒ�߂�ꂽ���Ƃ͎�������Ă��Ȃ��B�ƍߔ�Q�҂́A��{�@��R���P���̒�߂�u�l�̑������d���A���̑����ɂӂ��킵��������ۏႳ��錠���v�������Ȃ��N�Q���ꑱ���Ă���̂ł���B
��{�@�O���ł́u�����̒N�����ƍߔ�Q�ғ��ƂȂ�\�������܂��Ă��鍡�����A�ƍߔ�Q�ғ��̎��_�ɗ������{����u���A���̌������v�̕ی삪�}����Љ�̎����Ɍ����ĐV���Ȉ���ݏo���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƌ��ӂ���Ă���B��{�@�����肳��ĊԂ��Ȃ��Q�O�N���o�Ƃ��Ƃ��Ă���̂ł���A�ƍߔ�Q�҂��\���ȑ��Q�y�ьo�ϓI�⏞�����Ă��Ȃ��͒����ɉ��P����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�U�@���Q�̎������m�ۂ̂��߂Ɂi����ɂ��ƍߔ�Q�Ҏx���ٌ�m���x�̑n�݁j
���{�̌Y�������ł́A�ƍߔ�Q�҂Ƃ̎��k���������̉�����i�̈�Ƃ��Ē蒅���Ă���B�������A���Q�ґ�����̎��k�̐\����́A���������㑁���ɍs���A�ƍߔ�Q�҂������㍬��������Ԃɂ��钆�ŁA�@���I�ȏ�����@����Ȃ��܂܁A���k��������Ă��܂����Ƃ������݂���B���k�ł́A���Q�ґ��̎���ɂ��ʏ�̑��Q���������ŎZ�肳��鑹�Q�z�����Ⴂ���z������Ă���ɂ�������炸�A���̎x���ƈ������ɁA���Q�҂��u�G���v����A�Ƃ������e����Ă���邱�Ƃ������B�����������k�̖@���I�ȈӖ����\���ɗ������Ȃ��܂܁A�ƍߔ�Q�҂͎��k��������Ă��܂�������邱�Ƃ�����B
�ƍߔ�Q�҂����k�ɂ���ēK�ȑ��Q����悤�ɂ���ɂ́A���Q�ґ��������鎦�k�̓��e�ɂ��āA�ٌ�m����K�ȃA�h�o�C�X���A���Y�ٌ�m���ƍߔ�Q�҂̑㗝�l�Ƃ��ĈϔC���A���Q�ґ��ƌ����s�����Ƃ��K�v�ł���B�܂��A���k�ɂ���ēK�ȑ��Q�������Ȃ��ꍇ�ł��A�ƍߔ�Q�҂ɕٌ�m���㗝�l�Ƃ��ďA���A���Q�������ߐ\���▯���i�ד��̖@�I�葱�𗘗p���������ŁA�K���Ȕ����z���F�߂���ׂ��ł���B
���̂��߂ɂ́A�����������ォ��A�ƍߔ�Q�҂��ٌ�m�Ɉ˗��ł���悤�ɂ���ׂ��ł���A��^�ҁE�퍐�l�̍��I�ٌ쐧�x�Ɠ��l�ɁA�ƍߔ�Q�҂ɂ�����ŕٌ�m���˗��ł���A�ƍߔ�Q�Ҏx���ٌ�m���x�𑁋}�ɑn�݂��ׂ��ł���B
������������ɔƍߔ�Q�҂ɍ~�肩������́A���k���̑��Q�̖�肾���łȂ��A���ɎЉ�I�ɒ��ڂ��W�߂鎖���ł́A�ƍߔ�Q�҂̂��ƂɃ}�X�R�~���E������A�Ƃ��������f�B�A�Ή��̖��������ɉ������Ă��炸�A�����������̑Ή��̂��߂ɂ��A�����������ォ��ƍߔ�Q�҂��ٌ�m�Ɉ˗��ł���悤�ɁA�ƍߔ�Q�Ҏx���ٌ�m���x�𑁋}�ɑn�݂���K�v������B���̓_�ɂ��ẮA���{�ٌ�m�A����A�Q�O�P�X�i�ߘa���j�N�Ɂu����ɂ��ƍߔ�Q�Ҏx���ٌ�m���x�̓��������߂�ӌ����v�o���A�{�N�S���ɁA���R����}����������i�@���x������̔ƍߔ�Q�ғ��ی�E�x���̐��̈�w�̐��i��}��o�s�����\�����u�ƍߔ�Q�ғ��{��̈�w�̐��i�̂��߂̒i�āj�v�i�ȉ��u�����}�āv�Ƃ����B�j�ɂ����Ă��u��Q�Ҏx���ٌ�m���x�̑n�݁v�����߁A�{�N�U���ɂ́A���{���ƍߔ�Q�ғ��{�����i��c�ɂ����Ĕƍߔ�Q�Ҏx���ٌ�m���x�̑������������肵���B
�����������{�̑Ή��͕]�����ׂ��ł���A�ƍߔ�Q�Ҏx���ٌ�m���x�̑n�݂Ɍ���������̎��g�݂����҂����B���̍ۂɁA�̐S�Ȃ��Ƃ́A���{�́A�ƍߔ�Q�҂̎��͂ɂ�����炸�A�ƍߔ�Q�҂���Q���ォ��ٌ�m�Ɉ˗��ł��鐧�x�����邱�Ƃł���B��Q����̔ƍߔ�Q�҂́A�ٌ�m�ɃA�N�Z�X���邽�߂̏�Ȃ������łȂ��A�ٌ�m�ɃA�N�Z�X����C�͂���Ȃ��悤�ȏɂ��邱�Ƃ������B���̂悤�Ȕƍߔ�Q�҂���Q���ォ��ٌ�m�Ɉ˗��ł���悤�ɂ��邽�߂ɂ́A�����A����ɂ��A�ƍߔ�Q�҂���Q���ォ��ٌ�m�Ɉ˗��ł��鐧�x����邱�Ƃ��s���ł���B
�܂��A���̐��x���������ꂽ�Ƃ��Ă��A���Q�������ߐ\���������ًc���Ŗ����i�葱�Ɉڍs�����ꍇ��A�ƍߔ�Q�҂����Q�҂ɖ����i�ׂ��N����ق��Ȃ��ꍇ�ɂ́A���ɔ�Q���d��Ȏ����قǐ����z�����z�ƂȂ邽�߁A�ٔ����Ɏ��߂�萔���i�ȉ��u��v�Ƃ����B�j�����z�ƂȂ�A�ƍߔ�Q�҂����Q�������ߐ\����i�ג�N���S�O���錴���ɂȂ�B����ɁA���Q�������߂▯���������̍����`���Ƃ��Ă��A���Q�҂��甅���̎x������ꂸ�����Ԃ��o�߂����ꍇ�ɂ́A���Ŏ����̊����P�\�̂��߂ɍĂі����i�ׂ��N���邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�B
�����i�ז@��̑i�~�����F�߂��Ȃ��ꍇ�ɂ́A��Q�҂͍����`�邽�߂̈�S���Ȃ���Ȃ炸�A�ŏI�I�ɍ����`���Ƃ��Ă��A���Q�҂Ɏ��͂��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�シ���������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���̂悤�Ȏ��Ԃ�h�����߂ɂ��A���́A�ƍߔ�Q�҂̍s�������i�ד��̍ٔ��葱��p�̉������s���ׂ��ł���B
�V�@�ƍߔ�Q�҂����Q�y�ѕ⏞���錠�����߂��ƍߔ�Q�ғ��⏞�@�̐���
�Ƌ��@�ɂ�鋋�t���̎x���́A�O�q�̂Ƃ���A�������s�\���ł���B
�Ƌ��@�̖��_�Ƃ��ẮA����܂łɂ��g�Ɏw�E����Ă����悤�ɁA�@���@�̖ړI���߂���P���ɂ����āu�ƍߍs�ׂɂ��s���̎��𐋂����҂̈⑰���͏d���a���Ⴕ���͏�Q���c�����҂̔ƍߔ�Q���𑁊��Ɍy������v�ƒ�߂āA�K�p�Ώۂ����肵�Ă��邱�ƁA�A�⑰���t���̎Z��ɂ������āA�����O�̔ƍߔ�Q�҂̎����ɉ�������b�z�ɂ��̐��v�ێ��W�⑰�̐l���ɉ������{�����|���ĎZ�o���A�편���v���l�����Ȃ����߁A�����̂Ȃ��A�������͎����̏��Ȃ��ƍߔ�Q�҂��S���Ȃ����ꍇ�̎x���z���ɂ߂Ē�z�ł��邱�ƁA�B��U���ŋ��t���̑S�����͈ꕔ���x�����Ȃ��ꍇ���߂Ă���A���t�������z�܂��͕s�x���ƂȂ�ꍇ���L�͂ɔF�߂��Ă��邱�ƁA����������B
���̂����A��L�A�̋��t���̎Z����@�ɂ��ẮA�����}�Ăł����t��b�z��{���ݒ���������ȂǁA�K���������̌��I���t���x�̎Z����@�ɂƂ���Ȃ����������s���ׂ��ł���Ƃ̒��Ȃ���A�{�N�U���̔ƍߔ�Q�ғ��{�����i��c�ɂ����āA���{�͎Z����@���������Ė����i�ׂł̑��Q�����z����������������s�����Ƃ����肵�Ă���B
�������A�Ƌ��@�̖��̍��{�́A�Ƌ��@�̖ړI���A�ƍߔ�Q�҂ɑ���o�ϓI�⏞���s�����̂ł���A�Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ��_�ɂ���B
�Ƌ��@�̎�|�́u�̈ӂ̔ƍߍs�ׂɂ���Q�����҂܂��͂��̈⑰���A���@��͕s�@�s�א��x������Ȃ���A�����㑹�Q���������Ȃ��ꍇ�������A�Ƃ��������O��Ƃ��āA����ΎЉ�A�ы����̐��_�������āA�Љ�I�ɋC�̓łȗ���ɂ���ƍߔ�Q�҂̔�Q�̊ɘa�������悤�Ƃ�����́v�ł���A���t���́u�������I�Ȑ��i�v��L���Ă���Ɛ�������Ă���i��J���E�V�������u�ƍߔ�Q���t���x�v�i�L��t�V���j�U�O�Łj�B�������������́A�Ƌ��@�����肳�ꂽ�P�X�W�O�i���a�T�T�j�N��ɂȂ��ꂽ���̂ł���A���ꂩ��S�O�N�߂����o�߂����B���̊Ԃɂ́A�Ƌ��@�������̉������Ȃ���A���t���̎x���Ώۓ����g���Ă��Ă͂���B�������Ȃ���A�ƍߔ�Q�҂̑��Q�y�ьo�ϓI�⏞���\���ɂȂ���Ă��Ȃ�����ɂ��邱�Ƃ͂���܂ŏq�ׂĂ����Ƃ���ł���A�{�N�U���̔ƍߔ�Q�ғ��{�����i��c�ɂ����鐭�{�̌���Ɋ�Â������ɂ����Ă��A�Ƌ��@�̎�|���A�ƍߔ�Q�҂Ɍo�ϓI�⏞���s���A�ƍߔ�Q�҂̌�����ۏႷ�邱�Ƃ�ړI�Ƃ�����̂ւƕς��Ȃ�������A�ƍߔ�Q�҂̏\���ȑ��Q�y�ьo�ϓI�⏞���}����Ƃ͎v���Ȃ��B
�O�q�̂Ƃ���A��{�@�͑�R���P���ŁA�ƍߔ�Q�҂ɂ́u�l�̑������d���A���̑����ɂӂ��킵��������ۏႳ��錠���v��F�߂Ă���A�ƍߔ�Q�҂����Q�A��Q�̕⏞�����߂邱�Ƃ́A�ƍߔ�Q�҂̌����ł���B
��{�@�����肳��ĊԂ��Ȃ��Q�O�N�������A�x���Ɏ����邪�A��{�@��R���̊�{���O�ɂ̂��Ƃ�A�ƍߔ�Q�҂����Q�y�ьo�ϓI�⏞���錠�����߂��ƍߔ�Q�ғ��⏞�@��V���ɐ��肷�ׂ��ł���B
��̓I�ɂ́A�O�L�U�̑��Q�̂��߂̐��x�������Ƃ��Ă��A�Ȃ��A���Q�҂Ɏ��͂��Ȃ��x�������Ȃ��ꍇ�͑����c����̂ƍl������B�܂��A���{���j�Ɋ�Â��Ƌ��@�̉������Ȃ��ꂽ�Ƃ��Ă��A�����i�ׂ̑��Q�����z�ɔ�ׂĔ�Q�҂̑��Q�y�ьo�ϓI�⏞���\���ɐ}���Ȃ��ꍇ��������\��������B���̂��߁A���́A�ƍߔ�Q�҂̑��Q�y�ьo�ϓI�⏞�̂��߂̐��x�{�I�Ɍ������A�ƍߔ�Q�҂̗L���鑹�Q�����������i�����`�j�̗��֕����x��݂���ׂ��ł���B�܂��A���Q�҂��s���ł�������A���Q�҂��ӔC���\�͂ł���ȂǁA���Q�҂ɑ��鑹�Q���������ɂ��č����`���擾�ł��Ȃ��ꍇ�����邽�߁A���������P�[�X�ɂ��ẮA���֕����x�Ɠ����̕⏞��ƍߔ�Q�҂ɑ��čs���ׂ��ł���B����ɁA���A��Q�Ґl���錾��P�R���Łu��Q�ҕ⏞����̑n�݁A��������ъg�[�̓w�͂�����K�v������B�v�ƒ�߂�Ƃ���A���̂��߂̍������m�ۂ��A��������ъg�[�����ׂ��ł���B
�W�@�n�������c�̂��������𐧒肵�A�ƍߔ�Q�҂̌o�ϓI�x�����s������
(1) �n�������c�̂ɂ�����������̐���
��{�@�́A�ƍߔ�Q�Ҏx���̂��߂̎{��̍���y�ю��{�ɂ��āA��S���ŁA��{���O�ɂ̂��Ƃ�A���ɐӖ�������Ƃ��A�����ɑ�T���ŁA�n�������c�̂ɑ��Ă��A��{���O�ɂ̂��Ƃ�A���Ƃ̓K�Ȗ������S�܂��āA���̒n�������c�̂̒n��̏ɉ������{������肵�A�y�ю��{����Ӗ���L����A�ƒ�߂Ă���B
�n�������c�́A���Ɏs�����́A�Z���̈�l�ł���ƍߔ�Q�҂ɂƂ��ė��邱�Ƃ̂ł���ł��g�߂ȑg�D�ł���A��{�@�O���́u�ƍ߂�}�~���A���S�ň��S���ĕ�点��Љ�̎�����}��Ӗ��v��ϋɓI�ɉʂ����Ă������Ƃ����߂���B��{�@�̊�{���O���߂���R���Q���ł́u�ƍߔ�Q�ғ��̂��߂̎{��́A��Q�̏y�ь����A�ƍߔ�Q�ғ����u����Ă�����̑��̎���ɉ����ēK�ɍu��������̂Ƃ���B�v�ƒ�߁A�܂������R���Łu�ƍߔ�Q�ғ��̂��߂̎{��́A�ƍߔ�Q�ғ����A��Q�����Ƃ�����Ăѕ����Ȑ������c�ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂ł̊ԁA�K�v�Ȏx������r��邱�ƂȂ��邱�Ƃ��ł���悤�A�u��������̂Ƃ���B�v�ƒ�߂Ă���B����������{���O���������邽�߂ɂ́A�ł��g�߂ȑg�D�ł���n�������c�̂��A���ƂƂ��ɔƍߔ�Q�҂̎x���ɂ����邱�Ƃ��K�v�ł���B�����ꎩ�����ƍߔ�Q�҂ɂȂ��Ă��A�ƍߔ�Q�҂̌������ۏႳ�ꂽ�s�����������A���S�ň��S���ĕ�炷���Ƃ��ł���s�����ł���Ƃ�����B
�ߔN�A�n�������c�̂̒��ł��A�s���{���ł́A�S���I�ɁA��������S�E���S�܂��Â�����̒��ɔƍߔ�Q�Ҏx���ɂ��Ă̋K���u�������ł͂Ȃ��A�ƍߔ�Q�Ҏx���ɓ��������ƍߔ�Q�ғ��x�����i���������ƍߔ�Q�ғ��x�����́u�������v�Ƃ�����B�j�̐��肪�i�B�������A�ߘa�T�N�Ŕƍߔ�Q�Ҕ����ɂ��A�s�����ɂ�����������̐���́A�ߘa�T�N�S���P�����݂ŁA���ߎw��s�s�ł͂Q�O�c�̂̂����P�R�c�́A���ߎw��s�s�ȊO�̎s�撬���ł͂P�V�Q�P�c�̂̂����U�O�U�c�̂Ɏ~�܂��Ă���B�Z�����ƍߔ�Q�ɑ����Ă��A���Q���܂߂��ƍߔ�Q�҂̌�����ۏႷ�邽�߂ɂ́A�������s�����ɂ����ē������𐧒肷�邱�Ƃ��A��{�@��T���̒n�������c�̂̐Ӗ����ʂ������߂ɕK�v�ł���B
(2) �n�������c�̂ɂ�����o�ϓI�x���̓���
�ƍߔ�Q�҂ɑ���o�ϓI�x���Ƃ��āA�n�������c�̂ɂ����āu�������v��u�x�����v���̖��̂ŋ��K�̎x�����s�����x������Ƃ��낪�݂��A�ߘa�T�N�Ŕƍߔ�Q�Ҕ����ɂ��A�ߘa�T�N�S���P�����݂ŁA�s���{���P�U�c�́A���ߎw��s�s�P�S�c�́A���ߎw��s�s�ȊO�̎s�撬���ł͂U�R�P�c�̂����肵�Ă���B���ł����Ɍ����Ύs�ł́A���Q�҂ɑ��鑹�Q�����������ɂ��č����`��L����ƍߔ�Q�҂ɑ��A�R�O�O���~������Ƃ��ė��֕����s�����x��݂��Ă���B���Ɍ����Ύs�ł́A����ȊO�ɂ��A���Q�҂��S�_�r�����ŌY���ӔC�����Ȃ����̗��R�ɂ�藧�֎x�����̎x�������Ȃ��⑰�ւ̓��ዋ�t���A�����`�Ɋ�Â��Ė������s�@��̍��Y�J���葱�y�ё�O�҂���̏��擾�葱���s���ꍇ�̔�p�⏕�A���Ŏ����̊����P�\�̂��߂̍Ē�i���̔�p�⏕�Ȃǂ�������ɐ��荞��ł���A��i�I�Ȏ�g�Ƃ��Ē��ڂ����B
�O�q�̂Ƃ���A�����A����A���{���j�Ɋ�Â��Ƌ��@�̉������s�����Ƃ��Ă��A�����i�ׂ̑��Q�����z�ɔ�ׂĔ�Q�҂̑��Q�y�ьo�ϓI�⏞���\���ɐ}���Ȃ��ꍇ��������\��������B���̂��߁A�n�������c�́A���Ɏs�����́A���Ƃ͕ʂ̊ϓ_����A�Z���̈�l�ł���ƍߔ�Q�҂ɂƂ��ė��邱�Ƃ̂ł���ł��g�߂ȑg�D�Ƃ��āA�d�w�I�Ȍo�ϓI�⏞���s���A���A�e��葱��p�̕⏕�荞�������𐧒肷�邱�Ƃ����߂���B
(3) �n�������c�̂ɑ��A�������̐�������߂邱��
�n�������c�̂́A�ƍߔ�Q�҂ɍł��g�߂ȑg�D�Ƃ��āA�ƍߔ�Q�҂ɑ���o�ϓI�x�����s���Ă������Ƃ��K�v�ł���A���̂悤�Ȏx�����s���Ă���n�������̂������A��{�@�O���́u���S�ň��S���ĕ�点��v�܂��ł���Ƃ�����B���ɁA�s�����ɂ����ẮA�ƍߔ�Q�҂̌�����ۏႵ�A��{�@��T���̒�߂�Ӗ����ʂ������߁A�������̐���A�y�сA�ƍߔ�Q�҂̑��Q�̂��߂̌o�ϓI�x���𐄂��i�߂Ă������Ƃ��K�v�ł���B
���̂��߁A���A����ɏ�������e�P�ʉ�A�ƍߔ�Q�����Ғc�́A�ƍߔ�Q�Ҏx���c�́A�n�������c�́A�@�֓��ɃA�v���[�`���A�����������A�n�������c�̂���A���Q���������̗��֕����x���܂߂��������̐�������߂銈����ϋɓI�ɍs���Ă������Ƃ��K�v�ł���B
�X�@����
�ȏ���ӂ܂��A���A����́A�ƍߔ�Q�ғ���{�@�̊�{���O�ɂ̂��Ƃ�A�ȉ��́i�P�j�Ȃ����i�R�j�̐��x���̎��������y�ђn�������c�̂ɋ��߂�ƂƂ��ɁA���A����ɏ�������e�P�ʉ�i�S�j�̊������s�����Ƃ�錾���邱�Ƃ��Ă��鎟��ł���B
�i�P�j�ƍߔ�Q�҂̑��Q�̎������m�ۂɎ����邱�Ƃ���A�����A����ɂ��A�ƍߔ�Q�҂���Q���ォ��ٌ�m�Ɉ˗��ł��鐧�x������ƂƂ��ɁA�ƍߔ�Q�҂̍s�������i�ד��̍ٔ��葱��p�̉������s�����ƁB
�i�Q�j�����A�ƍߔ�Q�҂����Q�y�ьo�ϓI�⏞���錠�����߂��ƍߔ�Q�ғ��⏞�@�𐧒肷�邱�ƁB��̓I�ɂ́A�����A�ƍߔ�Q�҂̗L���鑹�Q�����������̗��֕����x��݂��邱�ƁA�܂��A�ƍߔ�Q�҂����Q�҂ɑ��鑹�Q���������̍����`���擾�ł��Ȃ��ꍇ�ɂ́A���֕����x�Ɠ����̕⏞��ƍߔ�Q�҂ɑ��čs�����ƁA�y�т��̂��߂̍������m�ۂ��A��������ъg�[���邱�ƁB
�i�R�j�n�������c�̂��A���Q���������̗��֕����܂߂��ƍߔ�Q�҂̌o�ϓI�x�����s�����ƁA�y�т��̂��߂̍������m�ۂ��A��������ъg�[���邱�ƁB���Ɏs�����͓������𐧒肵�A�ƍߔ�Q�҂̌�����ۏႵ�A���Q���߂̌o�ϓI�x�����s�����ƁB
�i�S�j���Q�̎������m�ۂ��\���ɍs���Ă��Ȃ�������ӂ܂��āA���A����ɏ�������e�P�ʉ�́A�ƍߔ�Q�����Ғc�́A�ƍߔ�Q�Ҏx���c�́A�n�������c�́A�@�֓��ɃA�v���[�`���A�����������A�n�������c�̂���A���Q���������̗��֕����x���܂߂��������̐�������߂銈����ϋɓI�ɍs�����ƁB
�ȏ�